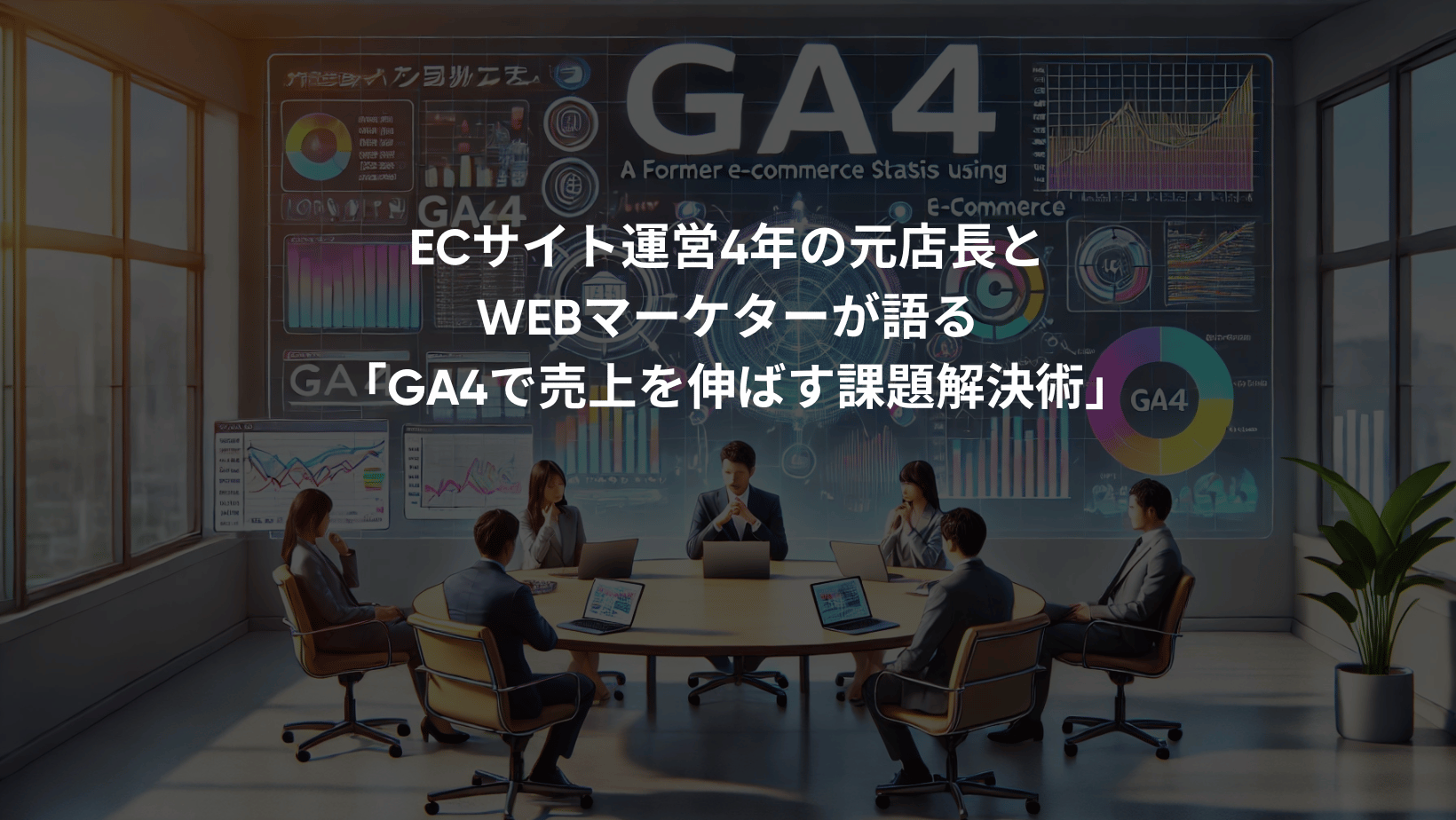企業マーケに効く「ショートドラマ」徹底解説
~ショート動画とは違う、物語がブランドを動かす時代~
SNS動画の急速な普及により、企業のマーケティング手法も大きく変化しています。TikTokやYouTube Shorts、Instagram Reelsといった短尺動画の台頭によって、数秒で消費者の心をつかむ“ショート動画”が主流となりました。
一方で、近年はこの流れの先にある**「ショートドラマ」**という新しい表現手法が注目を集めています。
ショートドラマとは、わずか1〜3分の中にストーリー性を持たせ、視聴者の共感や感情を動かす短編映像コンテンツのこと。単に商品やサービスを紹介するだけでなく、**“物語を通じてブランドの価値観を伝える”**という点で、従来のショート動画とは大きく異なります。
本記事では、このショートドラマがなぜ企業マーケティングに効果的なのかを、ショート動画との違いや事例を交えながら解説していきます。
「認知から共感へ」「一瞬から記憶へ」──その変化の背景と、企業が今取り組むべき新しいストーリーテリング戦略を見ていきましょう。
- 企業マーケで“ショートドラマ”が注目される背景
- 「ショート動画」と「ショートドラマ」の違い
- 成功事例:ショートドラマで成果を上げた企業たち
- 効果の違い:ショートドラマがもたらす3つの価値
- 企業がショートドラマを制作する際の設計指針
- まとめ:今後の展望:AI×ショートドラマ、共創の時代へ
1.企業マーケで“ショートドラマ”が注目される背景
近年、TikTokやYouTube Shorts、Instagram Reelsなどのプラットフォームを中心に、短尺動画コンテンツの視聴が日常化しています。数秒〜数十秒の情報をテンポよく消費するスタイルが一般化するなかで、企業マーケティングにおいても「短い時間でいかに印象を残すか」が課題となっています。
しかしその一方で、「単なる短い動画広告」ではなく、物語性を持ったショートドラマ型の動画が注目を集めています。
その理由は明快です。
ユーザーが「広告」としてではなく「コンテンツ」として視聴できるからです。
特にZ世代・ミレニアル世代のように“企業の価値観や世界観への共感”を重視する層にとって、数分間のストーリーはブランドへの心理的距離を一気に縮める効果があります。
つまり、ショートドラマは「伝える」から「感じさせる」マーケティングへの転換点となっているのです。

2.「ショート動画」と「ショートドラマ」の違い
まず整理しておきたいのは、「ショート動画」と「ショートドラマ」は同じ“短尺動画”でありながら、マーケティング上の目的も効果もまったく異なるということです。
| 項目 | ショート動画 | ショートドラマ |
|---|---|---|
| 主な目的 | 認知拡大・トレンド参加・瞬間訴求 | ブランド理解・共感醸成・感情訴求 |
| 長さ | 数秒〜30秒前後 | 1〜3分(物語として成立) |
| 内容構成 | 単発・断片的 | 起承転結をもつ脚本形式 |
| 成果指標 | 再生数・CTR・エンゲージメント率 | 視聴完了率・ブランドリフト・共感度 |
| 強いSNS | TikTok・Instagram Reels | YouTube Shorts・TikTok・X動画など |
| 向いている商材 | ファッション、コスメ、飲料など直感型 | サービス、採用、ブランド価値訴求型 |
ショート動画が“トレンドやリズム感”で一瞬の注目を集めるのに対し、ショートドラマはストーリーテリングを通じて「心に残る体験」を生み出すことに重きを置きます。
言い換えれば、ショート動画が“瞬発力”で動かすのに対し、ショートドラマは**“持続的なブランド浸透力”**で効かせる手法です。
3.成功事例:ショートドラマで成果を上げた企業たち
花王|“共感の日常”でブランド信頼を醸成
花王は、家庭や職場など“日常の小さなドラマ”を描くショートドラマを継続的に展開しています。
特に「#これが私のスタイル」シリーズでは、洗剤やスキンケアなどの商品を前面に出すのではなく、**「人の生き方」や「価値観」**に焦点を当てた構成が特徴です。
たとえば、働く女性が忙しい日々の中で小さな達成感を得る瞬間を描いたエピソードでは、製品名がほとんど登場しないにもかかわらず、「花王らしい優しさを感じる」「こんな動画をもっと見たい」といったコメントが多数寄せられました。
花王の狙いは、商品の訴求ではなく、ブランドが持つ“やさしさ”や“共感”の世界観を伝えること。その結果、広告ではなく“コンテンツ”として自然に受け入れられ、ブランド好感度の維持・向上に寄与しています。
サントリー|シリーズ化による“キャラクター愛着形成”
サントリーは、若年層向けアルコールブランド「ほろよい」のショートドラマシリーズで大きな成功を収めました。
短編ドラマの中で、登場人物たちが日常の中で「ほろよい」を囲んで語り合う姿を通して、**“リラックスできる自分時間”**というブランドコンセプトを視覚的に体験させています。
このシリーズでは、俳優を固定し、エピソードを連続展開することでキャラクターへの愛着を育成。
YouTubeやXでは「次回が気になる」「登場人物たちの関係性に共感できる」といった感想が投稿され、**CMでありながらファンが続編を待ち望む“ドラマコンテンツ化”**に成功しました。
さらに、シリーズ展開を通じて「ブランドが発信するストーリー」から「視聴者が共に楽しむ物語」へと進化し、“共感型ブランドコミュニティ”の形成につながっています。

マクドナルド|“青春ストーリー”でブランド体験を再定義
マクドナルドのショートドラマは、若者たちの放課後・友情・恋愛といった青春の一場面にブランドを溶け込ませる手法が特徴です。
たとえば「マックに行こうぜ」シリーズでは、学校帰りに立ち寄るワンシーンを通じて、マクドナルドが“ただの飲食店”ではなく“コミュニケーションの場”として描かれています。
この手法の優れている点は、「商品訴求」ではなく「体験価値の可視化」にあります。
動画内で商品名を強調せずとも、「友達と語らうマック時間」が自然に印象づけられるため、ブランド体験そのものが広告メッセージに転化しているのです。
TikTok上では、「この雰囲気、リアルすぎてエモい」「学生の頃を思い出した」といった感情的コメントが多数寄せられ、エモーショナルマーケティングの好例とされています。
その他の注目事例
-
日本郵便:「手紙の記憶」シリーズ
送り手と受け手の関係性を丁寧に描いたショートドラマで、「郵便=人と人をつなぐ象徴」というブランド価値を再認識させた。 -
ユニリーバ:「#この世界にやさしさを」キャンペーン
社会課題や多様性をテーマにしたショートドラマで、企業理念と社会的共感を融合。広告を超えて“社会的メッセージ”として話題に。
成功企業に共通する3つのポイント
| 要素 | 内容 | 効果 |
|---|---|---|
| ストーリー性 | 人間ドラマ・感情の起伏を中心に構成 | 感情移入によるブランド共感 |
| 暗示的プロモーション | 商品やサービスを“背景”として扱う | 広告感を抑え自然な訴求 |
| 継続性 | シリーズ化・キャラクター展開 | 視聴者との関係性の深化 |
これらの企業に共通しているのは、**「売るための動画」ではなく「共感でブランドを伝える動画」**へと発想を転換している点です。
その結果、単発的な広告では得られない“記憶に残るブランド体験”を提供し、SNS上でのUGC(感想投稿・考察・切り抜き)によって二次拡散が自然発生しています。
4.効果の違い:ショートドラマがもたらす3つのマーケティング価値
同じ“短尺動画”でも、ショート動画とショートドラマでは、視聴者の心の動きやブランドへの影響プロセスがまったく異なります。前者が「認知の入口」を作るのに対し、後者は「記憶と共感」を形成する——つまり、目的と成果の“深さ”が違うのです。
効果①:記憶定着の深さ
| 比較軸 | ショート動画 | ショートドラマ |
|---|---|---|
| 記憶の種類 | 瞬間的記憶(ワーキングメモリ) | 感情記憶(エピソード記憶) |
| 継続時間 | 数秒〜数分 | 数日〜数週間 |
| 主な刺激要素 | 音・テンポ・ビジュアル | ストーリー・共感・余韻 |
ショート動画は、テンポ感・音楽・映像のインパクトによって“印象”を残します。
一方ショートドラマは、物語を通じて「登場人物の感情」と「自分の経験」とを重ね合わせることで、感情を伴う記憶=エピソード記憶として定着します。
たとえば「主人公が商品を使って前向きになる」「誰かを思い出して手紙を書く」といったシーンは、視聴者自身の経験とリンクしやすく、結果として“ブランドが人生の一部として記憶される”効果を生みます。
効果②:ブランド理解と世界観浸透
| 比較軸 | ショート動画 | ショートドラマ |
|---|---|---|
| 訴求軸 | 商品の特徴・使い方 | ブランドの理念・価値観 |
| 情報量 | 高密度(短時間で多情報) | 情緒的(体験として理解) |
| 視聴動機 | 面白い・すぐ役立つ | 共感できる・心に響く |
ショート動画は「何を伝えるか」に優れていますが、ショートドラマは「なぜそれを伝えるのか」を語ることができます。つまり、ブランドの“人格”や“哲学”を体験的に理解させることができるのです。
たとえば「自然と生きる」「人を想う」「小さな幸せを大切にする」といった価値観を、セリフや演出で表現することで、視聴者はブランドのメッセージを“感覚的に理解”します。
これにより、広告を見た瞬間の理解ではなく、「この企業らしい」という認識(ブランドパーソナリティ)が形成されます。
効果③:拡散力と共創性
| 比較軸 | ショート動画 | ショートドラマ |
|---|---|---|
| 拡散の起点 | トレンド・音楽・チャレンジ企画 | 感情共鳴・考察・ストーリー解釈 |
| 拡散の形態 | ハッシュタグ・リミックス投稿 | コメント・考察投稿・二次創作 |
| 二次波及 | 短期的(数日) | 長期的(シリーズ化・議論化) |
ショート動画の拡散はスピーディですが一過性で終わりやすいのに対し、ショートドラマは「語りたくなる物語」として自然拡散が続きます。
視聴者はコメント欄で“続編予想”や“キャラクター分析”を行い、SNS上で議論が生まれます。
その結果、UGC(ユーザー生成コンテンツ)やファンコミュニティが形成され、企業発信を超えた“共創型のブランドストーリー”が育っていくのです。
効果③:効果まとめ:一瞬のバズから、持続するブランド体験へ
| 観点 | ショート動画 | ショートドラマ |
|---|---|---|
| 視聴動機 | 面白い・役立つ | 感じたい・共感したい |
| ブランド接触 | 一時的 | 関係的 |
| KPI | 再生回数・CTR | ブランド好感度・検索増加・共感コメント率 |
| 効果の質 | 拡散型(広がる) | 浸透型(深まる) |
ショート動画が“バズ”を生む施策だとすれば、ショートドラマは“ブランドを好きになる理由”を育てる施策です。消費者の行動心理は、「知る → 興味 → 感情移入 → 共感 → ファン化」という流れで進行しますが、ショートドラマはこの中の「感情移入〜共感」に強く作用します。
つまり、広告としてのKPIだけでなく、ブランドの“持続的な好意形成”を数値化できる領域へ導くのがショートドラマの真価といえるでしょう。
ショートドラマは“ブランドの第二の声”
ショート動画が「伝えるための声」だとすれば、ショートドラマは「感じさせるための声」。
感情を動かす物語体験こそが、ブランドの印象を強く・長く残す力を持っています。
5.企業がショートドラマを制作する際の設計指針
 ショートドラマをマーケティングに活用する際、重要なのは「映像制作」ではなく「戦略設計」です。
ショートドラマをマーケティングに活用する際、重要なのは「映像制作」ではなく「戦略設計」です。
ストーリーを感動的に仕上げても、目的と一貫性を欠くとブランド価値を正しく伝えられません。
ここでは、企業がショートドラマを効果的に活用するための5つのステップを解説します。
ステップ1:目的設計 ― 何を“感じて”もらうのかを明確にする
まず最初にすべきは、「何を伝えたいか」ではなく、「視聴者にどう感じてもらいたいか」を定義することです。
| 目的のタイプ | 内容 | 成果指標(例) |
|---|---|---|
| 認知型 | 新商品・新サービスの存在を知ってもらう | 再生数、検索数増加 |
| 共感型 | ブランド理念・企業姿勢への共感を醸成 | ブランドリフト、好感度上昇 |
| 採用・共創型 | “働く姿”や“価値観”に共感してもらう | エントリー数、SNS反応率 |
ショートドラマは「ブランド体験の物語化」です。
たとえば、製品の“便利さ”を伝えるのではなく、その製品が“誰かの気持ちを救う”ストーリーにする。
感情を目的に置くことで、広告ではなく「ブランド体験の物語」として記憶されるようになります。
ステップ2:ストーリーテリング設計 ― 起承転結の中に“ブランドの意味”を埋め込む
3分以内の映像であっても、ストーリーには「起承転結」や「葛藤→解決→余韻」の構造が必要です。
視聴者が心を動かされるのは、“完璧な世界”ではなく、“葛藤と変化”が描かれた瞬間だからです。
たとえば、
-
「挫折した主人公が、ある出会いを通じて前に進む」
-
「日常の中で見落としていた優しさに気づく」
-
「誰かの行動が静かに世界を変えていく」
この“心の変化”の中に、ブランドの存在が自然に寄り添う形を設計します。
商品を登場させるのではなく、**ブランドの価値を象徴する「出来事」や「選択」**として表現するのがポイントです。
ステップ3:キャスティングと世界観の一貫性
ブランドの世界観を“人”で表現するのがショートドラマの強みです。
ターゲット層が感情移入できるキャラクターを設定し、その人物を通してブランドのメッセージを語ります。
たとえば、
-
若者向けブランドなら「迷いながらも前進する20代の主人公」
-
ファミリーブランドなら「家族の温かさを支える親の視点」
-
BtoBブランドなら「誠実に仕事に向き合う社員の姿」
配役だけでなく、演出トーン(照明・色味・音楽)を統一することで、ブランドの印象が視覚的にも定着します。
シリーズ展開を想定する場合は、キャラクターや空間を固定し、「この世界観=この企業」という関連づけを作ると効果的です。
ステップ4:メディア戦略 ― プラットフォームごとの文法を理解する
ショートドラマは1本作って終わりではなく、SNSでの循環設計が鍵です。
| プラットフォーム | 特徴 | 配信ポイント |
|---|---|---|
| YouTube Shorts | ストーリー重視・視聴完了率が高い | 本編+シリーズ再生リストで滞在時間を確保 |
| TikTok | 拡散力が高い・UGC化しやすい | 感情のピーク部分を切り抜き投稿 |
| Instagram Reels | ブランドイメージとの親和性が高い | ビジュアル重視で世界観訴求 |
| X(旧Twitter) | 会話・考察・引用が生まれやすい | 感想ポストを誘発するコピー設計 |
特に効果的なのが、「本編」と「ショートカット版(15〜30秒)」の二段階構成。
本編で感情を動かし、短尺版でトレンド的に広めることで、認知と共感の両立が図れます。
ステップ5:効果測定とPDCA ― “感情の反応”を数値化する
ショートドラマは再生数だけでは測れません。
「感情を動かしたか」を評価するために、以下の指標を組み合わせて測定します。
| 評価軸 | 指標 | 測定方法 |
|---|---|---|
| 関心 | 平均視聴時間、完了率 | YouTube Studio / TikTok Analytics |
| 共感 | コメント内容のポジティブ率 | テキスト感情分析ツール |
| 検索行動 | ブランド名・商品名の検索増加 | Googleトレンド / Search Console |
| 記憶・好感度 | ブランドリフト調査 | YouTube広告 / 外部リサーチ会社 |
これらを定点的に追い、「どの感情がブランド理解につながったか」を把握することで、次の作品に活かすことができます。
特にシリーズ展開では、回ごとに感情トーン(共感・感動・ユーモア)の効果を比較することで、ブランドの“最適な語り口”が見えてきます。
ショートドラマは、単に映像を作る施策ではなく、企業が「どんな想いで社会と関わりたいか」を可視化するプロジェクトです。
目的設定から脚本構成、SNS展開、効果測定までを一貫して設計することで、初めてブランドの人格=ストーリーブランディングが完成します。
💡補足:BtoB企業が活用する場合
BtoB領域でもショートドラマは効果的です。
たとえば、
-
採用ブランディング:社員のリアルな1日をドラマ化し、共感を醸成
-
企業理念の共有:創業ストーリーを感情的に描き、企業の信頼性を高める
-
パートナーシップ強化:取引先との協働を物語として表現し、価値共創を訴求
実際、BtoB動画の視聴者は理屈よりも“人間らしさ”に心を動かされるため、**「理念を伝える手段」**としてショートドラマが有効に機能します。
6.今後の展望:AI×ショートドラマ、共創の時代へ

ショートドラマの進化は、単なる映像表現の発展にとどまりません。
近年は、AI技術やデジタルプラットフォームの進化によって、企業と視聴者が共にストーリーを作る時代が到来しています。
ここでは、今後のショートドラマ活用を左右する3つのキーワード「AI生成」「インタラクティブ体験」「共創型ブランド」を軸に展望を整理します。
1. AI生成による“物語制作の民主化”
生成AIの進化により、脚本・キャスティング・映像生成のすべてが手軽に行える時代になりました。
特に注目されているのが、AIによるストーリープロトタイピング。
企業のブランドメッセージやキーワードを入力するだけで、AIが複数の脚本案を生成し、短期間で方向性を検証できます。
たとえば、
-
ブランドトーンに沿った台詞やナレーションをAIが自動生成
-
映像生成AIによる「仮想ロケ撮影」や「俳優なしのドラマ制作」
-
AI感情分析による脚本段階での共感度シミュレーション
これにより、かつては制作コストや工期の問題で実現できなかった「シリーズ展開」や「A/Bテスト型の物語制作」も可能になりつつあります。
AIは“人間の感性を代替する”のではなく、“創造を加速させる補助輪”として、ショートドラマ制作の民主化を後押ししています。
2. 視聴者参加型ドラマによる“体験の拡張”
次に注目されているのが、インタラクティブ型ショートドラマ。
視聴者が選択肢を選ぶことでストーリーが分岐したり、コメントやリアクションが物語展開に影響したりする仕組みが拡がりつつあります。
SNSではすでに、「視聴者のコメントをもとに続編を作る」「投票で主人公の行動が決まる」など、ユーザー参加型の制作が増加。
これにより、視聴者は単なる“受け手”ではなく、“共作者”として物語に関与する体験を得るようになっています。
マーケティング的に見れば、この形式は非常に強力です。
自分が関わったストーリーには強い帰属意識が生まれ、ブランドへのエンゲージメントが飛躍的に高まるからです。
特にZ世代を中心に、「体験に参加できるブランド」に好感を抱く傾向が強く、企業のコンテンツ戦略においても欠かせない潮流となっています。
3. 共創型ブランドストーリーの時代へ
AIやSNSが普及した今、企業が一方的に語るブランドストーリーはもはや通用しません。
これからの時代は、ユーザーが自らブランドの物語を“編集・再解釈”することが前提になります。
ショートドラマのコメント欄で交わされる感想、X(旧Twitter)上での考察投稿、TikTokでの切り抜き・二次創作——それらはすべて、ブランドを「共に作る」行為です。
企業がこの動きを受け入れ、**“物語を開放する姿勢”**を持つことで、ユーザーはそのブランドに“共感を超えた参加感”を覚えます。
たとえば、ドラマの続編を一般公募したり、ユーザー投稿から次のストーリーを生み出すなど、ブランドとファンが共に世界観を育てる構造が成立します。
この「共創型ストーリーブランディング」は、広告を“企業の発信”から“社会との対話”へと進化させる新しいフェーズです。
未来のショートドラママーケティング像
| 時代 | 特徴 | 企業の役割 |
|---|---|---|
| 〜2020年代前半 | 一方向的な広告映像 | ブランドがメッセージを発信 |
| 2025年以降 | 共感・参加型の物語体験 | ブランドが“場”を設計し、視聴者と共に創る |
| 今後 | AIが補完する共創エコシステム | 人とAIが協働し、ブランドストーリーを継続生成 |
AIと人間、企業とユーザーの垣根が溶け合うなかで、“ブランドが語る物語”から“みんなで語る物語”へと移行していくのが、これからのショートドラマの本質です。
物語は「語られるもの」から「共に生きるもの」へ
ショートドラマは再生数だけでは測れません。
「感情を動かしたか」を評価するために、以下の指標を組み合わせて測定します。
ショートドラマは、これまでの広告表現を超え、企業の“文化的発信”へと進化しています。
生成AIが企画を支え、SNSが共感を拡げ、ユーザーが物語を継いでいく——そんな時代において、ブランドの価値は「どんな物語を生み出すか」よりも、「どんな共感を生み続けられるか」にかかっています。
ショートドラマは、その中心に立つ最も人間的で、最も感情的なメディアなのです。
7.ショートドラマは、ブランドが心を伝える新しい言語である

ショート動画が「知ってもらうための広告」だとすれば、ショートドラマは「感じてもらうための物語」です。
消費者が“情報”ではなく“共感”を基準にブランドを選ぶ今、企業が発信すべきは商品スペックではなく、「なぜこの想いを届けたいのか」という情緒的な理由です。
ショートドラマは、その想いをわずか数分で伝え、心の中に残すことができる新しいマーケティング手法です。
そこには、従来の広告のような押しつけがましさはなく、観る人の記憶の中に静かに根を下ろす力があります。
さらに、AIやSNSの進化によって、ブランドが一方的に語る時代は終わり、ユーザーと共に物語を紡ぐ時代が始まりました。
企業の語りが“共感”を生み、その共感が“共創”へと広がっていく。
この循環こそが、これからのブランドが持続的に選ばれる理由となります。
💡 最後に:企業が今すぐできる第一歩
-
自社の理念や想いを「1本の物語」にしてみる
-
ショート動画の延長ではなく、「人の心が動く瞬間」を脚本化する
-
SNS上で共感を呼ぶテーマ(挑戦・絆・希望・誠実さなど)を見つける
たった1分の物語が、ブランドを大きく変えるきっかけになるかもしれません。
広告の先にある“体験”としてのマーケティング——それが、ショートドラマの本質です。
動画マーケティングの戦略設計、ご相談ください
自社ブランドのショートドラマ活用を検討している方、SNS動画戦略を見直したい方は、ぜひお気軽にご相談ください。
ストーリー設計から配信戦略、効果測定まで、御社に合った最適な動画マーケティング戦略をご提案いたします。