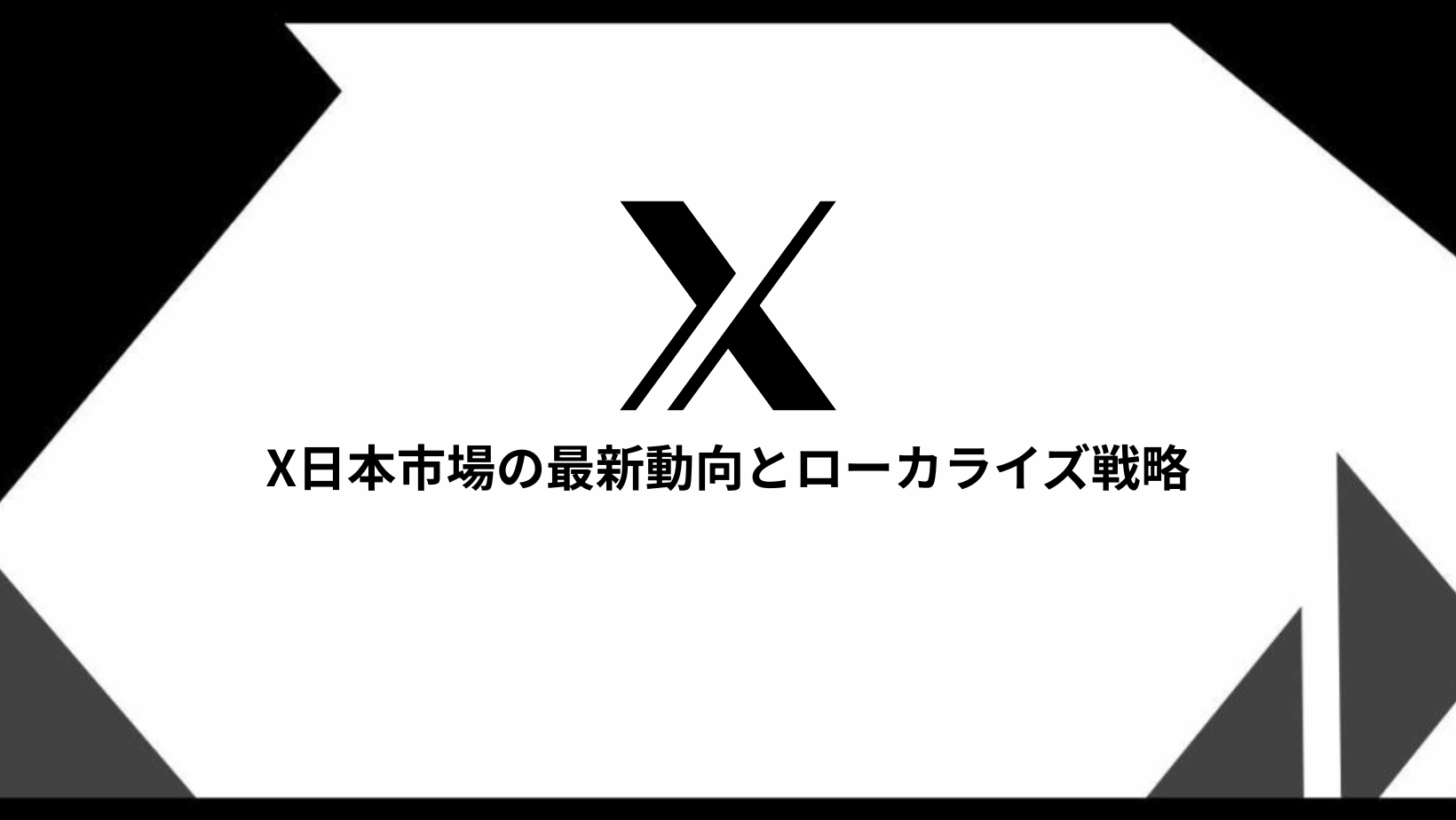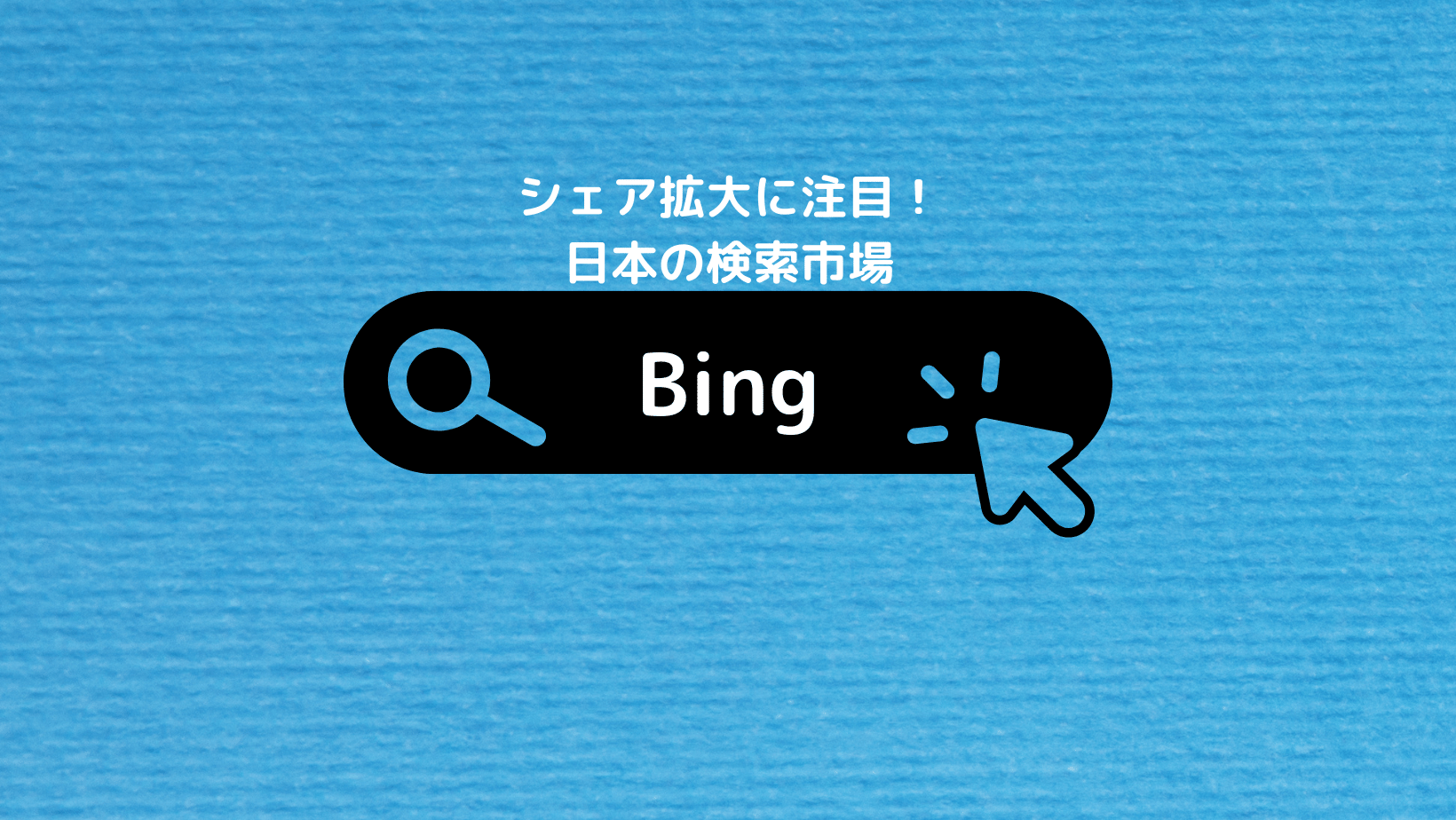日本のEC市場はどこまで伸びる?令和6年度調査に見るBtoC-ECの最新トレンド
消費スタイルが変わる中、ECは“生活の一部”へ
スマートフォンひとつで食品や日用品を注文し、週末の旅行もアプリで予約する。
そんな「オンライン購買行動」が、もはや特別ではなく“日常”になりました。
今の消費者は、「便利だからECを使う」ではなく「当たり前にECを使う」時代に生きています。
店舗での購買とECの境界はどんどん曖昧になり、生活に自然に溶け込むように“デジタル購買”が進化しています。
こうした変化を裏づけるように、日本のEC市場は令和6年度も拡大を続けています。
経済産業省が公表した最新の「電子商取引に関する市場調査」によると、BtoC-EC市場規模は前年比6.3%増の約25兆円、EC化率は9.3%(+0.35ポイント)と過去最高を更新しました。
 (図表4-7:BtoC-EC市場規模の経年推移/出典:経済産業省「令和6年度 電子商取引に関する市場調査」p.33)
(図表4-7:BtoC-EC市場規模の経年推移/出典:経済産業省「令和6年度 電子商取引に関する市場調査」p.33)
EC市場の拡大は、単なる取引のデジタル化ではなく、消費者のライフスタイルそのものが変化していることの表れです。特に食品・日用品・家電などの「生活密着カテゴリー」がEC化をけん引しており、企業にとってECはもはや「補完チャネル」ではなく「主要販路」の一つとして位置づけられています。
この記事では、令和6年度の調査結果をもとに、BtoC-EC市場の最新動向、消費者の購買行動の変化、そして企業が取るべき今後の販促戦略について解説していきます。
出典:経済産業省「令和6年度 電子商取引に関する市場調査」(2025年8月公表)
- BtoC-EC市場の最新トレンドと分野別動向
- 消費者の購買行動の変化とCX重視の流れ
- SNS・生成AIが変える販促構造
- リアルとWebが融合する購買行動(OMO/O2O)
- evoliaが考える今後のマーケティング戦略
- まとめ:BtoC-ECは「深化の時代」へ
1.BtoC-EC市場の最新トレンドと分野別動向
経済産業省の調査では、BtoC市場は「物販系」「サービス系」「デジタル系」の3つの分野に分類されています。それぞれの特徴を見ていきましょう。
■ 物販系:生活関連分野の拡大が続く

(図表4-17:物販系分野 商品別BtoC-EC市場規模およびEC化率/出典:同調査 p.49)
令和5年の物販系市場は約16.9兆円(前年比6.2%増)に達しました。
中でも、食品・飲料・日用品といった生活関連分野が前年に続き拡大しており、物販系全体の成長を支えています。ネットスーパーや定期宅配など、日常購買のオンライン化が進んだことで、生活者の購買行動は「ECが主軸」へと変化しています。
■ サービス系:旅行・チケット販売が回復基調に
観光・エンタメ分野のオンライン予約・販売が回復を続けています。宿泊やチケット販売では、OMO(Online Merges with Offline)型の購買行動が定着し、リアル体験の予約・購入がオンラインで完結する流れが広がっています。
■ デジタル系:サブスク化で安定成長
音楽・映像配信、電子書籍などのデジタルコンテンツ市場は、成熟期を迎えつつも安定した成長を維持しています。特にサブスクリプションモデルが一般化し、ユーザーは「所有」よりも「利用体験」を重視する傾向が定着しました。この構造は、BtoC-EC全体に共通する“体験重視型消費”の象徴といえます。

(図表4-6:サービス系・デジタル系分野のBtoC-EC市場規模の経年推移/出典:同調査 p.32)
2.消費者の購買行動の変化とCX重視の流れ

令和6年度の調査では、消費者の購買行動の主軸がスマートフォンへ完全に移行していることが示されました。
アプリやモバイルサイトの使いやすさ、決済のスムーズさ、プッシュ通知などのUXが購買を左右する時代に入っています。
またSNSの利用率は依然として高く、購買情報の取得から購入決定までSNSが重要な接点になっています。
特にInstagramやTikTokなどのビジュアルSNSでは、インフルエンサーの投稿が購買意欲を刺激し、
「発見から購買へ」の流れが自然に組み込まれています。
こうした動きは、価格よりも“体験価値”を重視する消費行動の広がりを裏付けています。
3.SNS・生成AIが変える販促構造
企業側でも生成AIによる商品説明文・広告コピー・レコメンドの自動生成が拡大しています。
これにより、少人数でも高品質なECサイト運営が可能になり、パーソナライズドな販促が実現しています。
SNSは今や「情報発信の場」から「購買を完結させる場」へと進化しています。
経産省の調査によれば、LINE・Instagram・TikTok・X(旧Twitter)といったSNSの利用率は依然として高く、
特に20〜40代ではSNSが商品認知から購入までの主要経路として機能しています。
SNSが変えた“発見から購入”のプロセス
従来、消費者は検索エンジンを使って「欲しいものを探す」購買行動が主流でした。
しかし現在では、SNS上で流れてくる動画や投稿から**「知らなかった商品を見つけ、即購入する」**という行動が一般化しています。
この流れは「ディスカバリーコマース(発見型購買)」と呼ばれ、特にTikTok Shopの登場以降、そのスピードが加速しました。
たとえば、短尺動画内で“使い方”や“ビフォーアフター”を示すコンテンツは、
広告というより「体験の共有」として受け止められ、消費者の購買意欲を直接刺激します。
SNSがメディアから販売チャネルへと変貌した象徴的な事例です。
生成AIがもたらす販促の効率化と精度向上
企業側では、生成AIの導入がSNS販促の構造を根底から変えつつあります。
AIによる商品説明文・広告コピー・レコメンド文章の自動生成が普及し、
人手では難しかった高速PDCA運用が可能になりました。
さらに、AIは単なる文章生成にとどまらず、ユーザーの属性や過去の閲覧履歴を学習し、パーソナライズされた販促メッセージを最適タイミングで配信できます。
たとえばECサイト上のレコメンドだけでなく、Instagram広告やLINE通知に自動連携して“個別最適なクリエイティブ”を生成するケースも増えています。
SNS×AIがつくる「感情と効率の両立」
SNSは“共感”を生み、AIは“最適化”を担う。
この2つの融合により、企業は「感情に訴える販促」と「効率的な顧客接点管理」を同時に実現できるようになりました。
特に、生成AIを活用してコメント分析やトレンド検知を行い、
ユーザーのリアルタイムな声を販促戦略に即反映する事例も増えています。
このように、AIは単に作業を自動化するだけでなく、SNSマーケティングを“動的に運用する”ための頭脳として機能し始めています。
4.リアルとWebが融合する購買行動(OMO/O2O)
近年の日本の小売業では、「リアルとデジタルのどちらが主軸か」ではなく、「両者をどう融合させるか」 が重要なテーマになっています。
経済産業省の調査でも、2023年以降のBtoC市場では実店舗とECをシームレスに統合する取り組み(OMO)が一般化しており、
店舗運営の効率化や販路拡大を超えて、「顧客体験価値(CX)の拡張」という目的が明確になっています。
実店舗は“体験装置”へと進化
調査では、コロナ禍を経て実店舗の位置付けが再定義されたことが強調されています。
かつての店舗は「商品を販売する場」でしたが、現在では“ブランドを体験する場”としての役割が増大。
購買前の比較検討、スタッフとの対話、商品の質感確認など、オンラインでは得られないリアル体験が
最終的な購買決定を後押しするようになっています。
その一方で、店舗で商品を体験した後にECで購入する「ショールーミング」も一般化しました。
このように、実店舗がECとの関係性を失うどころか、相互に補完し合う購買行動フローが定着しています。
オンライン接客の普及と信頼の可視化
オンライン接客やチャットサポートの導入も注目されています。
消費者がリアル店舗に足を運ばなくても、スタッフがビデオ通話やチャットで
商品の説明やサイズ相談に応じる「デジタル接客」が広がっており、
これは**“人による信頼”をオンライン上で再現する試み**ともいえます。
この仕組みが成功している企業ほど、顧客満足度の向上や返品率の低下といった成果を得ています。
リアル接客の良さをオンラインで再現できたことが、OMOの成熟を象徴しています。
BOPISの浸透とラストワンマイルの効率化
さらに、「BOPIS(Buy Online, Pick-up In Store)」の普及も見逃せません。
これはECで購入した商品を実店舗で受け取る仕組みで、配送コスト削減・在庫回転率の向上・店舗来店促進など、企業・消費者双方にメリットをもたらす施策として評価されています。
BOPISの利用者は受け取りのついでに店内で別の商品を購入する傾向もあり、
オンラインとオフラインの境界が自然に溶け合う購買体験が形成されています。
このようなOMO時代では、企業は「販売経路を増やす」のではなく、「チャネルを一つの顧客体験として統合する設計力」 が問われます。
リアル店舗のスタッフ教育、ECサイトのUX改善、在庫データの統合など、部門を超えた連携が企業価値を左右します。
つまり、OMOとは単なるマーケティング戦略ではなく、企業文化や組織構造の変革を伴う“経営戦略”なのです。
5.evoliaが考える今後のマーケティング戦略
デジタル広告の飽和と消費者の情報接触環境の多様化により、「どこに出稿するか」よりも「誰の行動に寄り添うか」が重要になっています。
evoliaでは、この環境変化を“再びローカルが力を持つ時代”の到来と捉えています。
商圏分析×行動データ ― 地域ごとの“人の動き”を科学する。
「どこで、どんな人が、どう動いているか」という空間的な理解です。
evoliaが提供するエリアマーケティングソリューションでは、GISデータ・位置情報データ・購買行動データを統合し、エリア単位で生活者のリアルな動きを可視化します。
これにより、「来店しやすいエリア」「Web経由での購買比率が高いエリア」を特定し、
チラシ配布・Web広告・イベント開催の最適配分が可能になります。
つまり、勘や経験ではなく、データドリブンで販促エリアを設計する時代へと進化しているのです。
6.まとめ:BtoC-ECは「深化の時代」へ
令和6年度の調査から見える日本のBtoC-EC市場は、
-
市場の拡大とEC化率の上昇
-
スマートフォン・SNSを中心とした購買体験の変化
-
SNS・AI・OMOによる販促構造の進化
という3つの方向で深化しています。
今後のEC戦略では、単に「売る場」を整えるのではなく、「ブランド体験をどう設計するか」が問われます。
オンライン購買行動とリアル行動データの統合こそが、これからの成長を左右する鍵です。
BtoC-ECは今、拡大の先にある“深化のフェーズ”へ。
生活者に寄り添う購買体験をどうつくるか——それが、これからのEC市場で勝ち抜くための最も重要な視点といえるでしょう。
EC市場の成長スピードに合わせて、今こそ販促戦略の見直しが求められています。
evoliaでは、商圏データや購買行動データを活用し、店舗集客・EC販促を両立させる最適なマーケティング戦略をご提案しています。
貴社の課題に合わせた無料相談も実施中です。お気軽にお問い合わせください。