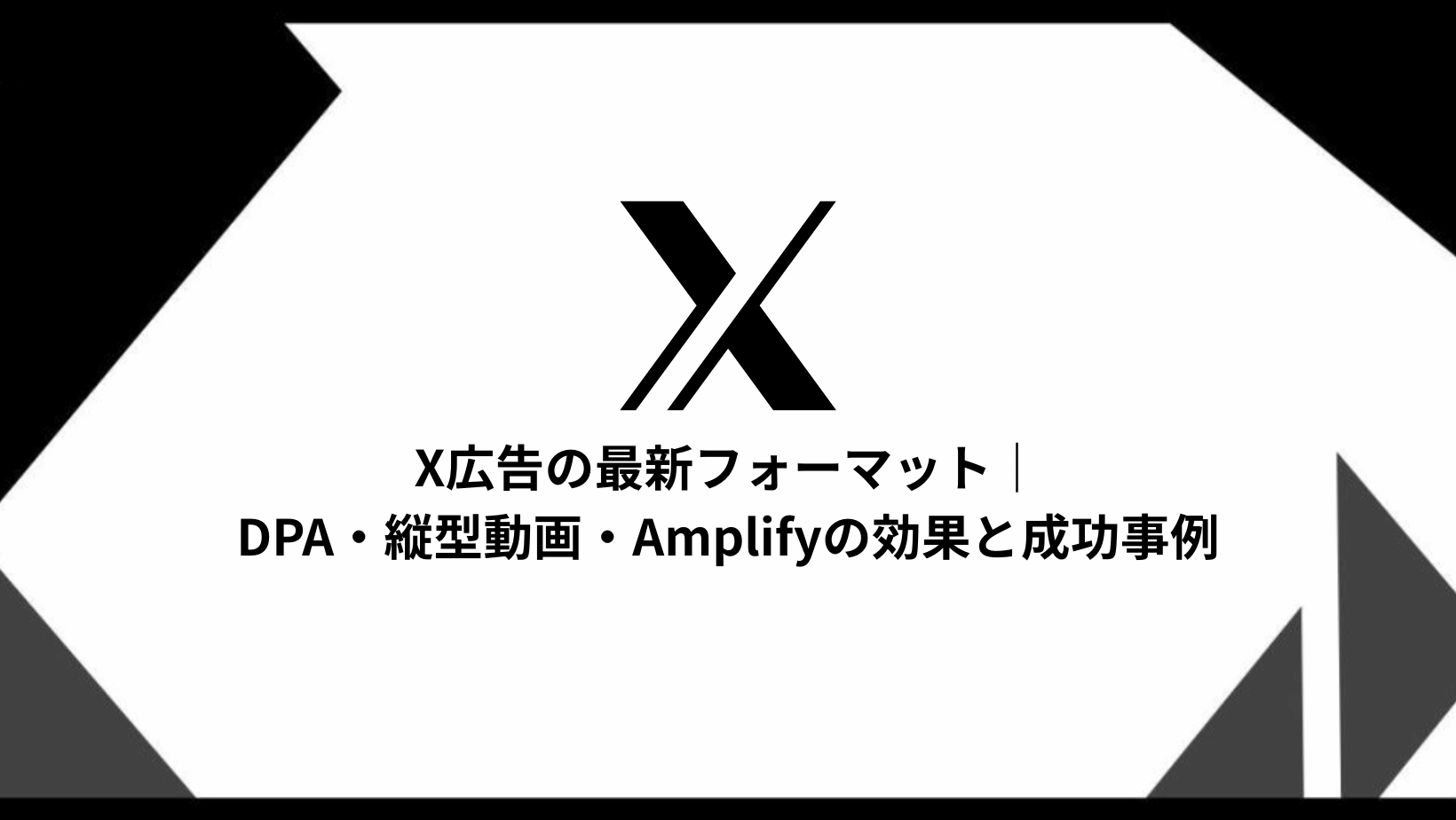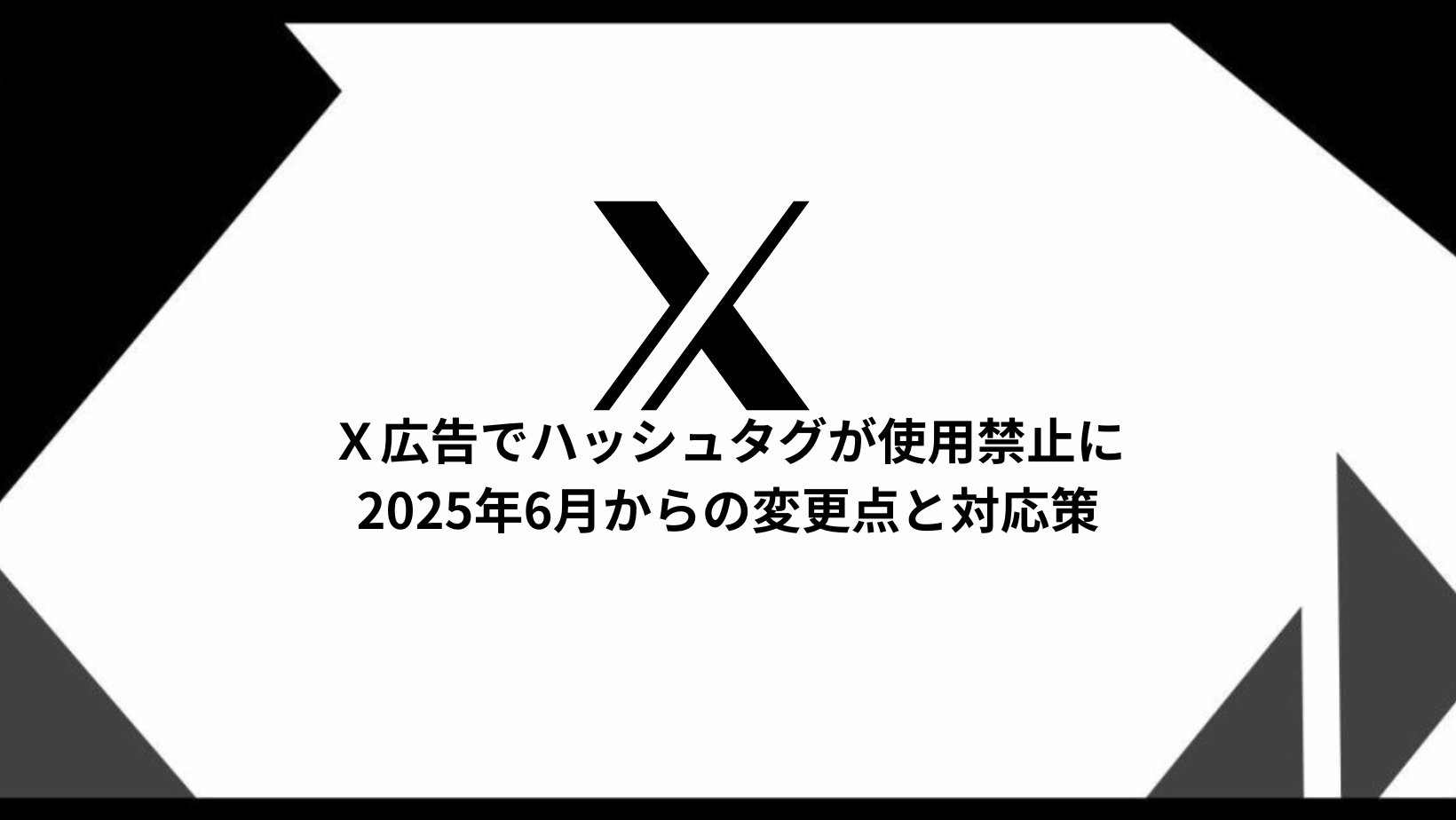X日本市場の最新動向とローカライズ戦略
SNS広告が飽和する中で、近年あらためて注目を集めているのが X(旧Twitter) です。
かつて「リアルタイムのつぶやき空間」として知られていたXは、いまやニュースやトレンド、エンタメ、日常の出来事まで、“社会の温度”を感じ取る場所として利用されています。
他のSNSが「つながり」や「自己表現」を主軸とするのに対し、Xは**「意見を交わす」「共感で広がる」**という独自の文化を持っています。
そのため、広告やブランド発信においても、ユーザーの“本音”が現れるこの場を活用することの価値が再評価され始めています。
特に日本では、Xの利用率が世界トップクラス。投稿量の多さや会話の熱量は他国を大きく上回っており、
企業にとっても“ユーザーとの距離が最も近いSNS”といえる存在です。
本記事では、日本のXユーザーの特徴と最新動向、そしてXが進める日本向けのローカライズ施策をもとに、
企業がいま取るべき「文化に寄り添う広告戦略」を探っていきます。
- 日本におけるXのユーザー動向 ― 圧倒的な利用規模と接触時間
- 「動画視聴×会話」が主軸に ― 滞在時間の55%が動画視聴
- 日本向けローカライズ施策 ― 「From Japan」が示す文化への敬意
- 信頼を築く「コミュニティノート」の進化
- 日本ブランドが取るべきX運用戦略 ― 共感が拡散を生む
- まとめ:文化を理解する広告が、信頼と成果を生む
1.日本におけるXのユーザー動向 ― 圧倒的な利用規模と接触時間
Xの日本国内での利用規模は、もはや“日常インフラ”といえるレベルに達しています。
最新データによると、月間アクティブユーザー(MAU)は6,700万人、日間アクティブユーザー(DAU)は4,000万人。
これは日本のSNS利用者全体の中でも突出した数値であり、ほぼ2人に1人がXを利用している計算になります。
また、デジタル媒体の接触時間においても、XとYouTubeが“トップ2”。
つまり日本のユーザーにとって、動画視聴と情報収集・会話の双方を行う主要なプラットフォームがこの2つなのです。
さらに注目すべきは、利用時間の伸び率。2025年時点でのデータでは、1人あたりの滞在時間が前年比+14% と着実に増加しています。単にユーザー数が多いだけでなく、「1人が長くXを見続けている」ことが、他SNSとの差を生んでいます。
数字の裏にある“文化的接触”
Xの強みは、“日常と社会が交わる場所”であること。
ユーザーはニュースを見て、感想をつぶやき、他者の意見に反応し、
そのまま動画や広告に接触するという行動を自然に行っています。
この流れが、“広告が入り込んでも違和感のない環境”を作り出しています。
そのため、X広告を検討する企業にとって、
「どんなタイミングで、どんな文脈で広告が届くのか」を理解することが、
最初の成功ステップといえるでしょう。
2.「動画視聴×会話」が主軸に ― 滞在時間の55%が動画視聴
X上での滞在時間をさらに分析すると、
なんと全体の55%が“動画視聴時間”**であることがわかっています。
これは単なるトレンドではなく、「情報を動画で理解し、会話で共有する」文化が根付いた証です。
動画視聴時間も前年比+14%と拡大しており、
「動画→コメント→拡散」という行動サイクルが日常化しています。
たとえばニュース動画やスポーツのハイライトを見て、
その感想をポストしたり引用リポストしたりする流れが典型例です。
企業にとっての意味
動画が“広告”としてだけでなく、“会話の中心”になっている点が重要です。
単に動画を流すだけではなく、**「その動画がどんな会話を生むか」**までを設計することが、
これからのSNS運用では求められます。
たとえば新商品の発表動画を出す場合でも、
「どんなリアクションを誘発したいのか」「ユーザーが何を引用して広めるか」を意識することで、
広告は“話題”に変わります。
成功している企業の共通点
-
短尺+感情訴求がうまい:3〜5秒でブランドの空気感を伝える。
-
動画内でコメントを促す工夫がある:「あなたならどう思う?」と問いかける。
-
音を活かす:BGMや効果音が“感情のトリガー”として機能。
Xはもはや「動画広告の新しい主戦場」といっても過言ではありません。
他SNSよりも“会話の連鎖”が生まれやすい点を理解して設計することが、成功の鍵になります。
3.日本向けローカライズ施策 ― 「From Japan」が示す文化への敬意
1. 世界でも特異な“日本仕様”
X(旧Twitter)はグローバルプラットフォームでありながら、
日本市場に対して非常に独自性の高いローカライズを行っています。
その象徴的なプロジェクトが、**「From Japan」**と呼ばれる取り組みです。
このプロジェクトは、日本の文化・アニメ・季節行事といった
「生活に根付いたコンテンツ」を中心に、ユーザー体験を最適化するもの。
たとえば、人気アニメ『鬼滅の刃』と連動したポータル企画では、
作品世界に関連する投稿をまとめ、キャラクターごとに閲覧できる仕組みを展開しました。
単なる広告やコラボに留まらず、**“文化の一部としてのX”**を実現している点が特徴です。
2. 「漫画が読みやすくなる」アップデート
日本では特に漫画・アニメ文化の発信が活発で、
投稿画像やスクリーンショットで物語を共有するユーザーも多い傾向があります。
この行動特性に対応するため、Xは縦スクロールで漫画を快適に読める表示機能を導入。
クリエイターが作品を投稿しやすく、読者がシームレスに閲覧できるUIへと進化しています。
これにより、Xは「会話のSNS」から「文化を体験するSNS」へと変化。
特に若年層やファンダム層では、Xが“新しいコミックプラットフォーム”として認知されつつあります。
3. ローカル文脈を理解するブランドの姿勢
こうした施策の根底にあるのは、「文化的な共感を軸にしたエンゲージメント設計」です。
グローバル広告でも日本の祭り・四季・作品文化をテーマにした投稿が多く、
単なる翻訳ではなく“情緒的な翻案”を行うブランドが成果を上げています。
広告においても、日本の文脈を理解する=信頼される という構図が明確になりつつあります。
Xのローカライズ戦略は、まさに「文化のリズムに合わせて広告を届ける」という思想に基づいています。
4.信頼を築く「コミュニティノート」の進化
1. 誰もが情報の“伴奏者”になる仕組み
Xが進化するもう一つの軸が、「信頼の構築」です。
その中心にあるのが「コミュニティノート」。
これは、ユーザーが誤解を招く可能性のあるポストに対し、
背景情報や補足を加える仕組みで、健全な会話空間をユーザー自身が保つという考え方です。
2025年時点で、コミュニティノートへのコントリビューター(貢献者)は100万人を突破。
これは単なる機能ではなく、Xが“信頼の民主化”を進めている象徴でもあります。
2. ブランドにとっての安心材料
広告主にとっても、この仕組みは大きなメリットです。
ブランドが誤情報やセンシティブな投稿と隣り合うリスクを最小化できるため、
ブランドセーフティの基盤として機能しています。
特に、AI(Grok)による文脈理解と組み合わせることで、
「誤情報を回避しながら、信頼度の高いコンテンツに隣接して広告を出す」ことが可能になっています。
これは、長期的に“ブランドイメージを損なわない広告運用”を実現する上で極めて重要です。
3. 「共に育てるプラットフォーム」へ
Xの強みは、ユーザーが単なる閲覧者ではなく、
情報空間を“共に作る存在” であること。
コミュニティノートによって、ユーザー・メディア・ブランドが
同じ基盤の中で“信頼を積み上げる構造”が形成されています。
企業がこの姿勢を理解し、自社の発信にも透明性や背景説明を加えることで、
X内での発言がより信頼されるようになります。
これが、これからの時代における「ブランドの会話力」といえるでしょう。
5.日本ブランドが取るべきX運用戦略 ― 共感が拡散を生む
1. 「会話を設計する」という発想
Xでは、単に広告を配信するだけでは成果が出にくい時代に入りました。
ユーザーがどんな会話をしているのかを理解し、その流れの中に“自然に入り込む”ことが求められます。
特に日本のユーザーは「共感」や「気づき」をきっかけに行動する傾向が強く、
投稿を見て“自分の意見を添えて拡散する”という文化が根付いています。
つまり、広告やブランド発信も「一方通行」ではなく、“引用されやすい文脈”を持つ発信が重要なのです。
2. 実践ポイント:3つの共感設計
-
共感型投稿を作る
具体的なストーリーや人の気持ちを表現する。
(例:「こんなとき、あなたならどうする?」という問いかけ形式) -
動画×コメントの組み合わせ
動画を投稿したあとに、コメント欄で質問や裏話を展開する。
企業アカウントでも“人間らしさ”を出すのが鍵。 -
季節性・社会トピックとの連動
桜や花火、行事など、X内で自然に話題化するテーマを選ぶ。
これらを意識することで、“広告が話題になる” 状態を生み出せます。
6.まとめ:文化を理解する広告が、信頼と成果を生む

Xは今、日本で「文化を映す鏡」のような存在になりつつあります。
ユーザーは単に情報を得るだけでなく、そこに“共感”や“会話”を求めています。
その中で、ブランドがどんな発信をするか——
それは、商品の良さよりも 「どんな気持ちを届けたいか」 が問われる時代です。
AIが広告の最適化を進めるほど、
“人が文化を理解して発信する” ことの価値は高まっています。
DPAや動画広告のような機能的フォーマットの裏側には、
「誰に・どんな空気で・どう伝えるか」という文化的文脈が存在します。
evoliaは、こうした文脈を大切にしながら、
AI×人のハイブリッド運用でブランド価値を高める支援を行っています。
数字に強く、感情にも寄り添う広告。
その両立こそ、これからの日本市場で信頼を築く最も確かな道筋です。
X広告の戦略設計、ご相談ください
X広告は、単なるSNS広告を超え、いまやブランドの世界観を伝えるプラットフォームへと進化しています。
GrokをはじめとするAI技術の実装により、「誰に」「どんな文脈で」「どんな表現で」届けるか——
その精度とスピードは、これまでの広告とは比べものになりません。
当社では、こうしたXの最新機能やAI解析を活用し、
店舗集客・EC売上向上・ブランド認知拡大を目的とした広告設計・運用支援を行っています。
「Xを使って自社の認知を広げたい」「キャンペーンを話題化させたい」
「AIを取り入れた運用に興味がある」——
そんな企業様は、ぜひ一度ご相談ください。