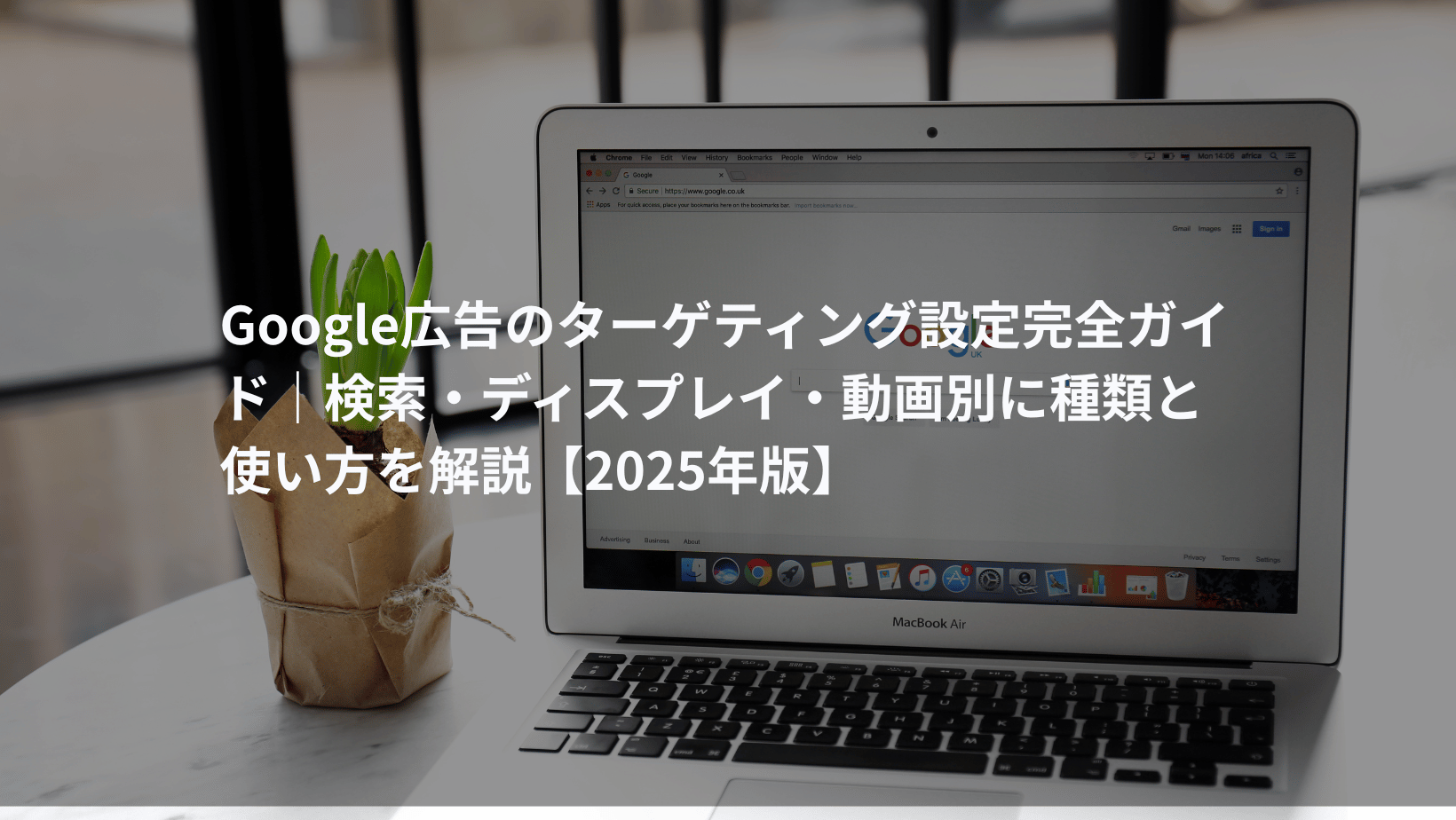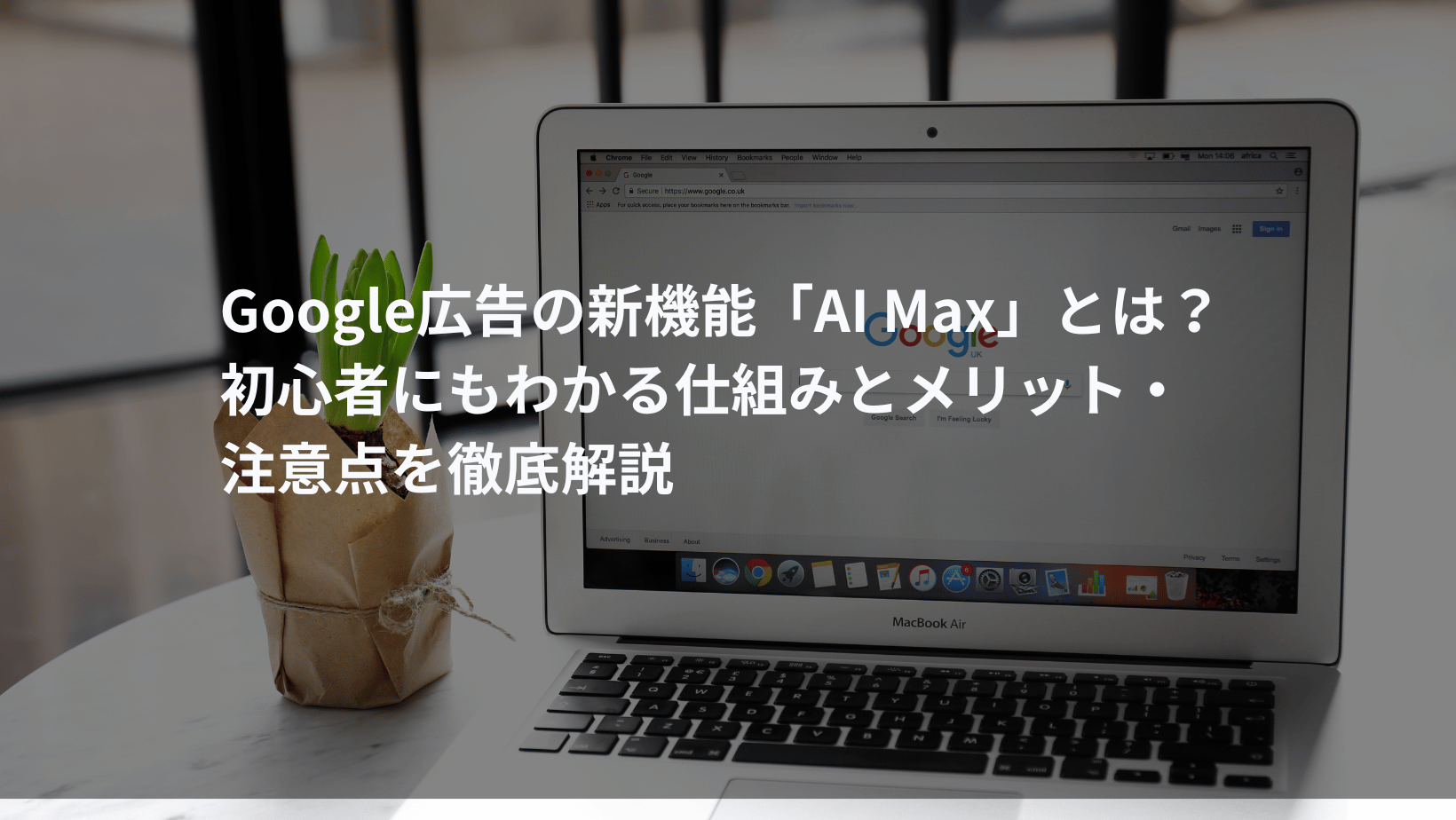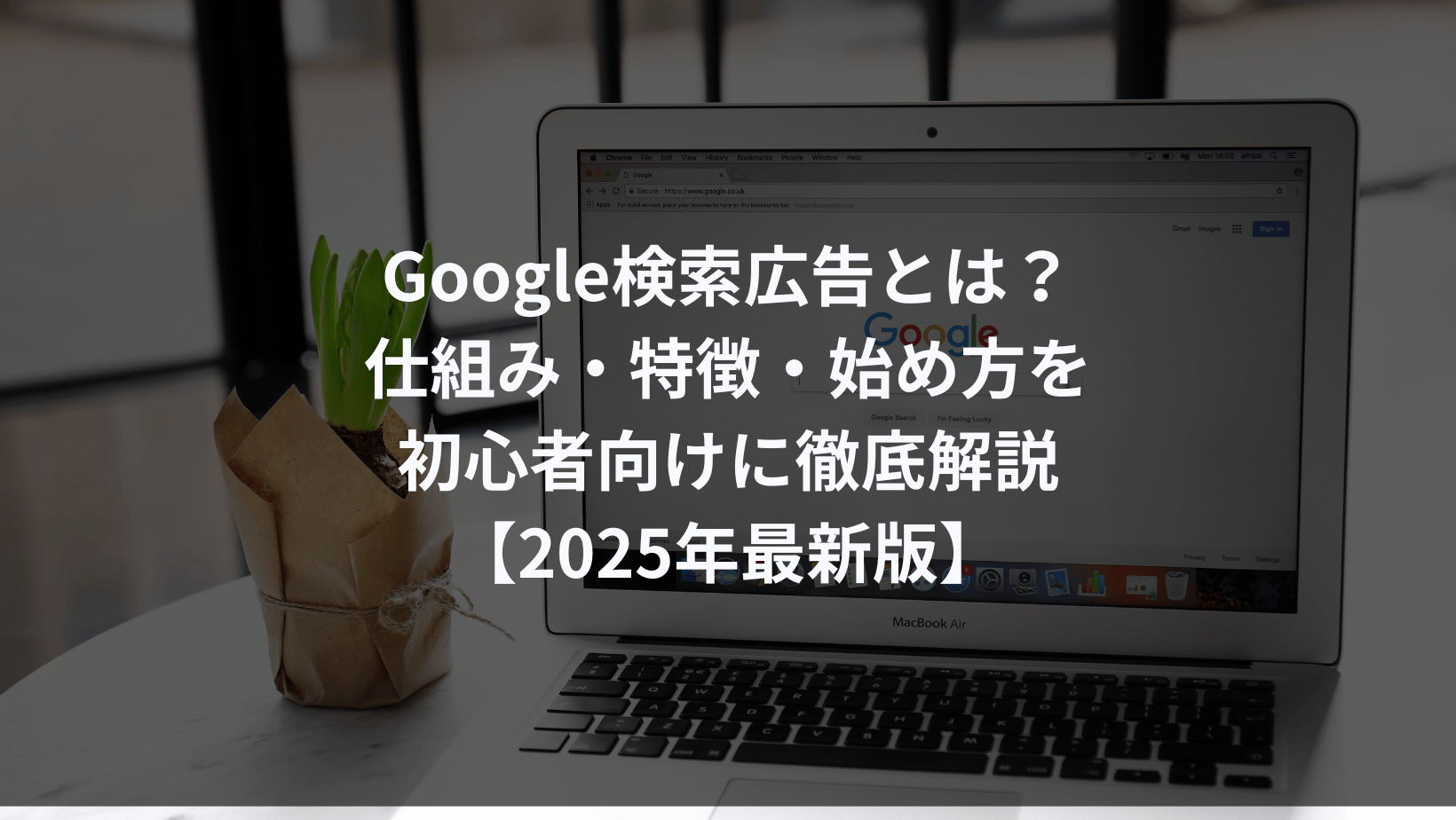【2025年最新版】Googleディスプレイ広告とは?仕組み・ターゲティング・成功のポイントを初心者向けに解説
Google広告には、検索広告・ディスプレイ広告・動画広告・ショッピング広告・アプリ広告・スマートキャンペーン・P-MAX・デマンドジェネレーションなど、さまざまなキャンペーンタイプが存在します。それぞれ目的や特性が異なるため、初心者の方にとっては「どれが自社に適しているのか」「何から始めるべきなのか」が分かりづらいのが現状です。
中でもディスプレイ広告は、検索行動をしていない潜在層にアプローチできる数少ない広告手段です。視覚的な訴求力を活かしてブランド認知を高めるほか、リマーケティングなどで再訪やコンバージョンのきっかけを生むなど、検索広告とは異なる役割を担います。
本記事では、Googleディスプレイ広告の仕組みや使い方を初心者にもわかりやすく解説しつつ、検索広告との違いや併用のコツまで詳しく紹介します。
- Googleディスプレイ広告とは?|検索広告との違いも解説
- ディスプレイ広告の配信面・広告形式・ターゲティングの種類
- Googleディスプレイ広告のメリットとデメリット
- Googleディスプレイ広告で成果を出すための設計・運用ポイント
- 検索広告との併用で成果を最大化するには?
- よくある質問(FAQ)
- まとめ|Googleディスプレイ広告を成果につなげるために
1.Googleディスプレイ広告とは?|検索広告との違いも解説
Googleディスプレイ広告は、検索行動をしていないユーザーにもアプローチできる広告手法で、視覚的な訴求力が強みです。検索広告との大きな違いは、"検索意図の顕在化"を前提としない点にあります。このセクションでは、ディスプレイ広告の仕組みと検索広告との違い、それぞれの使い分け方について順を追って見ていきましょう。
ディスプレイ広告の基本構造と特徴(GDNとは)
Googleディスプレイ広告は、Googleが提供する「Google ディスプレイ ネットワーク(GDN)」を通じて、数百万の提携サイト・アプリ・YouTubeなどに広告を表示できる広告配信手法です。検索行動をしていない潜在層にアプローチできるのが最大の特徴で、視覚的に訴求しやすいのも魅力です。
検索広告との違いと使い分け
検索広告は「今すぐ探している」顕在層向け、ディスプレイ広告は「興味を持つ可能性のある」潜在層向けの広告です。検索広告はテキスト中心で、検索結果ページに表示されますが、ディスプレイ広告は静止画・動画・バナーなどが主で、コンテンツの合間に表示されます。
2.ディスプレイ広告の配信面・広告形式・ターゲティングの種類
Googleディスプレイ広告は、GDN(Google ディスプレイ ネットワーク)を通じて、幅広い場所に広告が配信されます。これにはニュースサイト、ブログ、アプリ、YouTubeなどの他、最近では 、X(旧Twitter)上にも一部広告が配信されています。これはGoogleが一部の広告枠を拡張的に活用しており、配信先の柔軟性が高まっています。
どこに広告が表示される?
-
Googleが提携するニュースサイトやブログなど(GDN)
-
Gmailの広告枠
-
YouTubeのバンパー広告やディスプレイ広告位置
-
スマートフォンアプリの広告スペース
-
X(旧Twitter)の一部広告枠(キャンペーン設定によって自動で配信対象となる場合あり)
広告形式
-
レスポンシブディスプレイ広告(画像・見出し・説明文を組み合わせて自動最適化)
-
アップロードディスプレイ広告(既存の静止画・GIF・HTML5バナーを使用)
-
動画広告(YouTube上でのディスプレイバナーやショート広告)
.png?width=825&height=464&name=%E3%83%95%E3%82%A1%E3%83%8D%E3%83%AB%E5%88%A5%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%82%B2%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%B3%E3%82%B0menu(5).png)
主なターゲティングの種類
-
オーディエンスターゲティング(興味・購買意向・カスタムオーディエンスなど)
-
コンテンツターゲティング(掲載先のカテゴリやキーワード)
-
データセグメント(旧リマーケティング)(自社サイト訪問者など)
-
属性ターゲティング(地域・年齢・性別などのユーザー属性指定)
3.Googleディスプレイ広告のメリットとデメリット
たとえば、あるBtoB機器メーカーでは、自社サイトに一度訪問したものの、問い合わせに至らなかったユーザーに対してリマーケティング(現:自分のデータ セグメント)を活用しました。製品の導入事例や活用シーンを紹介する静止画バナーを展開した結果、再訪問率が約2.5倍に向上。最終的にホワイトペーパーのダウンロードや見積依頼数の増加にもつながりました。
このように「一度接点を持ったユーザーへの再アプローチ」として、ディスプレイ広告は非常に効果的です。
メリット
-
潜在層に早期にブランド認知ができる
-
検索広告よりもクリック単価が安い傾向
-
静止画・動画を使って視覚的に強く訴求できる
-
サイト訪問履歴を活用したリマーケティングに強い
デメリット
-
今すぐ購入したい層に対する即効性は低め
-
ターゲティングを誤ると無駄クリックが発生しやすい
-
成果に直結させるには中長期視点の運用が必要
向いている業種・商材
ディスプレイ広告は、比較的クリック単価が安価で、視覚的にユーザーの記憶に残りやすいため、幅広い業種に向いています。特に以下のような目的やフェーズにあるビジネスにおいて、高い効果が期待されます
-
ブランド訴求が重要な商材(飲料、化粧品、家電など)→ 消費者の感覚・印象に訴える静止画・動画の活用が効果的
-
比較・検討が必要なBtoB製品→ 認知→資料請求・セミナー誘導への導線設計に有効
-
アプリ訴求やLINE登録など“接点づくり”が目的の施策→ モバイルデバイスへの高頻度接触によって成果につながりやすい
また、ターゲティング設計とクリエイティブの組み合わせ次第で、低予算からでも成果を出しやすく、 ブランド認知から見込み顧客の育成まで一貫した広告戦略を構築することが可能です。
-
ブランド訴求が重要な商材(飲料、化粧品、家電など)
-
比較・検討が必要なBtoB製品
-
アプリ訴求やLINE登録など“接点づくり”が目的の施策
活用事例|ディスプレイ広告の成功活用パターン
① BtoB製造業:無名製品の認知獲得+リード創出
中堅の精密部品メーカーでは、自社名・製品名での検索が少なかったことから、業界・用途に関連する興味関心オーディエンスを対象に、静止画ディスプレイ広告を配信。
月額広告費は約50〜80万円で、製品の訴求とホワイトペーパー導線を中心に展開した結果、月間リード数が約1.8倍に増加。検索広告と併用することで、商談化率の向上にも貢献した。
② 美容・化粧品業界:動画クリエイティブによるブランド印象の構築
新商品のローンチに合わせて、20〜30代女性向けにYouTubeとGDNで動画ディスプレイ広告を展開。TVCMと連動したクリエイティブでブランド認知の統一感を持たせた。
月間広告予算は約100〜150万円。指名検索がキャンペーン中に前年比240%増加し、検索広告経由のCVRも大幅に改善。EC売上にも好影響を与えた。
③ 教育サービス:リマーケティング活用で申込率向上
資格系のオンラインスクールでは、検索広告でLPを訪問したがCVに至らなかった層に対し、ディスプレイ広告で再訴求。受講後のキャリアや受講者の声を静止画で訴求。
月額広告費は約30〜50万円で運用。再訪率は約2.3倍、申込率は1.5倍に向上し、コンバージョンまでのリードタイムも短縮された。
4.Googleディスプレイ広告で成果を出すための設計・運用ポイント
たとえば、ある教育系オンラインスクールでは、興味関心ベースのオーディエンスターゲティングを用いたディスプレイ広告を展開し、サイト訪問につながるCTRが従来のSNS広告の約1.8倍に改善しました。視覚的な訴求を工夫し、レスポンシブ広告で複数パターンのバナーを用意することで、幅広い層へのクリック誘導に成功した好例です。
ただ広告を配信するだけでは、ディスプレイ広告は思ったような成果につながらないこともあります。このセクションでは、より高い効果を得るために押さえておくべき設計と運用のポイントを整理して紹介します。
ターゲティング設計
オーディエンス(興味・購買意向など)とコンテンツ(掲載面)の2軸を組み合わせ、的確に潜在層へアプローチ。配信対象の属性や関心に沿ってカスタムオーディエンスも活用。
広告クリエイティブの考え方
-
視覚的に目を引く画像・色使い・キャッチコピー
-
「メリット+信頼」のバランスが重要
-
レスポンシブ形式では多パターン素材の用意が成果に直結
リマーケティングで検索広告と連携
検索広告でサイトに訪れたものの、すぐにコンバージョンしなかったユーザーを、ディスプレイ広告を通じて再アプローチすることで成果に結びつけることができます。
たとえば、ある不動産仲介会社では、検索広告からの訪問者に対し、ディスプレイ広告で物件のバナーを配信。再訪を促すことで資料請求率が約1.6倍に向上し、結果的に見学予約へとつながったケースがあります。
-
検索広告でサイトに来たユーザーを、ディスプレイ広告で再度アプローチ
-
“忘れられ防止”や購入検討の後押しとして効果的
除外設定・配信先コントロールのコツ
-
成果が出にくいドメインやカテゴリは除外
-
広告表示の質を保つためのフィルター設定も推奨
5.検索広告との併用で成果を最大化するには?
検索広告とディスプレイ広告は、役割や配信対象が異なるからこそ、組み合わせて使うことで大きな効果を発揮します。このセクションでは、併用のメリットや活用パターンを紹介します。
たとえば「外壁塗装 費用」であれば購入検討段階のユーザーにリーチできますが、「外壁塗装 失敗談」などは除外対象にすべきです。無駄なクリックを減らすことで、予算の効率的な運用が可能になります。
ファネル設計での使い分け
-
認知(ディスプレイ)→ 検討(検索)→ 行動(CV)の流れを意識
-
キャンペーン設計も目的別に分けることで最適化しやすくなる
リマーケティング活用の具体例
-
検索広告で訪問→ディスプレイで再アプローチ→再訪・CV
-
動画視聴者に静止画ディスプレイを出すなど多面展開も有効
P-MAXとの使い分け
-
完全自動化のP-MAXでは制御しきれない配信面・ターゲットをGDNで補完
-
ブランド管理や目的別の切り分けを意識したハイブリッド運用を推奨
6.よくある質問(FAQ)
ディスプレイ広告について、よく寄せられる質問を、Q&A形式でまとめました。ぜひ疑問解消にお役立てください。
-
Q:検索広告と比べて費用対効果はどうですか?
A:即効性は低いですが、認知からの流入増加に寄与し、指名検索数アップにつながります。 -
Q:画像がなくても始められますか?
A:レスポンシブ広告では画像なしでも可能ですが、成果を出すには画像素材の準備が推奨されます。 -
Q:リマーケティングに予算をどれくらいかけるべき?
A:全体予算の20~30%程度を目安にし、データを見ながら最適化するのが基本です。 -
Q:成果を出すまでにどのくらいの期間がかかりますか?
A:ターゲティングの内容や広告素材によりますが、初期学習期間を含めて2〜4週間程度で配信の最適化が進みます。 -
Q:配信先はどこまで細かくコントロールできますか?
A:コンテンツカテゴリやプレースメント単位での除外・指定が可能です。また、不適切なサイトやアプリをブロックする設定も用意されています。 -
Q:スマートキャンペーンやP-MAXと何が違いますか?
A:ディスプレイ広告は配信面やターゲティングを細かく設定できますが、スマートキャンペーンやP-MAXは自動最適化が前提です。目的や管理レベルに応じて使い分けることが重要です。
ディスプレイ広告は、Google広告の中でも“認知獲得に最も強い”配信手法です。検索広告との違いや役割分担を理解した上で、視覚的な訴求力や柔軟なターゲティング設定、再訪設計(リマーケティング)を活用することで、顕在層へのコンバージョン獲得にもつながる強力な戦略となります。
特にブランド認知や検討段階の接点づくりに課題がある企業にとって、ディスプレイ広告は広告戦略の幅を広げる有効な手段です。低予算からでも始められるため、初心者でもスモールスタートが可能で、改善を重ねることで成果につなげやすい特徴があります。
広告運用でお悩みの方、効果的なターゲティングやクリエイティブ設計に不安のある方は、ぜひ一度お気軽にお問い合わせください。
参考:ディスプレイ広告と Google ディスプレイ ネットワークについて- Google 広告 ヘルプ