【総集編・完全保存版】 大河ドラマ『べらぼう』全48話から読み解く 蔦屋重三郎に学ぶ、広告・マーケティングの原点と未来
NHK大河ドラマ『べらぼう ~蔦重栄華乃夢噺~』は、江戸という時代を舞台に、蔦屋重三郎という一人の版元の生涯を描き切りました。しかし本作が現代に投げかけたのは、歴史的成功譚ではありません。
それは、
価値はどのように生まれ、どう語られ、どう次の時代へ引き渡されるのか。
広告、マーケティング、事業、文化に共通する、極めて本質的な問いでした。
本連載では全48話を25回にわたり、ドラマの具体的な場面を手がかりに、江戸時代の出版・広告文化と現代マーケティングを重ねて読み解いてきました。本稿はその集大成として、蔦屋重三郎という存在が、私たちの仕事に何を教えてくれるのかを総覧します。

- 第1章:蔦屋重三郎は「売る人」ではなく「編集する人」だった
- 第2章:江戸にすでに存在した「市場創造」の思想
- 第3章:噂・草稿・物語──「伝えた」のではなく「語られた」
- 第4章:危機・炎上・ナラティブの書き換え―「守る」のではなく「意味を奪い返す」
- 第5章:残し方・承継・レガシー―「終わらせ方」を設計した蔦屋重三郎
- おわりに:すべては「何を残すか」という問いに収束する
- あとがき:この連載を読んでくださった皆様へ
第1章:蔦屋重三郎は「売る人」ではなく「編集する人」だった
.png?width=756&height=422&name=A_photorealistic_depiction_of_an_Edo_period_street-1765785346771%20(1).png)
①ドラマの場面から読み解く
『べらぼう』の序盤から中盤にかけて一貫して描かれるのは、蔦屋重三郎が作品を「商品」として即断しない人物であるという点です。
浮世絵や黄表紙を前にしたとき、蔦重はまず値段や刷り部数、あるいは「売れるかどうか」といった話をしません。彼が最初に投げかけるのは、常に次のような問いです。
-
これは、今の江戸でどう見られるのか
-
誰がこれを見るのか、どんな立場の人の目に触れるのか
-
この絵や本は、今という時代と、どう関係づけられるのか
つまり蔦重は、作品を“単体”として見るのではなく、
社会の中に置かれた瞬間の姿を想像してから判断しています。
その姿勢は、作品を世に出すプロセスにも色濃く表れます。
-
どの場面を切り取るか
-
誰の名を前に出すか
-
どの順で世に出すか
-
何と並べて見せるか
これらは一見すると細かな演出に見えますが、実際には「どう解釈されるか」を左右する極めて重要な要素です。
ドラマでは、蔦重がこの配置や関係性について、異様なほど時間をかけ、悩み、周囲と議論する姿が描かれます。それは、彼にとって、作品の完成=世に出す準備が整った状態ではなかったことを意味しています。
➁その場面で起きていた「選択の分岐」
ここで重要なのは、蔦屋重三郎には、もっと分かりやすく、楽な選択肢があったという点です。
例えば――
-
すでに流行している絵柄を真似て量産する
-
世間で名の通った絵師や戯作者の名前だけを前面に出す
-
今売れているジャンルを後追いし、外さない商品だけを並べる
これらは、商人として見れば極めて合理的です。
在庫リスクは低く、短期的な利益も見込みやすい。
江戸の町には、実際にそのやり方で商いをしている本屋も数多く存在していました。
つまり蔦重は、
「特別なことをしなければならなかった」わけではありません。
あえて、簡単な道を選ばなかったのです。
③ 蔦屋が選ばなかった道(=危うさ)
蔦重が「売れるものを並べる」道を選ばなかった理由は、
それが長く続かない商いであることを、肌感覚で理解していたからです。
流行を追えば、商品は確かに売れます。
しかしその場合――
-
売れたのは「蔦屋だから」ではない
-
名前ではなく「流行」だけが記憶に残る
-
流行が終わった瞬間に、次の軸がなくなる
という状態に陥ります。
商品が主役の商いでは、
商品が消えた瞬間に、商いそのものも終わってしまう。
蔦重はそれを避けるために、
商品より先に「蔦屋」という意味を作ろうとしたのです。
結果として彼は、250年前にすでに
「売る前に意味を編集する」
という、極めて現代的な仕事をしていました。
④ 蔦屋がやっていた構造的な仕事
蔦屋重三郎が本質的にやっていたのは、
商品を売ることではなく
「意味が流通する回路」を編集することでした。
彼は、単体ではバラバラに存在している
-
絵師の才能
-
戯作者の発想
-
江戸の流行
-
庶民の関心や不満
を束ね、それらを「今の江戸にとって、これは面白い」
「今、この形で世に出す意味がある」と翻訳して、社会に送り出します。
これは、職業名で言えば、編集者であり、同時にプロデューサーの仕事です。
重要なのは、蔦重が「自分が表に立つ主役」ではなく、
意味が伝わる構造そのものを作る裏方に徹していた点です。
⑤ 現代での具体的な実務例
現代でこの役割に最も近いのは、次のような立場です。
-
コンテンツマーケティングの編集責任者
-
ブランドマネージャー
-
プロダクトマネージャー
これらの仕事に共通するのは、
「良いものを作れば売れる」とは考えていない点です。
どんなに優れた商品やコンテンツであっても、
-
どんな文脈で語られるか
-
どんな順番で顧客と出会うか
-
何と並べて見られるか
が設計されていなければ、
市場では存在しないのと同じになります。
蔦屋の仕事は、
現代でいう「編集責任を持つ仕事」の原型だと言えます。
⑥ この章から残る問い
この章が、現代の私たちに突きつけている問いは明確です。
あなたの仕事は、
「商品を作る仕事」でしょうか。
それとも「意味を編集する仕事」でしょうか。
もし「作ること」だけに集中しているなら、意味づけは誰が担っていますか。
その役割は、きちんと設計されていますか。
蔦屋重三郎が250年前に示したのは、意味を編集できる者だけが、時代を超えて名前を残す
という、厳しくも普遍的な現実でした。
第2章:江戸にすでに存在した「市場創造」の思想
.png?width=788&height=439&name=A_photorealistic_depiction_of_an_Edo_period_street-1765785517172%20(1).png)
① ドラマの具体的な場面
『べらぼう』の中盤で繰り返し描かれるのが、芝居・遊里・出版を取り巻く“冷えた空気”です。
倹約令や風紀粛清によって、
-
芝居は公には好ましくないものとされ
-
派手な遊興は抑えられ
-
表立った娯楽消費は肩身の狭いものになる
町の側から見れば、「もうこの商売は厳しい」という空気が漂っています。
しかしドラマでは同時に、庶民が芝居役者の噂話をしたり、
絵や読み物に目を輝かせたりする様子も、さりげなく描かれます。
つまりそこには、
-
表では「抑えられている」
-
しかし内側では「消えていない」
という、二重構造の需要が存在していました。
蔦屋重三郎は、この矛盾にいち早く気づきます。
「芝居がダメになった」のではない。
「芝居を好きだと言えなくなっただけ」だと。
② その場面で起きていた「選択の分岐」
この状況で、多くの商人が取った選択は明快です。
-
規制に従い、扱いを縮小する
-
危ない領域からは距離を取る
-
市場が冷えたと判断し、別の商売に移る
これは、短期的には正しい判断でした。
余計なリスクを負わず、当局とも揉めず、「何も起こらない」ことを優先する選択です。
蔦重自身も、その道を選ぶことはできました。
③ 蔦屋が選ばなかった道
しかし蔦屋は、
「市場がなくなった」という見方そのものを疑います。
なぜなら彼の目には、
-
芝居を語りたがる人
-
役者の絵を欲しがる人
-
読み物に熱を注ぐ人
が、はっきりと見えていたからです。
もしここで「市場は死んだ」と判断してしまえば、
それは “需要がない”のではなく、“需要を読む力を失った”
ということになります。
蔦屋が避けたのは、
規制=需要消滅と短絡的に結びつける思考でした。
④ 構造的な仕事
蔦屋重三郎がやったのは、
「既存市場で戦うこと」ではありません。
彼は、
市場を“作り直す”
という選択をしました。
具体的には、
-
芝居そのものではなく「役者の姿」を絵にする
-
公には語れない熱量を「浮世絵」という許された形に変換する
-
娯楽を“体験”ではなく“所有できるコンテンツ”に置き換える
これによって、
「芝居に行くことができない人」も、
「芝居を語れない人」も、
役者文化に参加できる市場が生まれます。
これは単なる代替商品ではありません。
需要の入口を再設計した市場創造です。
さらに写楽プロジェクトでは、
-
個人名を前に出さない
-
世界観と衝撃性で認知を作る
という手法が取られます。
これは、「誰が描いたか」より
「何が起きているか」に注目させる設計でした。
⑤ 現代での具体例
この構造は、現代でも驚くほど頻繁に使われています。
例えば――
-
広告規制が厳しい業界で、
商品広告ではなくコンテンツやコミュニティで接点を作る -
マス広告が打てない中で、
IP・キャラクター・世界観から市場を立ち上げる -
D2Cブランドが、
機能ではなく「使う理由」「語れる価値」から市場を作る
いずれも共通しているのは、
市場は最初から存在しているものではなく、
意味づけによって立ち上がるもの
という前提です。
蔦屋がやっていたのは、
「顧客を探す」ことではなく、
顧客が参加できる形を設計することでした。
⑥ 残る問い
この章が、私たちに突きつけている問いは次の一文に集約されます。
あなたは今、
「市場がない」と言って諦めているだけではないでしょうか。
その市場は、本当に存在しないのか。
それとも、
今の形では“参加できない”だけではないのか。
蔦屋重三郎は、
規制や逆風の中でこそ、
「市場を作り直す」という選択肢があることを示しました。
市場創造とは、
新しい需要を生むことではありません。
すでにある欲望に、入り口を与えることなのです。
第3章:噂・草稿・物語──「伝えた」のではなく「語られた」
.png?width=1024&height=571&name=In_an_Edo_period_town_bustling_with_life_people_e-1765786463075%20(1).png)
① ドラマの具体的な場面
『べらぼう』の中盤以降、物語の随所に登場するのが、
噂・流言・未完成の物語です。
代表的なのが、
-
平賀源内は生きているのではないか、という「源内生存説」
-
正体不明の存在として語られる「七ツ星の龍」
-
完成前の草稿や構想だけが人づてに伝わる読み物
これらは、いずれも
蔦屋が公式に「発表した広告」ではありません。
にもかかわらず、江戸の町では、
-
人から人へ
-
茶屋から長屋へ
-
芝居小屋から書肆へ
と、驚くほどの速さで広がっていきます。
重要なのは、
これらが「完成された情報」ではなく、
断片的で、曖昧で、想像の余地を残した情報だった点です。
② 選択の分岐
蔦重には、より分かりやすい方法もありました。
-
完成した絵や本だけを出す
-
内容を明確に説明する
-
誤解の余地を残さない
これは、現代的に言えば
「誤解されない広告」「炎上しない広報」です。
多くの商人や為政者は、
情報は管理すべきものだと考えていました。
③ 蔦屋が選ばなかった道
しかし蔦屋は、
情報を完全にコントロールする道を選びませんでした。
なぜなら、
人は説明されたことより、想像したことを語る
という性質を、彼が直感的に理解していたからです。
すべてが説明されてしまえば、
人はそれ以上、口を挟む余地がありません。
蔦重はあえて、
-
正体を曖昧にし
-
物語の全体像を明かさず
-
「本当かどうか分からない」状態を残す
ことで、
語りの主語を人々に渡しました。
これは、広告としては非常に危うい選択でもあります。
しかし同時に、
最も強い拡散を生む選択でもありました。
④ 構造的な仕事
蔦屋重三郎がやっていたのは、
情報を広めること
ではなく
語られる構造を仕込むこと
です。
噂が広がるとき、人は必ずこう言います。
-
「聞いた話なんだけどさ」
-
「本当かどうか分からないけど」
-
「あれ、知ってる?」
つまり噂とは、
誰かが語り手になる前提で成立するメディアです。
蔦重は、
-
未完成
-
不確定
-
正体不明
という状態を意図的に残すことで、
広告を「見るもの」から
「語るもの」へと変換しました。
これは、江戸版の“自然拡散型メディア設計”と言えます。
⑤ 現代での具体例
この構造は、現代の広告・マーケティングでも極めて重要です。
例えば――
-
ティザー広告で、すべてを明かさない
-
SNSで、公式よりもユーザーの解釈が先に広がる
-
UGC(ユーザー生成コンテンツ)を前提に設計する
-
あえて「余白」を残したコピーやビジュアルを使う
これらはすべて、
企業が語るのではなく、
人が語りたくなる状態を作る
という発想に基づいています。
広告費をかけても拡散しない施策がある一方で、
ほとんど説明していないのに広がる事例があるのは、
この「語りの設計」ができているかどうかの違いです。
⑥ 残る問い
この章が、私たちに突きつける問いは次の通りです。
あなたの広告や情報発信は、
「伝えきること」に力を注ぎすぎていないでしょうか。
その結果、
人が語る余地を奪っていないでしょうか。
蔦屋重三郎が示したのは、
広告とは「説明する技術」ではなく、
「物語を手放す勇気」でもあるという事実です。
語られる広告は、
作った瞬間ではなく、
人の口に乗った瞬間から力を持ち始めます。

① ドラマの具体的な場面
物語終盤に向けて描かれる「毒饅頭事件」は、『べらぼう』全体の中でも、蔦屋重三郎が最も厳しい局面に立たされる出来事です。
曽我祭の夜、差し入れとして配られた饅頭によって、蔦重の仲間たちは次々と倒れ、
芝居小屋は一瞬にして祝祭の場から地獄絵図へと変わります。
重要なのは、この事件が、
-
単なる暴力
-
単なる暗殺未遂
として描かれていない点です。
事件の直後、江戸の町では次のような「語り」が広がり始めます。
-
仇討ちを企てた者たちは愚かだった
-
蔦屋の周りは危ない
-
あそこに近づくと巻き込まれる
つまり毒饅頭事件は、人命を狙う行為であると同時に、物語を書き換えるための攻撃でもありました。
② 選択の分岐
この状況で、蔦屋重三郎にはいくつかの選択肢がありました。
-
しばらく店を閉め、嵐が過ぎるのを待つ
-
事件への関与を全面否定し、距離を取る
-
黙って耐え、「被害者」として振る舞う
いずれも、現代で言えば
炎上時に企業が取りがちな“守りの対応”です。
実際、多くの人にとっては
「何もしない」ことこそが、最も安全に見える選択です。
③ 蔦屋が選ばなかった道
しかし蔦屋は、
沈黙することも、逃げることも選びませんでした。
なぜなら、
沈黙は「安全」ではなく、
相手が作った物語をそのまま受け入れる行為だと理解していたからです。
もしここで何も語らなければ、
-
「毒饅頭=蔦屋側の自滅」
-
「正義を気取った者の末路」
という物語が、
事実として固定されてしまう。
蔦重が避けたのは、
事件そのものよりも、
意味が一方的に確定してしまうことでした。
④ 構造的な仕事
蔦屋重三郎が取った行動は、
「被害を最小化する」ことではありません。
彼が向き合ったのは、
事件の“解釈権”を取り戻すことでした。
毒饅頭という象徴が使われたなら、
その象徴の意味をひっくり返すしかない。
-
毒を使ったのは誰か
-
なぜその手段を選んだのか
-
本当に裁かれるべきなのは誰か
蔦重は、
相手が作ったフレームの中で戦うのではなく、
フレームそのものを書き換えようとします。
これは、危機対応を「守り」ではなく
編集による攻めとして捉える姿勢です。
⑤ 現代での具体例
この構造は、現代の企業活動にもそのまま当てはまります。
例えば――
-
不祥事や炎上が起きた際、
事実説明だけで終わらせるのか -
それとも
「なぜそれが問題だったのか」
「何を変えるのか」まで語るのか
この違いによって、
ブランドの評価は大きく変わります。
蔦重のやり方は、
-
事実を否定しない
-
しかし、意味を相手に渡さない
という高度なナラティブ戦略です。
現代で言えば、
-
レピュテーションマネジメント
-
クライシスコミュニケーション
-
ブランド再定義
の核心に当たります。
⑥ 残る問い
この章が、私たちに突きつける問いは明確です。
あなたは危機に直面したとき、
「何を守るか」ばかり考えていないでしょうか。
本当に守るべきなのは、
数字や表面の評価ではなく、
そのブランドが、どう記憶されるかではないでしょうか。
蔦屋重三郎は、
危機を避けることはできなくても、
危機の意味を選ぶことはできると示しました。
炎上や逆風は、
ブランドが壊れる瞬間であり、
同時に、物語を書き換える最後の機会でもあるのです。
.png?width=1024&height=571&name=A_photorealistic_scene_depicting_Jzabur_Tsutaya_-1765787171579%20(1).png)
① ドラマの具体的な場面
物語の最終盤、蔦屋重三郎は明らかに変わります。
かつてのように、目の前の一冊、一枚で勝負する姿は影を潜め、代わりに描かれるのは、
-
若い書き手に仕事を振る姿
-
すぐには売れない本にも価値を見出す姿
-
吉原の遊び方や金の流れそのものを整え直そうとする姿
です。
特に印象的なのは、
自らが病に侵され、先が長くないことを悟りながらも、
-
本居宣長のような「難しいが重要な書物」を世に出そうとする
-
十返舎一九や曲亭馬琴といった若い才能に、次の舞台を与える
-
「蔦屋」の看板を、誰にどう渡すのかを明確に示す
といった行動を、淡々と積み重ねていく点です。
ここで蔦重は、
自分がいなくなった後の世界を、明確に見据えています。
② 選択の分岐
この段階で、蔦重には別の選択肢もありました。
-
最後に一発、大きなヒットを狙う
-
名声を固める作品だけに集中する
-
「蔦屋重三郎」という個人の物語を、より強く印象づける
いずれも、
創業者・プロデューサーとしては自然な選択です。
多くの人は、
「最後は自分が主役で終わりたい」と考えるでしょう。
③ 蔦屋が選ばなかった道
しかし蔦重は、自分が主役のまま終わる道を選びませんでした。
もしそうしていれば、
-
蔦屋は「一代限りの天才」で終わり
-
周囲の才能は次につながらず
-
名前だけが語られ、仕組みは残らない
という結果になっていたはずです。
蔦重が避けたのは、
個人の成功が、文化の断絶になることでした。
④ 構造的な仕事
蔦屋重三郎が最後にやっていた仕事は、もはや出版でも商売でもありません。
それは、
文化が続くための「地面」を整えること
でした。
具体的には、
-
人を残す(次の書き手・描き手)
-
仕組みを残す(定期的に出る本、継続する棚)
-
ルールを残す(吉原の新しい取り決め)
-
名前を残す(「蔦屋」という編集思想)
という、レガシー設計です。
ここで重要なのは、
蔦重が「教え込む」のではなく、
自然に引き継がれる形を作った点です。
この章が、私たちに突きつける問いは、
これまでで最も重いものです。
あなたの仕事は、
あなたがいなくなった後も、続くでしょうか。
もし続くとしたら、
それは「成果」が残っているからでしょうか。
それとも、
考え方・仕組み・文化が残っているからでしょうか。
蔦屋重三郎が最後に示したのは、
事業とは「成功すること」ではなく、
引き継がれることによって完成する
という静かな真理でした。
おわりに:すべては「何を残すか」という問いに収束する
.png?width=1024&height=560&name=tsutajyunimanabu%20(1).png) 大河ドラマ『べらぼう』全48話を通して描かれた蔦屋重三郎の生涯は、
大河ドラマ『べらぼう』全48話を通して描かれた蔦屋重三郎の生涯は、
成功譚でも、成り上がり物語でもありませんでした。
彼が繰り返し向き合っていたのは、「どう売るか」「どう勝つか」ではなく、
「何を、どう残すのか」という問いだったように思います。
浮世絵や黄表紙を世に出すとき、蔦重は作品そのものよりも、
それが どんな文脈で、どんな意味として受け取られるか を考えていました。
市場が冷えたときには、市場が消えたとは考えず、
入り口の形を作り直す ことを選びました。
噂や草稿を扱うときには、すべてを説明することを避け、
人々が語り、想像し、関わる余白を残しました。
危機に直面したときには、沈黙や逃避ではなく、
意味を書き換える覚悟 を持って立ち向かいました。
そして晩年、自らが表舞台に立ち続けることよりも、
人・仕組み・ルールを残すことを選びました。
これらすべてに共通しているのは、
蔦屋重三郎が、「一時の成果」ではなく「続く価値」を見ていた、という一点です。
現代の私たちは、
データや指標、即効性のある施策に囲まれて仕事をしています。
それらは確かに重要です。
しかし同時に、
「この仕事は、何として記憶されるのか」
「誰かに引き継がれる形になっているのか」
という問いを、後回しにしがちでもあります。
『べらぼう』の最終話が静かに教えてくれるのは、
事業や仕事の価値は、始め方や勝ち方ではなく、終わり方によって輪郭が定まる
という事実です。
蔦屋重三郎が江戸の混乱期に示したのは、派手な成功ではありませんでした。
それでも彼の名と思想が残ったのは、文化と人と仕組みを、
丁寧に編集し続けたからでしょう。
変化が激しく、不確実な時代だからこそ、私たちもまた、「市場を読む」だけでなく、
「時代に何を残すか」という視点を仕事のどこかに持っていたいものです。
この連載が、日々の業務や意思決定の中で、ふと立ち止まり、
少し視点を引き上げるきっかけになれば幸いです。
あとがき:この連載を読んでくださった皆様へ
.png?width=1024&height=557&name=evoculture%20(1).png)
NHK大河ドラマ『べらぼう』の放送にあわせて始まったこの連載も、
全48話を見届け、この総集編をもって一区切りとなりました。
約1年間という時間の中で、毎回欠かさず読んでくださった方、
途中から興味を持って読み進めてくださった方、必要な回を行き来しながら参照してくださった方——
本当にありがとうございます。
この連載は、単なるドラマ解説やレビューを目的としたものではありませんでした。
蔦屋重三郎という人物を通して、
-
広告とは何か
-
マーケティングとは何か
-
価値はどのように生まれ、どう残るのか
といった、時代を超えて変わらない問いを、現代の仕事や事業と重ねて考える場にしたい、
そんな思いから書き続けてきました。
江戸という時代に描かれた出来事は、決して遠い過去の物語ではありません。
市場が揺れ、価値観が変わり、規制や逆風の中で、それでも何かを生み出そうとする人々の姿は、
今を生きる私たちの仕事と、驚くほど重なります。
連載を通じてお伝えしたかったのは、「正解」や「成功法則」ではなく、
考え続けるための視点でした。
・売る前に、意味を編集すること
・市場がないときこそ、入口を作り直すこと
・語られる余白を残すこと
・危機にこそ、物語を書き換える覚悟を持つこと
・そして、何を残すかを考えること
これらは、すぐに答えが出るものではありません。
けれど、仕事のどこかで立ち止まったとき、判断に迷ったとき、ふと立ち返れる軸として、
心に残っていれば嬉しく思います。
連載という形で書き続けることができたのは、読んでくださる方がいたからこそです。
ページを開いてくださったその時間が、この文章を「連載」にしてくれました。
改めて、約1年間お付き合いいただき、ありがとうございました。
このシリーズが一区切りを迎えたいまも、蔦屋重三郎が示した問いは、
私たちが仕事や事業に向き合うたび、何度でも問い返されるものだと思います。
時代や手法が変わっても、その問いだけは、これからも手放せないはずです。
連載を始めたきっかけ
―「増田コレクション」と、広告の原点に触れて
この連載を始めた背景には、
私たち株式会社evoliaが所有・管理している
江戸時代から明治期にかけての広告資料群「増田コレクション」の存在があります。
増田コレクションには、引札(ひきふだ)をはじめとする、当時の商いや暮らし、
そして人々の価値観が色濃く反映された資料が数多く残されています。
そこに描かれているのは、単なる商品説明ではありません。
-
なぜこの店なのか
-
なぜ今、これを選ぶのか
-
この店と付き合うと、どんな未来があるのか
そうした問いに、絵や言葉、構図や物語で応えようとする、
極めて高度な「広告の思想」が詰まっています。
私たちはこれまで、東京都のプロジェクトとして、
引札をモチーフにした商品開発や販売、また引札や江戸期の広告文化をテーマにした展示会の企画・運営などにも携わってきました。
その過程で強く感じたのが、これらの資料が、
「過去のもの」ではなく、「今こそ読み直すべきもの」だということでした。
大河ドラマ『べらぼう』で描かれた蔦屋重三郎の姿は、まさにその感覚と重なります。
売るために語るのではなく、意味を編み、文脈をつくり、文化として残していく。
引札に込められた工夫や思想と、蔦屋重三郎の編集的な仕事は、時代を越えて響き合っていました。
だからこそ私たちは、このドラマを単なる歴史作品として消費するのではなく、現代の広告・マーケティング・事業に通じる視点から読み解く連載として残したいと考えました。
evoliaでは、広告やマーケティングの支援にとどまらず、
-
大相撲の海外公演
-
歌舞伎をはじめとする伝統芸能の企画
-
伝統工芸のリブランディング
-
日本文化を軸にしたプロジェクト設計
など、日本文化の価値を、現代の文脈で伝え直す取り組みも行っています。
もしこの連載を通して、
-
江戸の広告文化に面白さを感じた方
-
文化や歴史を、事業やブランドづくりに生かしたいと感じた方
-
日本文化を、次の世代や海外へどう伝えるかを考えている方
がいらっしゃいましたら、ぜひお気軽にお問い合わせください。
過去を懐かしむためではなく、未来につなぐために文化を扱う。
その姿勢は、蔦屋重三郎が生きた時代から、今も変わらず有効だと、私たちは信じています。
Tokyo Tokyo(東京おみやげプロジェクト)について
https://tokyotokyo.jp/ja/action/omiyage/
江戸時代から明治時代に使われていた「引札(宣伝用チラシ)」には、当時の日本の文化や暮らしが色濃く反映されています。私たちは、この歴史的に貴重な引札のデザインを現代に活かすため、東京都が進める「東京おみやげプロジェクト」に参画し、伝統的な日本の魅力が詰まった商品の開発と販売を行っています。
東京都と民間企業が共同で開発した伝統的な工芸品から文房具、食料品など、東京旅行の思い出をもっと楽しくするアイテム「東京おみやげ」のPR・販売拠点「# Tokyo Tokyo BASE」(羽田空港)で販売しています。
引札の魅力や現代の広告や商品開発に引札のエッセンスを取り入れたい方は、お気軽にご相談下さいませ。


.png)
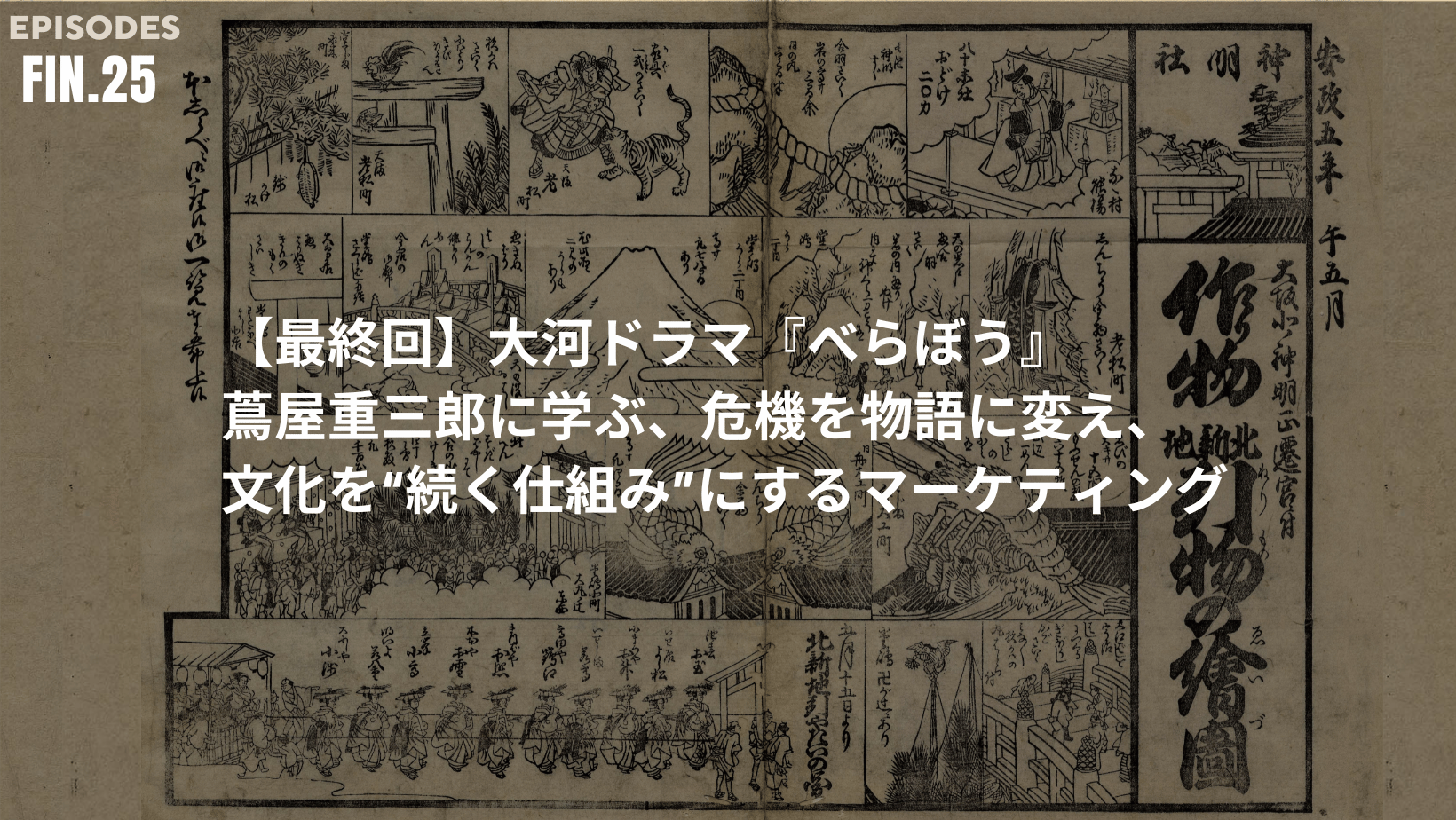
.png)