大河ドラマ『べらぼう』蔦屋重三郎に学ぶ危機管理とメディア戦略
2025年に放送されたNHK大河ドラマ『べらぼう ~蔦重栄華乃夢噺~』の第33話と第34話では、天明7年(1787年)の打ちこわし騒動から寛政の改革開始までの激動期が描かれます。この時期は、蔦屋重三郎が直面した最大の危機の一つであり、同時に松平定信による巧妙なメディア戦略が展開された時代でもありました。
第33話「打壊演太女功徳」では、江戸を揺るがした打ちこわし騒動における蔦重の危機管理能力と社会的責任が描かれます。一方、第34話「ありがた山とかたじけ茄子」では、松平定信による「読売」を活用した世論操作と、それに対抗する蔦重の文化的戦略が展開されます。
これらの物語は、現代企業が直面する危機管理、メディア戦略、情報統制への対応、そしてSNS時代における世論形成について、深い示唆を与えてくれます。特に注目すべきは、松平定信による「読売」を活用した組織的な世論操作が、現代のSNSマーケティングやインフルエンサー戦略と驚くほど類似した構造を持っていることです。江戸時代の情報戦略から学ぶ実践的なビジネス戦略への応用可能性をみていきます。
.png?width=674&height=380&name=tsutajyu18%20(1).png)
1.第33話「打壊演太女功徳」:危機時のリーダーシップと社会的責任
あらすじ
天明7年(1787年)、江戸各地で米不足と物価高騰により庶民の不満が爆発し、「政を正せ」と書かれた幟を掲げた新之助たち町人一党による打ちこわしが本格的に始まります。田沼家御用米屋の破壊がきっかけとなり、米俵が道にばら撒かれ、群衆も加勢する事態に発展しました。
この混乱の中、蔦屋重三郎は幕府と庶民の間で奔走し、米の代わりに銀を配るという革新的なアイデアを田沼意次に提案し、混乱収拾に貢献します。江戸城では老中・田沼意次が状況把握と対応に追われ、町奉行が動き出す中、長谷川平蔵(鬼平)が正式登場し、鎮圧の役目を果たしました。
物語のクライマックスでは、新之助が身を挺して蔦重を守り、襲撃者に刺され命を落とします。最愛の友を失った蔦重は深い喪失感に打ちひしがれ、「命の重さ」と「人の生きる意味」について深く思い悩むことになります。この体験が、後の蔦重の人生観と事業戦略に大きな影響を与えることになります。
1. 危機時のリソース代替戦略
米不足による社会混乱に対し、蔦重は「米が供給できないなら銀を配り、民の購買力を維持する」という革新的な代替戦略を提案しました。これは直接的な商品供給が困難な状況において、貨幣価値の提供により需要を満足させ、同時に市場の混乱を防ぐという二重の効果を狙った画期的なアプローチでした。
現代の課題と対応策
現代企業においても、サプライチェーン断絶や原材料不足といった危機的状況は頻繁に発生します。このような場面では、代替品の提供、デジタル化による価値転換、サブスクリプション形式での継続的価値提供など、多様な代替戦略が重要な役割を果たします。コロナ禍でのデジタル決済促進や、エネルギー危機時の再生可能エネルギーへの転換などが現代的な対応例です。
江戸時代と現代の比較
蔦重の銀配布戦略と現代の代替戦略は、本質的に同じ発想に基づいています。固定的な思考の枠を超えた柔軟性と創造性により、価値の形態転換を通じて危機を乗り切る点で共通しています。現代企業には、事前に複数の価値提供手段を準備し、危機時には迅速に代替手段に切り替える柔軟性が求められており、これは蔦重が260年前に示した適応力と同じ本質を持っています。
2.コミュニティリーダーシップと信頼構築
江戸時代の課題と対応策
蔦重は出版業者としての本業を超えて、地域コミュニティの安定化に積極的に関与しました。幕府と庶民の間に立ち、双方の利益を調整する仲介者として機能することで、長期的な事業基盤の安定化を図ったのです。打ちこわし騒動では、単なる傍観者ではなく積極的な解決策提案者として行動しました。
現代の課題と対応策
現代のコミュニティマーケティングにおいても、企業は単なる商品・サービス提供者を超えて、コミュニティの価値創造に貢献する役割が期待されています。地域課題の解決、ステークホルダー間の利害調整、社会的価値の創出などを通じて、持続可能な競争優位を構築することが重要です。
江戸時代と現代の比較
蔦重のコミュニティリーダーシップと現代のESG経営は本質的に同じ考え方です。企業がコミュニティの「良き市民」として行動し、平時からの信頼関係構築が危機時の協力獲得につながるという原理は変わりません。現代ではSNSコミュニティの運営、地域パートナーシップの構築、多様なステークホルダーとの対話などが実践方法となります。
3. 危機時コミュニケーション戦略
江戸時代の課題と対応策
「政を正せ」という幟が示すように、庶民の不満を的確に言語化し、社会現象へ導く「メッセージ戦略」の重要性が描かれています。蔦重は混乱の中でも冷静に状況を分析し、効果的な解決策を政策決定者に提言する能力を発揮しました。感情的な対立を避けながらも、核心的な問題解決に向けた建設的な提案を行うことで信頼を獲得しました。
現代の課題と対応策
危機時の企業コミュニケーションでは、ステークホルダーの感情に寄り添いながらも、建設的で具体的な解決策を提示することが重要です。SNSでの迅速な情報発信、透明性のある状況説明、関係者への個別フォロー、そして何より感情的な対立を避けた冷静な対応が求められます。
江戸時代と現代の比較
蔦重の危機時コミュニケーションと現代の危機管理広報は、本質的に同じ原理に基づいています。事実の正確な伝達と関係者の感情面への配慮を両立させる点で共通しています。現代では、データに基づく客観的説明と共感を示す人間的なメッセージを組み合わせた「ハイブリッド型コミュニケーション」として実践されています。
2.第34話「ありがた山とかたじけ茄子」:情報戦略と文化的対抗
あらすじ
打ちこわし騒動後、江戸の街には無数の土饅頭が築かれ、深い悲嘆が街全体を覆います。物語は新たな局面へと転換し、松平定信が老中として「寛政の改革」を推進し始め、質素倹約令が発布されます。庶民文化の取り締まりが強化される中、蔦重は「文化を守る」という強い信念を胸に、新たな戦いへの決意を固めていきます。
意気消沈していた蔦重を救ったのは、成長した絵師・歌麿の「命を写した絵」でした。その絵からほとばしる生気を感じ取った蔦重は希望を取り戻し、歌麿と共に新たな挑戦への道のりを歩み始めます。この時期の江戸社会は「改革派」と「庶民文化派」が激しく対立する構図となり、蔦重の出版活動にも厳しい規制の波が押し寄せることになります。
この話で最も注目すべきは、松平定信による「読売」を活用した組織的なメディア戦略です。定信は老中首座就任後、江戸の街で自身を賛美する「読売」を意図的に流通させました。「吉宗公の孫→生まれ変わり」「熊をも倒した柔術の達人」といった内容は、偶然の産物ではなく戦略的に計画された情報操作でした。一方、蔦重はこの組織的な情報統制に対して、文化的・創作的手法で対抗していくことになります。
1. 松平定信の「読売」活用メディア戦略
江戸時代の課題と対応策
松平定信は政治的正統性と民衆の支持を獲得するため、「読売」を活用した組織的なメディア戦略を展開しました。「吉宗公の孫」「生まれ変わり」「柔術の達人」といったメッセージは、権威との接続、神格化、能力の誇張という三つの戦略的要素を含んでいました。さらに「田沼病」というフレーミングにより、競合の田沼政治を病的なものとして印象操作しました。
現代の課題と対応策
現代のインフルエンサーマーケティングやSNS戦略では、定信の手法と同様のアプローチが用いられています。ブランドストーリーテリング、権威性の転移活用、感情的訴求、問題設定マーケティングなどの手法が、現代のデジタルマーケティングの基本原則として幅広く活用されています。創業者の物語を企業価値と結びつけたり、業界権威や学術機関との関連付けを通じて信頼性を構築したりしています。
江戸時代と現代の比較
松平定信の「読売」戦略と現代のインフルエンサーマーケティングは、本質的に同じ心理メカニズムを活用しています。第三者効果、権威性の原理、ハロー効果、社会的証明などの心理的影響力が共通しています。異なるのは情報拡散の速度と受け手の批判的思考能力です。現代では、情報のファクトチェックが容易であり、透明性と信頼性がより一層重要な競争優位の源泉となっています。
2.隠密ネットワークによる情報収集システム
江戸時代の課題と対応策
松平定信は隠密を活用して市井の声を収集し、リアルタイムで民心を把握するシステムを構築していました。茶屋、市場、長屋での聞き込み、表情や口調からの感情分析、意見形成力のある商人や職人の特定、問題のある噂への対抗情報の流布など、現代のSNSモニタリングツールと本質的に同じ機能を果たしていました。このシステムは、情報発信→市民反応→隠密による報告→戦略修正というリアルタイム・フィードバックループを形成していました。
現代の課題と対応策
現代企業においても、ソーシャルリスニングツールを活用したリアルタイム世論監視、AIによるセンチメント分析、マイクロインフルエンサーとの関係構築、炎上や評判悪化の早期警戒システムなど、定信の隠密システムと類似した機能が重要な役割を果たしています。SNS投稿の分析、エンゲージメント率の高いアカウントの特定、ネガティブ投稿への対応、PR戦略の修正などが現代的な実践方法となっています。
江戸時代と現代の比較
定信の隠密ネットワークと現代のSNSモニタリングは、多層的影響力ネットワークの活用、リアルタイム・フィードバックループの構築、オーガニックリーチの演出という点で本質的に同じ構造を持っています。現代では、24時間365日の監視体制、AIによる自動分析、予測的対応など、技術の進歩により効率性と精度が向上していますが、人間の感情や行動パターンを理解して世論を把握するという基本的な考え方は変わっていません。
3.蔦重の文化的対抗戦略と創造的レジスタンス
江戸時代の課題と対応策
松平定信による表現規制・質素倹約令に対して、蔦重は直接的な反論を避け、文化的・創作的手法で対抗しました。二重メッセージ戦略により表面的には定信を褒めながら実は皮肉を込める黄表紙の出版、狂歌や浮世絵という「娯楽」の形で批判的メッセージを埋め込む手法、戯作者・絵師・狂歌師という創作者ネットワークによる文化的影響力の構築などを通じて、短期的な政治変化に左右されない文化的価値の創造と保護を目指しました。
現代の課題と対応策
現代企業においても、規制や制約が強化される環境下では、サブカルチャーマーケティング、コミュニティ主導型ブランディング、文化的価値創造、クリエイティブレジスタンスなどの手法が重要な差別化戦略となります。メインストリームを避けた独自文化圏でのブランド構築、ファンコミュニティによる自発的なブランド価値創造、短期的な売上よりも長期的な社会的意義を重視した事業展開、制約を創造性のきっかけとして活用する発想転換などが現代的な応用例です。
江戸時代と現代の比較
蔦重の創造的対抗戦略と現代のブランド差別化手法は、規制に配慮しながらも本質的価値を伝える高度なコミュニケーション技術という点で共通しています。江戸時代の「文化を守る」という信念は、現代のパーパス経営やESG経営の考え方と本質的に同じです。異なるのは、現代では企業の社会的責任がより明確に求められ、ステークホルダーとの透明性のある対話が重要視されている点です。しかし、文化的価値と経済的価値を統合させることで持続可能な競争優位を構築するという戦略的思考は、時代を超えて変わらない重要な原則といえます。
3.第33話・34話から読み解く現代企業の危機管理とメディア戦略

第33話・34話を通じて見えるのは、危機時における官民の役割分担の重要性です。蔦重は民間の立場から柔軟で創造的な解決策を提案し、松平定信は公的権力による秩序回復を図りました。現代企業も、政府・自治体と適切に連携しながら、民間ならではの機動性と創造性を発揮することが求められています。平時から官民連携の枠組みを構築し、危機時には迅速な意思決定と柔軟な対応力を発揮し、利益追求だけでなく公益への貢献も重視する姿勢が重要です。
江戸時代と現代の情報環境比較
| 要素 | 江戸時代(読売) | 現代(SNS) | 戦略的意味 |
|---|---|---|---|
| 情報拡散速度 | 口コミによる段階的拡散 | 即座のバイラル拡散 | リアルタイム対応の必要性 |
| 情報の質 | 文字情報中心 | 動画・画像・音声の多様性 | マルチメディア戦略の重要性 |
| 受け手の態度 | 受動的な情報受容 | 能動的な情報検証・拡散 | 双方向コミュニケーションの必要性 |
| 影響力者 | 読売作者・茶屋主人等 | インフルエンサー・一般ユーザー | 多層的影響力ネットワークの活用 |
| 検証可能性 | 情報源の特定困難 | デジタル足跡による追跡可能 | 透明性・信頼性の確保が重要 |
メディア戦略の倫理的側面とSNS時代の課題
松平定信の「読売」戦略は効果的でしたが、現代の視点では情報操作的側面も含んでいます。SNS時代の企業は、効果的なメディア戦略と倫理的責任のバランスを取る必要があります。
現代企業が遵守すべき原則
- 透明性の確保:スポンサードコンテンツやPR活動の明確な表示
- 事実性の重視:データに基づく正確な情報発信と誇張の回避
- 多様性の尊重:一方的な価値観押し付けではなく多角的視点の提供
- 消費者主権の尊重:選択の自由を奪わない情報提供
- 長期的信頼関係:短期的な印象操作より持続可能な価値創造
- 社会的責任:情報発信が社会に与える影響への自覚と責任
文化的価値と経済的価値の統合
蔦重が「文化を守る」という信念を貫いたことは、現代のESG経営につながる考え方です。経済的成功と社会的・文化的価値の創造を両立させることで、持続可能な競争優位を構築できます。現代企業には、パーパス経営による企業の存在意義の明確化、短期的収益に直結しなくても長期的価値を生む文化的投資、企業活動が社会に与える影響の自覚と責任といった姿勢が求められています。
おわりに:江戸時代の知恵から学ぶ現代ビジネス戦略
第33話・34話で描かれた蔦屋重三郎と松平定信の対照的な戦略は、現代企業にとって貴重な教訓を提供しています。蔦重から学ぶ危機管理の本質
- 柔軟な資源代替戦略:固定的思考を超えた創造的解決策の提案
- コミュニティ重視:短期的利益よりも長期的信頼関係の構築
- 文化的価値の堅持:経済的困難でも譲れない価値観の維持
松平定信から学ぶSNS時代のメディア戦略
- 読売ネットワーク戦略:現代のインフルエンサーマーケティングの原型となる組織的情報発信
- 権威性とストーリーテリング:「吉宗公の孫」「柔術の達人」等の魅力的なブランディング手法
- 隠密による情報収集:現代のソーシャルリスニングに通じる市場監視システム
- 問題設定マーケティング:「田沼病」フレーミングに学ぶ競合との差別化戦略
- 倫理的配慮の必要性:情報操作の危険性とSNS時代の透明性要求
現代企業への統合的示唆
江戸時代の「読売」が現代のSNSと本質的に同じ機能を果たしていたことは、人間の情報処理や意思決定の仕組みが時代を超えて変わらないことを示しています。現代企業は、技術の進歩を活用しながらも、人間の本質的な特性を理解した戦略立案が重要です。
蔦重と定信の対比は、企業が直面する「効率性vs人間性」「短期成果vs長期価値」「統制vs創造性」といった永続的なジレンマを象徴しています。これらのバランスを取りながら、持続可能で社会的意義のある事業を展開することが、現代企業の使命といえるのではないでしょうか。
Tokyo Tokyo(東京おみやげプロジェクト)について
https://tokyotokyo.jp/ja/action/omiyage/
江戸時代から明治時代に使われていた「引札(宣伝用チラシ)」には、当時の日本の文化や暮らしが色濃く反映されています。私たちは、この歴史的に貴重な引札のデザインを現代に活かすため、東京都が進める「東京おみやげプロジェクト」に参画し、伝統的な日本の魅力が詰まった商品の開発と販売を行っています。
東京都と民間企業が共同で開発した伝統的な工芸品から文房具、食料品など、東京旅行の思い出をもっと楽しくするアイテム「東京おみやげ」のPR・販売拠点「# Tokyo Tokyo BASE」(羽田空港)で販売しています。
引札の魅力や現代の広告や商品開発に引札のエッセンスを取り入れたい方は、お気軽にご相談下さいませ。




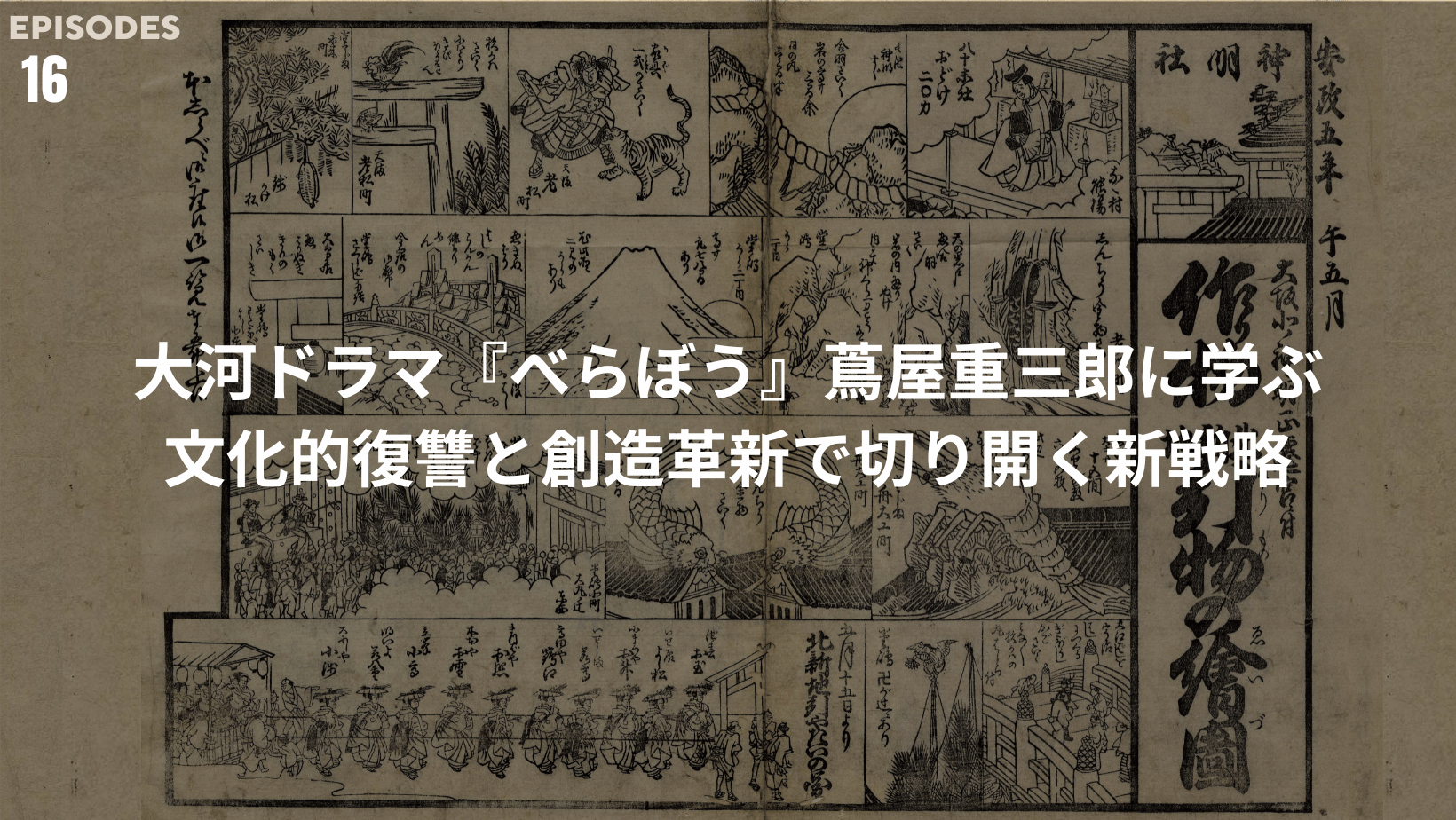
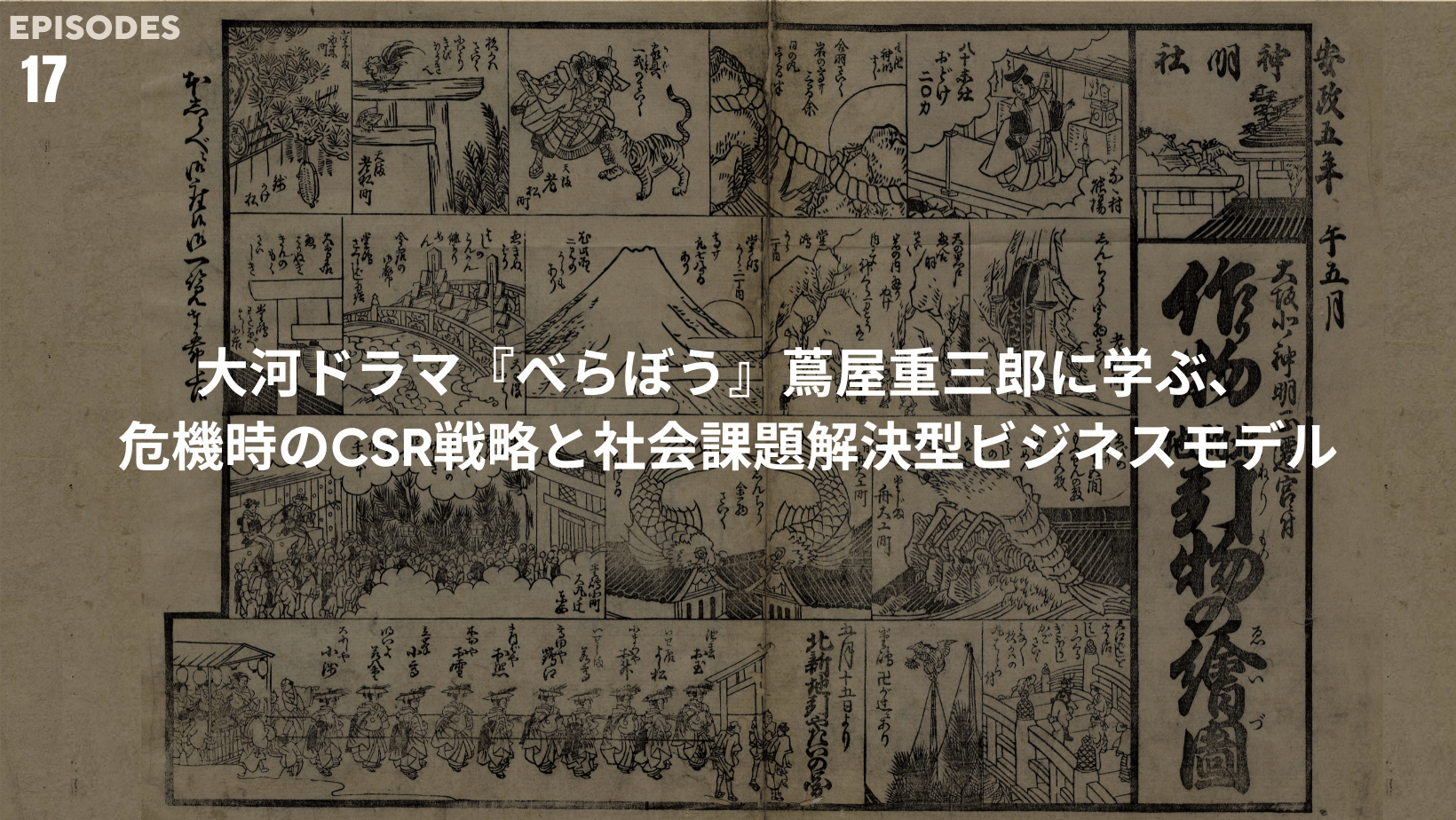
.png)