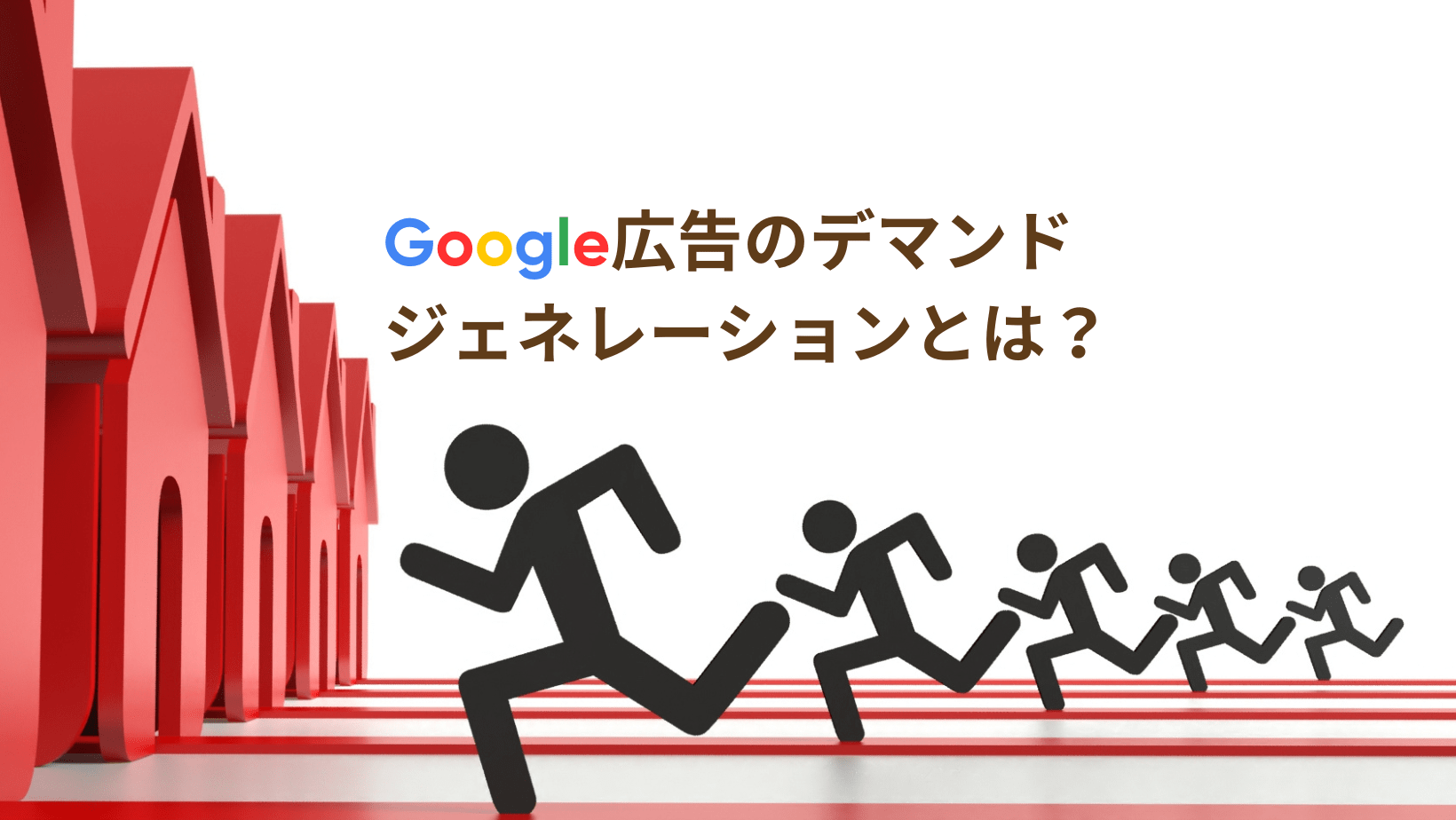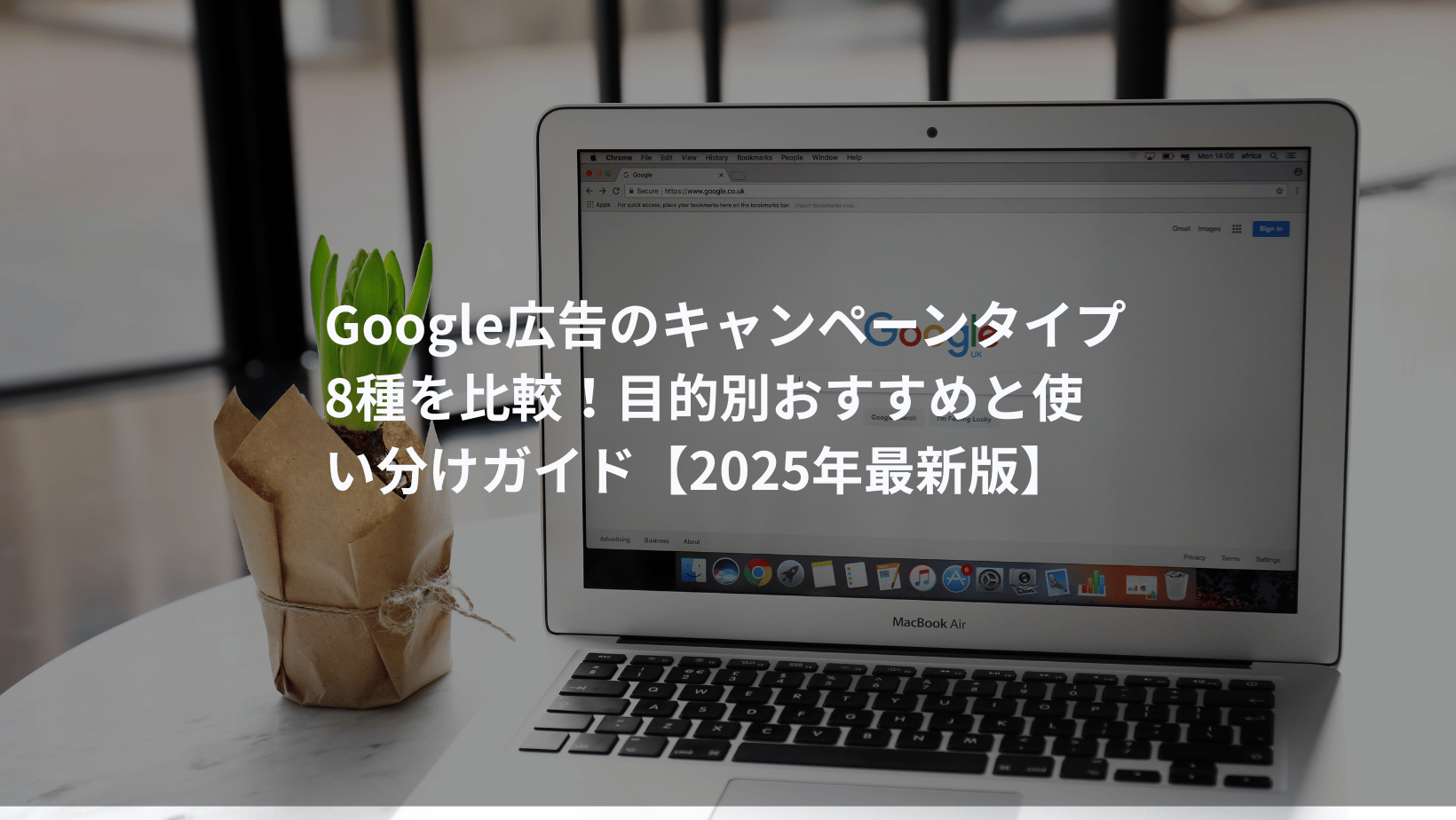ブランド認知を加速!デマンドジェネレーションキャンペーン(DGC)で広がる広告配信
〜Google広告が実現する、潜在層へのスマートなアプローチ〜
近年、ユーザーの情報接触行動が多様化する中で、「商品やブランドをまだ検索していない段階のユーザー」との接点づくりがますます重要になっています。
Googleが提供する「デマンドジェネレーションキャンペーン(DGC)」は、まさにそうした潜在層との出会いを設計するための広告手法として注目を集めてきました。
そして2025年3月、DGCはさらに進化を遂げました。これまでのYouTubeやDiscover、Gmailなどのフィード配信に加え、Googleディスプレイネットワーク(GDN)への対応が正式に開始されたのです。
このアップデートにより、広告主はより多様なユーザー接点を創出し、広範な認知や関心の獲得が可能になります。
本記事では、DGCの基本的な概要から、配信面拡大の背景、活用事例、クリエイティブ設計のポイント、そして導入時の実践的なアドバイスまでを、6つのブロックに分けて解説していきます。
デマンド ジェネレーションと Google ディスプレイ ネットワークの統合(Google広告ヘルプ)
https://support.google.com/google-ads/answer/15890515?hl=ja
- DGC(デマンドジェネレーションキャンペーン)とは?
- ディスプレイ面への配信拡大で何が変わる?
- 使用できるクリエイティブアセットと設計の考え方
- DGCの活用事例:業種別に見る成功パターン
- 成果を最大化する評価設計とKPIの考え方
- 今から始めるDGC活用のステップとアドバイス
- まとめ|DGCの進化で“発見起点”のブランド広告が加速する
1.DGC(デマンドジェネレーションキャンペーン)とは?
DGCは、Google広告における潜在層との出会いを設計するための広告手法です。検索広告やリマーケティングとは異なり、ユーザーが検索や比較行動を始める前段階で「発見」や「気づき」を与え、ブランドや商品の認知・興味喚起につなげます。
これまでの主な配信面は以下の通りでした。
-
YouTube ホームフィード
-
YouTube ショートフィード
-
Google Discover
-
Gmail(プロモーションタブ)
これらはすべて、視覚的・体験的なアプローチが可能なフィード型広告面です。特にZ世代やミレニアル世代との相性が良く、「スクロール中の偶発的な出会い」を演出しやすい設計となっています。
そして今回のGDN対応により、この広告がさらなる進化を遂げたのです。

2.ディスプレイ面への配信拡大で何が変わる?
2025年3月より、GoogleはDGCの配信対象にGoogleディスプレイネットワーク(GDN)を正式追加しました。
これにより、DGC広告は従来のフィード面に加え、以下のような広告枠にも表示可能になりました。
新たに追加された配信面:Googleディスプレイネットワーク(GDN)
今回のアップデートでは、DGCがGDN(Google Display Network)上のディスプレイ面にも対応することが明らかとなりました。これにより、従来のフィード中心のアプローチに加えて、以下のようなバナー広告面での接触も可能になります:
-
ニュースサイト、ブログ、ポータルなどの第三者メディア
-
アプリ内の広告面
-
Google提携メディアの広告枠
この拡張により、DGCの「興味関心フェーズ」への接触機会が大きく広がり、広告主のリーチと認知向上の可能性が飛躍的に増大します。
今回のアップデートの意義は極めて大きく、以下のような広告主メリットが考えられます。
| 観点 | 内容 |
| リーチの拡大 | 潜在層との接点が爆発的に広がる。 約350万以上のウェブサイト、アプリ、Google パートナーにまたがる広告面。より広範なリーチが可能。 |
| 生活文脈での発見性向上 | ユーザーが情報収集中に出会える機会が増加 |
| AI最適化の対象面拡張 | より多様な場で成果が出る配信構成が可能に |
なぜこの配信拡大が重要なのか?
1. ファネル上流へのアプローチがより強化される
DGCは「今すぐ顧客」ではなく、「これから顧客になる可能性のある層」へ向けた広告です。今回のGDN対応により、より広範囲での認知獲得・関心喚起が可能になります。
たとえば、新商品ローンチや新サービスの認知拡大において、ファネル上部(潜在層)へのタッチポイントが増えることは、施策全体の効果にも好影響を与えます。
2. AIによるクリエイティブ最適化との相乗効果
DGCでは、複数の画像・動画・テキスト素材を組み合わせ、Google AIが自動で最適なクリエイティブを生成して配信します。ディスプレイ面の追加によって、さまざまな配信環境でこの自動最適化が活きる場面が増え、広告効果の最大化が期待されます。
3. 一貫性のあるブランド体験が可能に
ユーザーが複数のGoogleプロパティにまたがって広告と接触する中で、DGCのフォーマットは比較的ブランドイメージをコントロールしやすい仕様です。今回の配信拡張により、ディスプレイ面でもブランディング軸で一貫性を保ちながらアプローチできる点は、従来のGDN単体運用とは異なる強みです。
3.使用できるクリエイティブアセットと設計の考え方
DGCで使用されるクリエイティブは、ブランド認知や感情喚起を促す構成が重視されます。以下のようなアセットを複数登録することで、GoogleのAIが最適な組み合わせを自動的に配信先に応じて生成します。
| アセット | 内容 |
| 画像 | JPG/PNG、1:1・1.91:1・4:5に対応。印象に残るビジュアルを。 |
| 動画 | 最大30秒。冒頭3秒で惹きつけるライフスタイル提案型が有効。 |
| 見出し・説明文 | 感情に訴えるコピーや共感を呼ぶフレーズが鍵。 |
| ロゴ・CTA | ブランド認知・信頼感を高める要素。 |
| カルーセル | Discover面などでは複数画像の横スライド表示も可能。 |
特にDGCは複数の素材をアップロードするだけで、GoogleのAIが配信先やオーディエンスに応じて自動的に最適な組み合わせを構築してくれるため、準備する側としては“素材の質とバリエーション”に集中すればOKという点も魅力です。
▼ 効果的なアセット設計のコツ
-
画像は「何の広告か」が一瞬でわかるように明快に
-
動画は冒頭3秒に“気づき”を与える演出を
-
テキストは「共感」「ベネフィット」「気になる言い回し」を意識
-
複数パターンを用意して、AIの最適化に委ねる
DGC×ディスプレイ活用の実務ポイント
素材設計は「視覚訴求×行動導線」を意識
ディスプレイ面での視認性・クリック率を高めるために、画像・動画・見出しの初動訴求力が鍵を握ります。「なにこれ?」「おもしろそう」と思わせる“発見”要素を素材に含めると効果的です。
運用成果は「クリック・コンバージョン」だけで見ない
DGCのKPIは、必ずしもコンバージョン至上主義ではありません。**エンゲージメント(動画再生率・スクロール率・セッション時間など)**も含めて評価し、ブランディング効果を中長期で見ていく視点が必要です。
他のキャンペーンとの役割分担を明確に
たとえば「DGC=需要喚起/P-MAX=獲得」といったように、キャンペーンごとの目的と評価指標を明確にしておくと、配信面が増えても混乱せず運用できます。
4.DGCの活用事例:業種別に見る成功パターン
① 化粧品ブランド|新商品の認知拡大と興味喚起に成功
■ 課題
新しいスキンケア商品の発売にあたり、ブランドの既存顧客だけでなく、まだ製品を知らない潜在層へのリーチが必要だった。
■ 実施内容
-
DGCでYouTubeフィード、Discover、Gmailに加え、ディスプレイネットワーク面にも広告配信
-
複数の動画・静止画・テキスト素材を組み合わせたクリエイティブ最適化を活用
-
「乾燥肌対策」「30代女性向け」といった関心軸でオーディエンスセグメントを設計
■ 成果
-
広告想起率が+20%以上改善
-
購買意向のあるトラフィックが増加し、商品ページへの訪問者数が2.5倍に
-
店頭キャンペーンとの相乗効果により、新商品が発売1ヶ月で初回出荷分を完売
② 大手自動車メーカー|Z世代へのブランド想起向上
■ 課題
若年層(特にZ世代)へのブランドの認知と、SUVモデルの興味喚起が不十分だった。
■ 実施内容
-
Z世代の行動パターンを踏まえ、YouTubeショート動画を中心にDGCを展開
-
「週末の冒険」「映えるドライブ体験」など、ライフスタイル提案型のビジュアルを制作
-
クリエイティブは複数フォーマットを用意し、AIが最適化
■ 成果
-
18〜24歳層のブランド検索ボリュームが前月比で1.8倍
-
広告接触層の中で、YouTube動画から自社公式サイトへの流入が顕著に増加
-
数か月後の展示会では、来場者の約3割が「ネットでこの車を見て気になった」と回答
③ D2Cアパレルブランド|低予算でも高いROIを達成
■ 課題
マーケティング予算が限られている中で、新規ユーザーへの認知・興味喚起を広く行いたかった。
■ 実施内容
-
DGCを利用し、DiscoverとGmail広告に集中配信
-
「春コーデ特集」などのシーズナリティを活かした画像バナーとショート動画を用意
-
配信ターゲットは「ファッション」「エシカル消費」「サステナブル」に関心がある層に絞り込み
■ 成果
-
1インプレッションあたりのエンゲージメント率が業界平均の2.3倍
-
SNSでのブランドメンションも増加し、広告経由での売上が前年比で約150%に上昇
-
「DGCのクリエイティブは、そのままSNS投稿にも転用できて便利」と運用担当者がコメント
【まとめ】
DGCは、ブランドや商品を“まだ知らないが関心を持ち得る人”に向けて、効果的に“気づき”を生み出す手段です。今回のディスプレイ面拡大により、接触機会と接触文脈がさらに多様化したことで、使い方次第であらゆる業種・規模の広告主にとって非常に有効な施策となり得ます。
5.成果を最大化する評価設計とKPIの考え方
DGCは“今すぐのコンバージョン”を目的にするキャンペーンではなく、中長期的な認知・興味・検索行動の変化をKPIに設定するのがポイントです。
| 評価項目 | 内容 |
| ブランドリフト | 「広告でブランドを知った」ユーザー割合の増加 |
| 検索リフト | 「広告接触後にブランド名を検索した人」の増加 |
| CTR・視聴完了率 | アセットの反応率を指標化 |
配信戦略と評価指標の設計
DGCは、いわゆる“刈り取り型”広告とは評価指標が異なります。クリック率や直接的なコンバージョンだけでなく、ブランドリフト・検索リフト・再訪問率など、認知→興味→行動のプロセスを重視した測定が重要です。
また、他のキャンペーン(例:P-MAXや標準ディスプレイ)と明確にファネル上の役割分担を設けることで、DGCの効果をより最大化できます。
6.今から始めるDGC活用のステップとアドバイス
DGCは、次のようなステップで取り組むとスムーズです:
-
目標設定とKPIの明確化(例:新商品の認知拡大、検索リフト)
-
アセットの準備(動画・画像・テキストを複数パターン用意)
-
オーディエンスシグナルの設計(興味・関心カテゴリを活用)
-
少額からテスト配信 → 最適化 → 拡張
社内に動画制作リソースがない場合でも、SNS用素材やPR用画像を流用しながら、最小限の負担で効果的な配信が可能です。
※DGCを使いこなすために今やるべきこと
① アセット設計にしっかり時間をかける
動画・静止画・テキストは単なる“素材”ではなく、「出会いの瞬間」を生む要素。ユーザー視点で“心が動く瞬間”を意識したクリエイティブを設計しましょう。
② ファネル設計と評価軸を整理する
獲得施策との関係性、認知から行動までの流れの中で、DGCの役割を位置づけてから導入すべきです。
③ 少額からでもトライ&エラーを繰り返す
GoogleのAIによる最適化が機能するにはある程度の配信データが必要です。最初は限られた予算でもテストを重ねてチューニングすることが効果最大化への近道です。
7.まとめ|DGCの進化で“発見起点”のブランド広告が加速する
デマンドジェネレーションキャンペーン(DGC)は、ユーザーの心に“ふとした気づき”を届ける、現代的な広告手法です。2025年3月からのGDN対応によって、その“気づき”の場はさらに広がり、潜在層への接触チャンスが格段に増しました。
「ブランド認知がなかなか進まない」「検索広告やSNSだけでは限界を感じる」──そんな課題をお持ちの広告主の方にとって、DGCは強力な一手となるでしょう。
株式会社evoliaでは、DGCの導入支援・クリエイティブ設計・配信戦略・効果分析までトータルでご支援しています。「うちの業種でも使える?」「何から始めればいい?」といったご相談も大歓迎です。
よくある質問(FAQ)
Q1. DGCはどのような業種に向いていますか?
A. DGCは、特に新商品の認知拡大やブランド訴求を重視する業種に向いています。化粧品、アパレル、自動車、食品、教育、不動産、旅行・観光など、意思決定前の興味喚起が重要な商材に有効です。
Q2. DGCとP-MAXはどう使い分ければよいですか?
A. DGCは潜在層への認知・関心喚起に強みがあり、P-MAXは顕在層への獲得施策に適しています。理想的には、DGCで関心を高めたユーザーを、P-MAXや検索広告でコンバージョンへつなげる「ファネル設計」が効果的です。
Q3. 少額の広告予算でもDGCは運用可能ですか?
A. はい、少額からでも十分にテスト可能です。初期は予算を抑えて配信し、結果を見ながらターゲティングやアセットの最適化を行うことで、効率的に効果を高めていけます。
Q4. GDNに配信されるようになったことで、何が変わったのですか?
A. 配信可能な広告枠が大幅に増えたため、ユーザーとの接点が増加し、より広範な認知獲得が可能になりました。従来のフィード配信に加え、ニュースサイトやアプリなど、日常の中での“偶発的な出会い”を演出できるようになりました。
Q5. DGCの成果はどのように測ればよいですか?
A. コンバージョン数だけでなく、ブランドリフト(想起率)、検索リフト(ブランド名の検索増加)、エンゲージメント(動画再生率やCTR)などを組み合わせて評価するのが一般的です。目的に応じた指標設計が成果最大化の鍵になります。