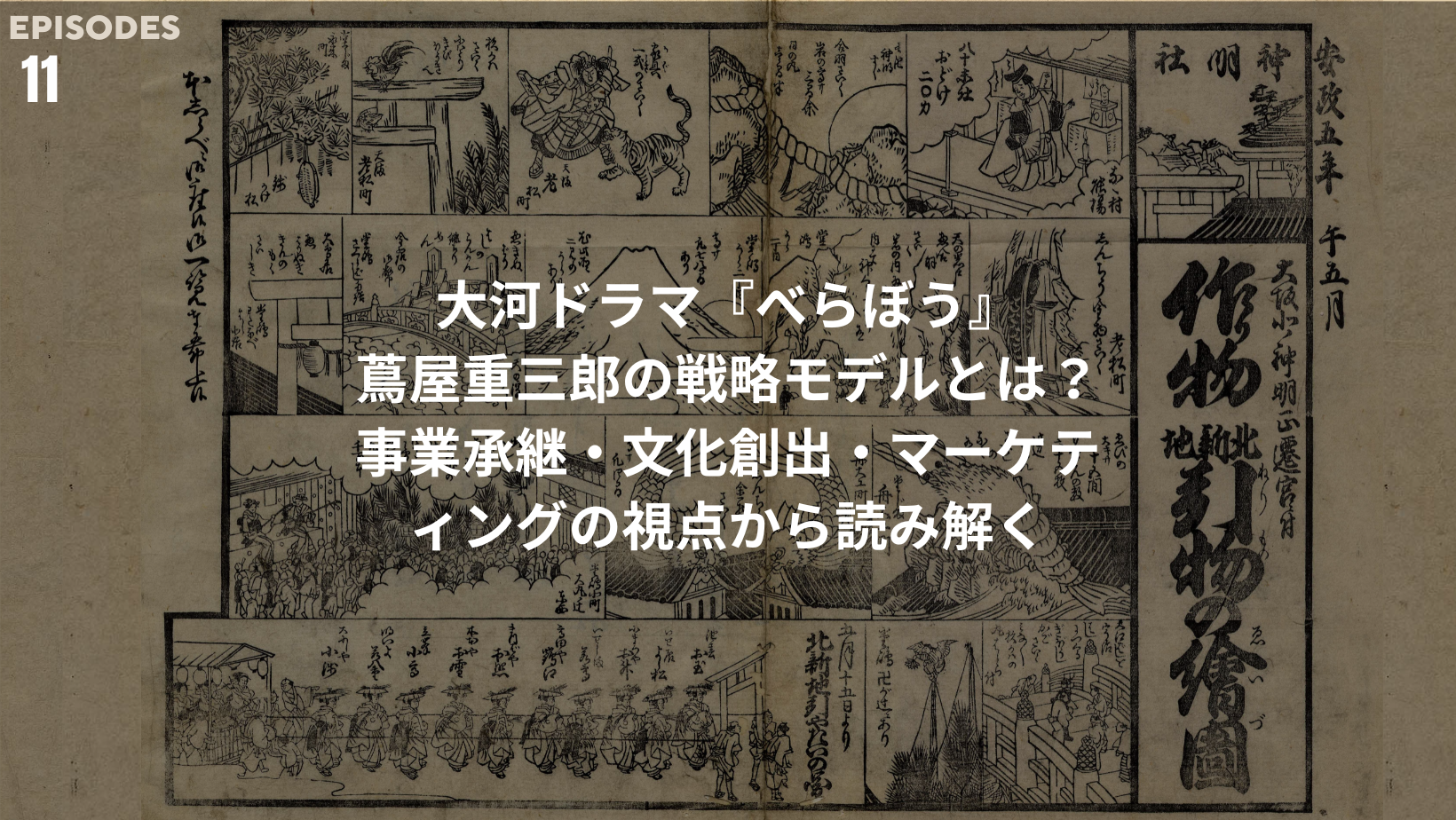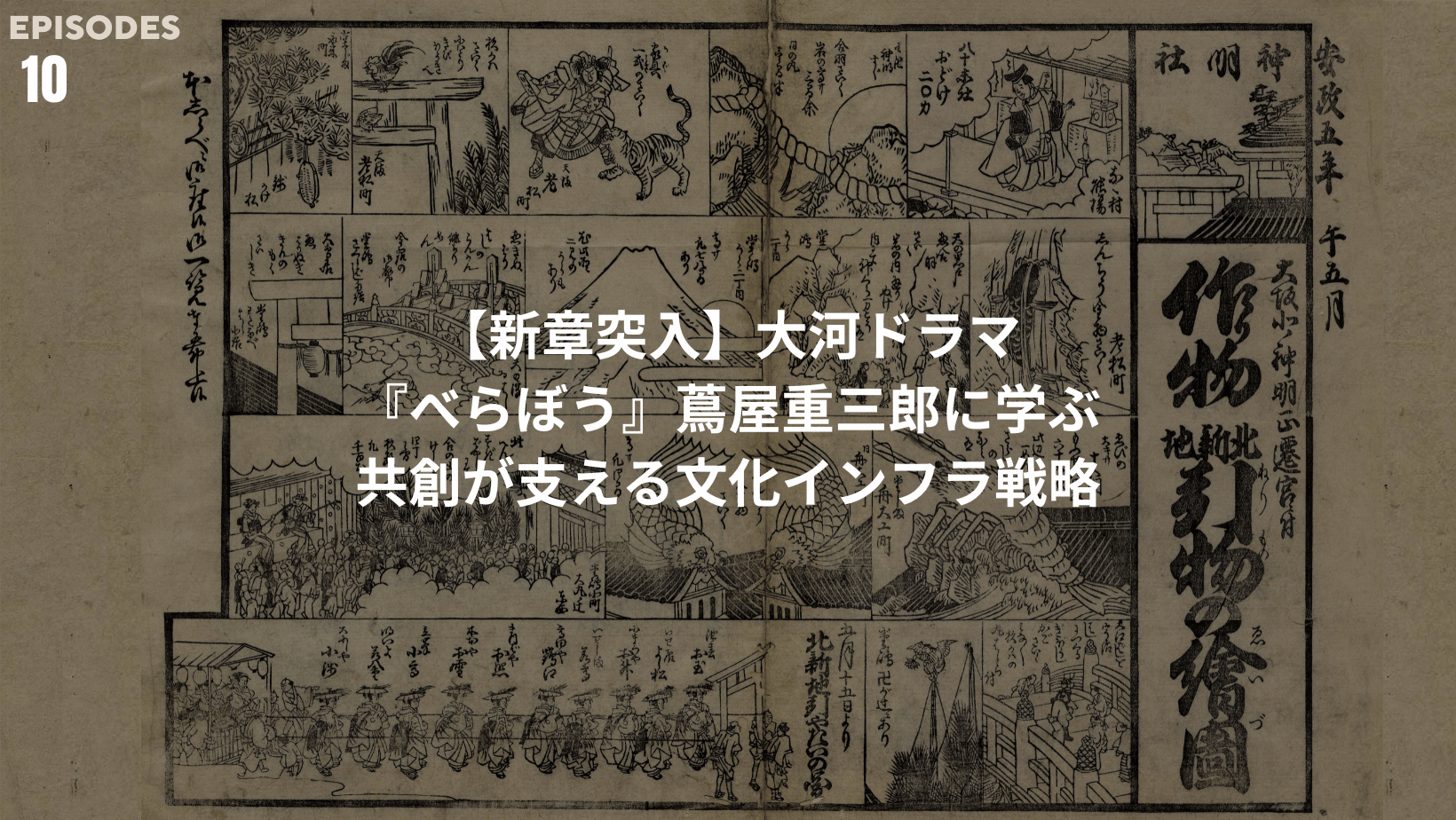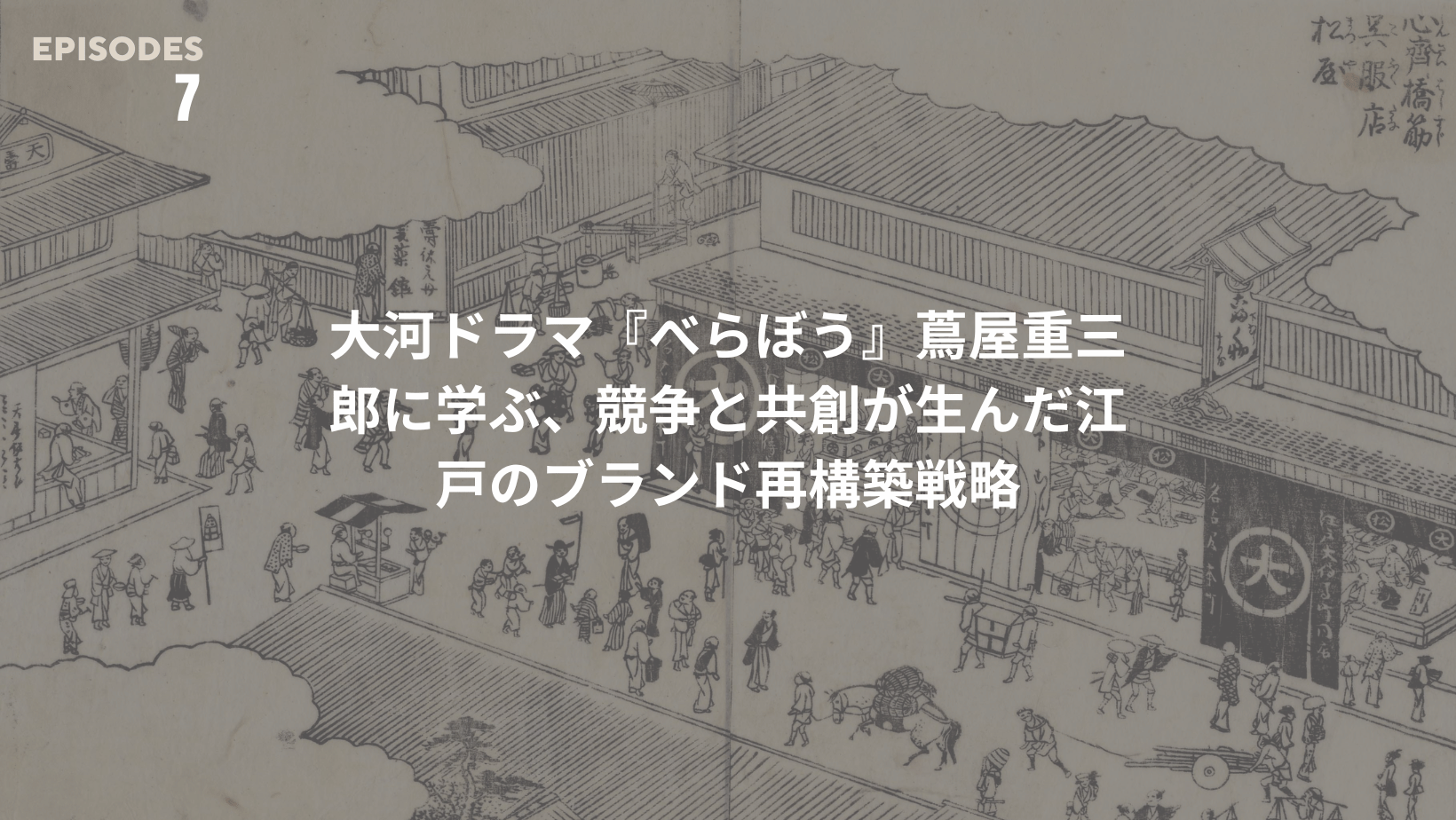大河ドラマ『べらぼう』蔦屋重三郎に学ぶ、江戸から続く創造と継承のビジネス戦略
NHK大河ドラマ『べらぼう』は、江戸時代の出版革命を牽引した蔦屋重三郎の人生を通して、現代にも通じる経営や文化戦略の本質を描き出してきました。
今回取り上げる第15話「死を呼ぶ手袋」、第16話「さらば源内、見立は蓬莱」では、蔦重が新たな出版拠点「耕書堂」を立ち上げ、仲間たちとともに出版再始動への道を切り開く一方、盟友・平賀源内が悲劇的な最期を遂げる過程が描かれます。
この2話を通して浮かび上がるのは、「場をつくり、人を巻き込む力」と「志を受け継ぎ、文化を未来へつなぐ覚悟」です。本記事では、この2話をもとに、現代ビジネスにも通じるエッセンスを「出版流通の再構築」と「信念と知の継承」という2つの軸で読み解きます。
ep.1 大河ドラマで注目が集まる蔦屋重三郎とは?引札で江戸時代の広告革命を牽引
ep.2 大河ドラマ『べらぼう』に見る蔦屋重三郎のマーケティング戦略と現代的教訓
ep.3 大河ドラマ『べらぼう』蔦屋重三郎から学ぶ江戸から令和の広告戦略とマーケティングの本質
ep.4 大河ドラマ『べらぼう』蔦屋重三郎から学ぶコンテンツとデータ活用のマーケティング術
ep.5 大河ドラマ『べらぼう』蔦屋重三郎から学ぶ5つのマーケティング手法
ep.6 大河ドラマ『べらぼう』に見る蔦屋重三郎のプロモーション戦略と江戸の集客方法
ep.7 大河ドラマ『べらぼう』蔦屋重三郎に学ぶ、競争と共創が生んだ江戸のブランド再構築戦略
ep.8 大河ドラマ『べらぼう』蔦屋重三郎に学ぶ、信頼と理念で組織を再構築する経営戦略

- 第15話「死を呼ぶ手袋」:出版ネットワークの再構築と共創モデルの始動
- 第16話「さらば源内、見立は蓬莱」:信念と知の継承によるブランド再構築戦略
- 第15話・16話から読み解く:創造と継承が拓く文化インフラ戦略
- おわりに

1.第15話「死を呼ぶ手袋」:出版ネットワークの再構築と共創モデルの始動
あらすじ
蔦屋重三郎は、瀬川との別れの痛みを抱えながらも、吉原五十間道に新たな書店「耕書堂」を開業。出版活動を再開し、「吉原をもっと楽しい街にする本を作りたい」という信念のもと、地本問屋の喜三二や絵師の政演などの仲間とともに「青本・洒落本・読本の作者求む!」と店先に掲げます。耕書堂は再び文化発信の拠点として動き出します。
一方、城内では将軍・徳川家治の嫡男・家基が鷹狩り中に急死し、田沼意次と松平武元の間に緊張が走ります。さらに「死を呼ぶ手袋」と呼ばれる謎の証拠品をめぐり、武元が死亡する事件が発生。政争と陰謀が交錯するなか、江戸の街に不穏な空気が漂い始めます。
江戸時代の課題と対応策
蔦重は、地本問屋という既存の出版流通網から外れた立場で再スタートを切りました。耕書堂は自身の名義で編集・制作・販売までを担う、独立型の出版体制を志向します。これは、吉原という地域を文化の街へと転換させる試みでもあり、蔦重にとっては単なる本屋ではなく「知と商いを結ぶ場」を築く挑戦でした。
現代の課題と対応策
今日のビジネス環境でも、プラットフォームへの依存リスクを避け、D2C(Direct to Consumer)やオウンドメディアによって独自のチャネルを構築する動きが活発です。個人やブランドが“自ら作り、自ら届ける”ことの価値が高まっており、蔦重の耕書堂モデルは、現代におけるブランドの自立・再構築の先例として参考になります。
2.共創型クリエイティブ体制と人的ネットワークの活用
江戸時代の課題と対応策
耕書堂の立ち上げに際して、蔦重は喜三二(企画)や政演(絵師)といった才能と結びつき、企画段階からの共創体制を築きます。蔦重は、出版を“モノを出す”だけでなく、“仲間と共に価値を生み出す”プロセスと捉えていました。耕書堂は、その象徴としての「場」でもあったのです。
現代の課題と対応策
現代のブランド開発や商品づくりも、共創(コ・クリエーション)の価値が高まっています。社内外のクリエイター、インフルエンサー、顧客とともにコンテンツやサービスを作る手法は、蔦重のネットワーク戦略と共通します。ファンベースを中心にしたブランド共創の姿勢は、蔦重の出版哲学に通じるものでしょう。
江戸時代と現代の比較
第15話は、「個の再出発」と「文化ネットワークの再構築」が軸になったエピソードでした。瀬川という支えを失いながらも、蔦重は“自分で場所をつくり、仲間と価値をつくる”という再出発を図ります。その姿は、現代におけるスタートアップの起業精神や、ブランドの自立と再構築の姿に重なります。
また、喜三二や政演といった顔ぶれと再び関係を築き直す姿は、人的ネットワークを再接続しながら共創の文化拠点を育てていくプロセスでもありました。これはまさに現代のコミュニティ型ブランド構築や、編集思考による場づくりとリンクします。
さらに、物語の背後では幕府中枢の政変と陰謀が展開されており、“文化の再起”と“権力の混迷”という2つの対比構造が本話の深層を形成しています。不確実な時代においてこそ、文化の力を信じて立ち上がる姿勢の重要性が浮き彫りになった回とも言えるでしょう。
2.第16話「さらば源内、見立は蓬莱」:信念と知の継承によるブランド再構築戦略
あらすじ
将軍世継・徳川家基の急死、松平武元の毒殺など、政権中枢が混迷するなか、田沼意次は平賀源内に「これ以上詮索するな」と警告を発します。しかし源内はその命に背き、真相を追おうとし、ついには精神的にも追い詰められていきます。
一方、蔦屋重三郎は源内を訪ね、新作の戯作執筆を依頼しますが、源内の言動には覇気がなく、もはや創作に向かう気力を失っているようにも見えました。そんな矢先、源内が殺人の罪で捕らえられるという報が入り、やがて彼は牢内で命を落とします。酔っていたという証言や、持っていたのが竹光だったことからも、冤罪の可能性は極めて高く、源内の最期は深い謎と無念に包まれたものでした。
源内の死を受け止めた蔦重や須原屋市兵衛、杉田玄白らは、彼の理念と魂を「本」というかたちで未来に残すことを誓います。「本を作ることで人の心は生き続ける」――蔦重はこの信念を胸に、耕書堂の出版活動に新たな意味を見出し始めます。
1. 信念の継承とコンテンツによる価値再構築
江戸時代の課題と対応策
源内の死は、蔦重にとって深い喪失体験でありながら、その死を“ただの悲劇”に終わらせないために、「本を作ることで志を継ぐ」という強い決意をもたらしました。本は単なる商品ではなく、想いや知をつなぐ“文化の器”であるという認識が、蔦重の出版観に新たな重みを与えました。
現代の課題と対応策
現代においても、理念を持った創業者や文化人の死が、ブランドや組織の価値観を再確認する契機になることがあります。Appleがスティーブ・ジョブズの精神を今もなおブランドに息づかせているように、蔦重のように“何を受け継ぎ、何を届けるか”という問いは、ブランド戦略の中核をなす視点です。
出版・コンテンツ制作においても、「誰の声を届けるか」「何を次代に残すか」が価値形成の鍵となっています。
2.創作者の支援とメディアの社会的責任
江戸時代の課題と対応策
精神的に追い詰められていく源内に対して、蔦重は創作依頼を通じて支えようとしましたが、結果として間に合いませんでした。源内を失ったあとも、その作品や思想を未来へ届けることこそが、自らに課せられた“出版者の責任”であると、蔦重は受け止めます。
現代の課題と対応策
現代のメディアや出版社、クリエイター支援の枠組みにおいても、「創作者の環境を守ること」と「創作物を社会とつなげる責任」は大きな課題です。たとえば、クリエイター支援のクラウドファンディングやアーカイブプロジェクト、記憶の継承を目的とした出版活動などは、まさに蔦重の姿勢と重なります。
江戸時代と現代の比較
第16話では、蔦重が直面したのは「大切な存在を失うことによって、自らの信念を問い直す」という局面でした。平賀源内という革新と知の象徴を失いながらも、その思いを“本”というかたちで後世へ残すという行動は、出版という営みの本質を突くものでした。
現代でも、クリエイティブ業界において“理念の継承”や“記録の使命”が重視される場面は数多く存在します。創業者の想い、クリエイターの思想、知識や文化の資産を可視化し、アーカイブして共有する営みは、蔦重の出版観と本質的に共通しています。
また、社会的な事件や冤罪の影が、表現者・思想家を消し去るという構造は、現代においても繰り返される課題です。だからこそ、蔦重のように“発信を止めない者”の存在が必要とされるのです。
3.第15話・16話から読み解く:創造と継承が拓く文化インフラ戦略
蔦屋重三郎が耕書堂を再始動させた第15話と、盟友・平賀源内の最期に直面する第16話は、蔦重の出版活動が“個の復活”を超えて、“文化の土台づくり”へと進化していく重要なターニングポイントとなりました。そこでは、「場」をつくる力、人と共に価値を生み出す共創、志を継ぐ覚悟、そして創作者と社会をつなぐ責任感といった、現代にも通じる本質的な視座が描かれています。
1. 文化の再出発において「場」を再設計できるか
江戸時代の戦略:
蔦重は失意の中で再起し、耕書堂という新しい出版の場を吉原に開設しました。それは単なる書肆ではなく、仲間と共に“文化の未来をつくる場”であり、知のインフラを再構築する拠点でもありました。場所の力を再定義し、自らが再び創造の中心に立つ姿勢は、戦略的な再起として機能しました。
現代の応用:
企業にとっても、「場」の再構築は再起の鍵です。オフィスを創造の場として再設計する動き、独自ブランドの拠点となるフラッグシップショップ、またはオウンドメディアや自社スタジオといった“発信基地”の整備は、蔦重の耕書堂設立と同様、自ら文化のハブになるための現代版インフラ戦略です。
2. 共創を文化創造の中核に据えられるか
江戸時代の戦略:
喜三二、政演といった仲間たちとの協働を通じて、蔦重は出版活動を“孤立した創作”ではなく“共に生み出す場”として確立しました。耕書堂は、編集・企画・創作を担う複数の人々の知が集う、ネットワーク型の文化機関として機能していたのです。
現代の応用:
現代のクリエイティブ領域では、インフルエンサーや外部クリエイターとの共創、ユーザー参加型コンテンツ、クラウドファンディングによる共創型出版などが一般的になりました。蔦重の取り組みは、ブランドが“誰と組むか”という視点で価値を高める戦略の原型といえます。
3. 志を失わずに「文化的継承者」として機能できるか
江戸時代の戦略:
盟友・平賀源内の非業の死を経て、蔦重はその喪失を“記憶”として残すのではなく、“志を継ぐ行動”へと変換しました。「本をつくり続けることで、源内を未来に残す」という信念は、出版者としての存在意義の再構築につながりました。
現代の応用:
現代でも、理念や哲学を継承しながら活動を続けることの重要性が高まっています。創業者の想いを引き継ぐ経営、故人の作品を守り育てるアーカイブ戦略、理念型ブランドの再編集といった取り組みは、蔦重が“文化の灯火を絶やさぬ者”として動いた姿勢に通じます。
4. クリエイターや思想家とどう共に立つか(社会的責任と文化の受容)
江戸時代の戦略:
精神的に追い詰められていた源内に対し、蔦重は新たな創作の機会を提供しようとしました。最期は叶わなかったものの、その死後、蔦重は“源内の想いを遺す責任”を出版者として引き受けました。
現代の応用:
現代においても、クリエイターの精神的ケアや活動支援は重要なテーマです。出版やメディアには“社会に伝える力”だけでなく、“社会の中で声を守る役割”も期待されており、蔦重の姿はメディアの社会的責任を象徴しています。創作者と並走する姿勢は、今の時代にこそ不可欠な文化的倫理といえるでしょう。
おわりに
『べらぼう』第15話・第16話では、蔦屋重三郎が耕書堂を起点に文化の再構築を試み、源内という“知の巨人”の死をきっかけに、出版の本質を再確認する姿が描かれました。
情報や言葉があふれる現代においても、「誰のために、どんな価値を残すのか」という蔦重の姿勢は、私たちの仕事や表現活動に深い示唆を与えてくれます。
創造する場、仲間との共創、信念の継承――。それらが複雑に絡み合いながらも、静かに力強く文化を未来へと送り届ける営みこそが、蔦屋重三郎の本質だったのです。
次回、第17話からは新章に突入します。文化を「どう継ぐか」から、「どう変えていくか」へ――蔦重の次なる挑戦に注目です。
引き続き、江戸の知恵と現代の実践をつなぎながら、『べらぼう』を通して未来に活きるヒントを探ってまいります。ぜひ、次回以降もご期待ください。
また、江戸時代の広告文化に興味を持った方は、ぜひ、引札についても興味を深めて頂ければと思います。
Tokyo Tokyo(東京おみやげプロジェクト)について
https://tokyotokyo.jp/ja/action/omiyage/
江戸時代から明治時代に使われていた「引札(宣伝用チラシ)」には、当時の日本の文化や暮らしが色濃く反映されています。私たちは、この歴史的に貴重な引札のデザインを現代に活かすため、東京都が進める「東京おみやげプロジェクト」に参画し、伝統的な日本の魅力が詰まった商品の開発と販売を行っています。
東京都と民間企業が共同で開発した伝統的な工芸品から文房具、食料品など、東京旅行の思い出をもっと楽しくするアイテム「東京おみやげ」のPR・販売拠点「# Tokyo Tokyo BASE」(羽田空港)で販売しています。
引札の魅力や現代の広告や商品開発に引札のエッセンスを取り入れたい方は、お気軽にご相談下さいませ。