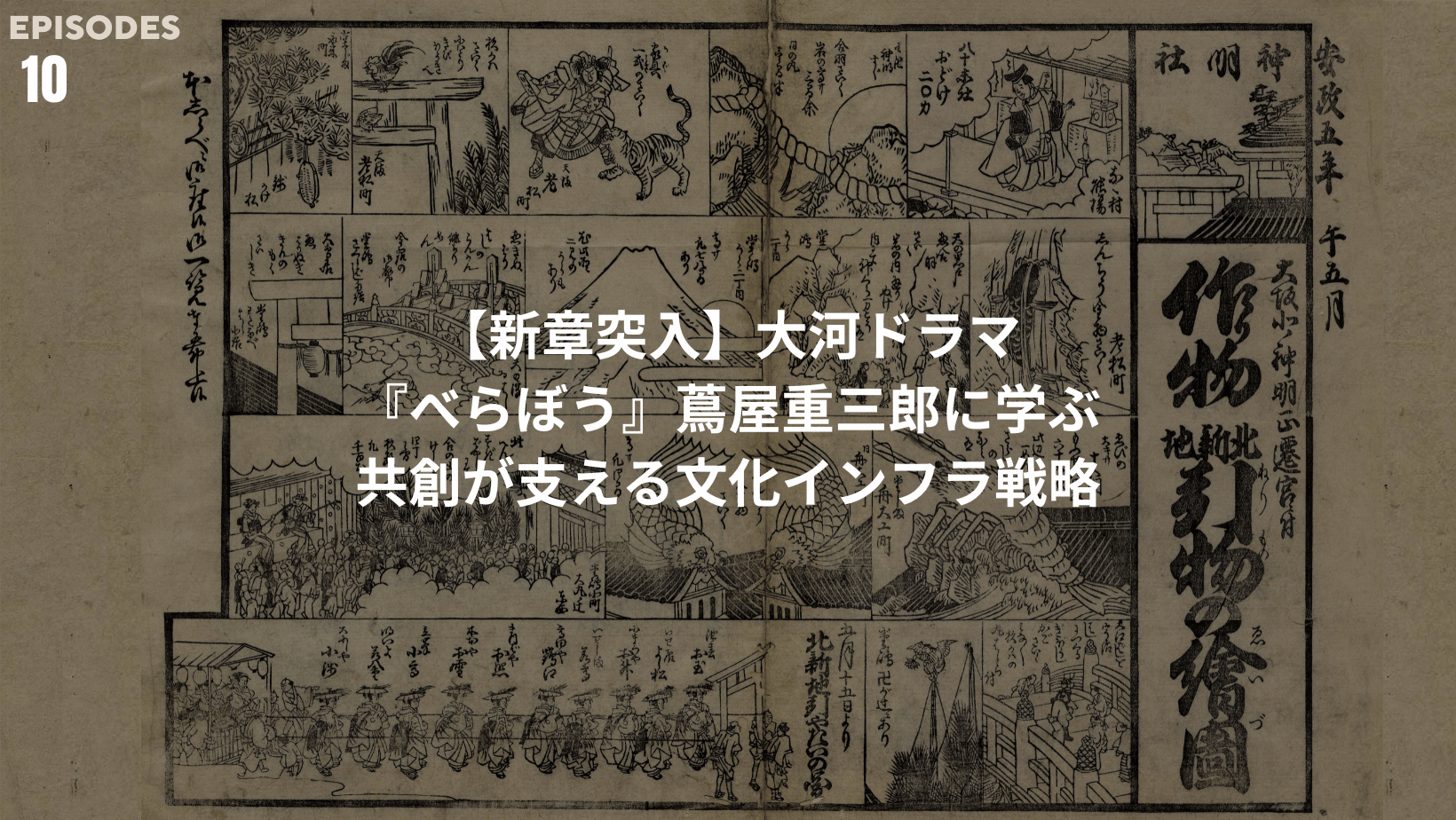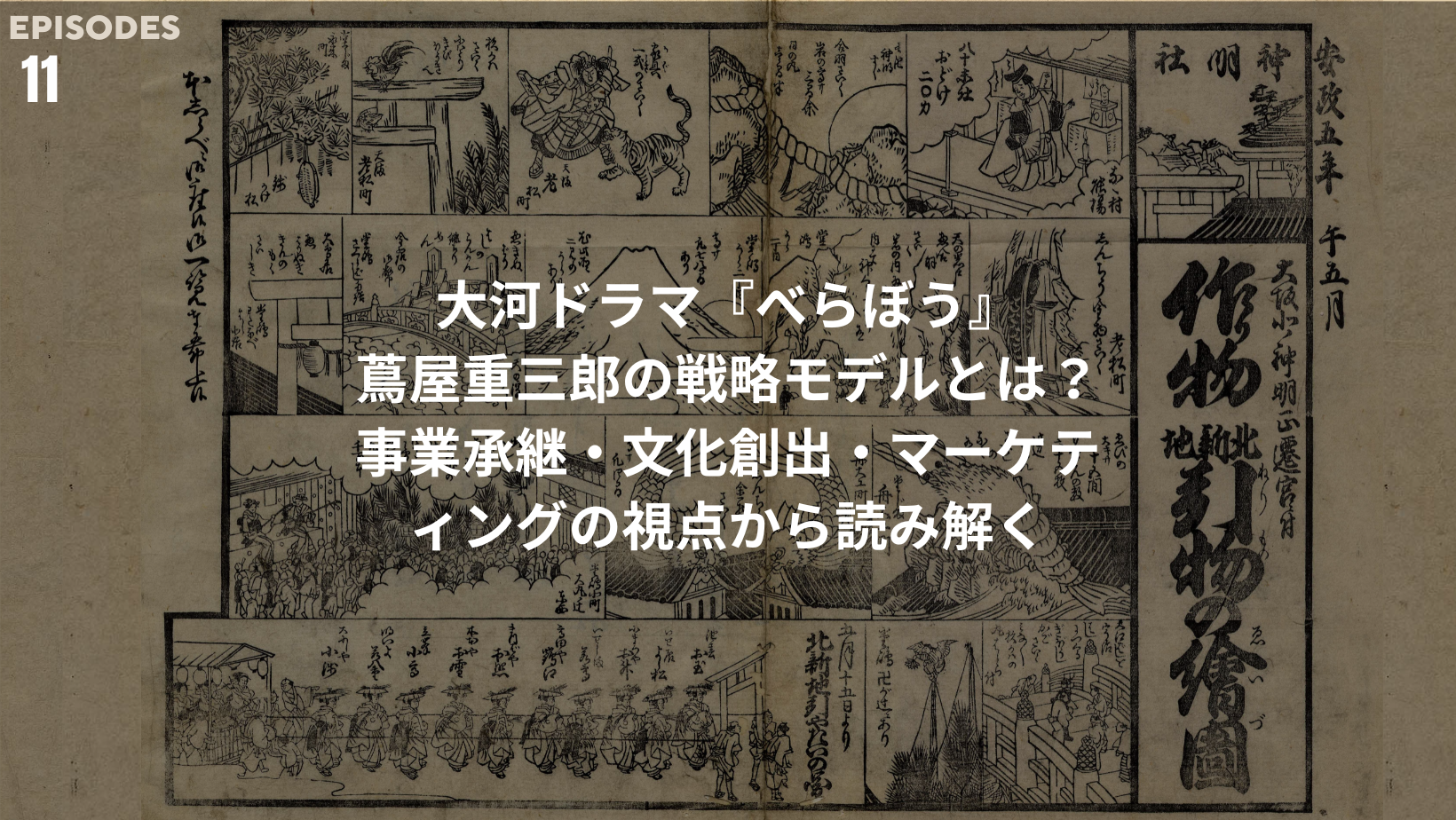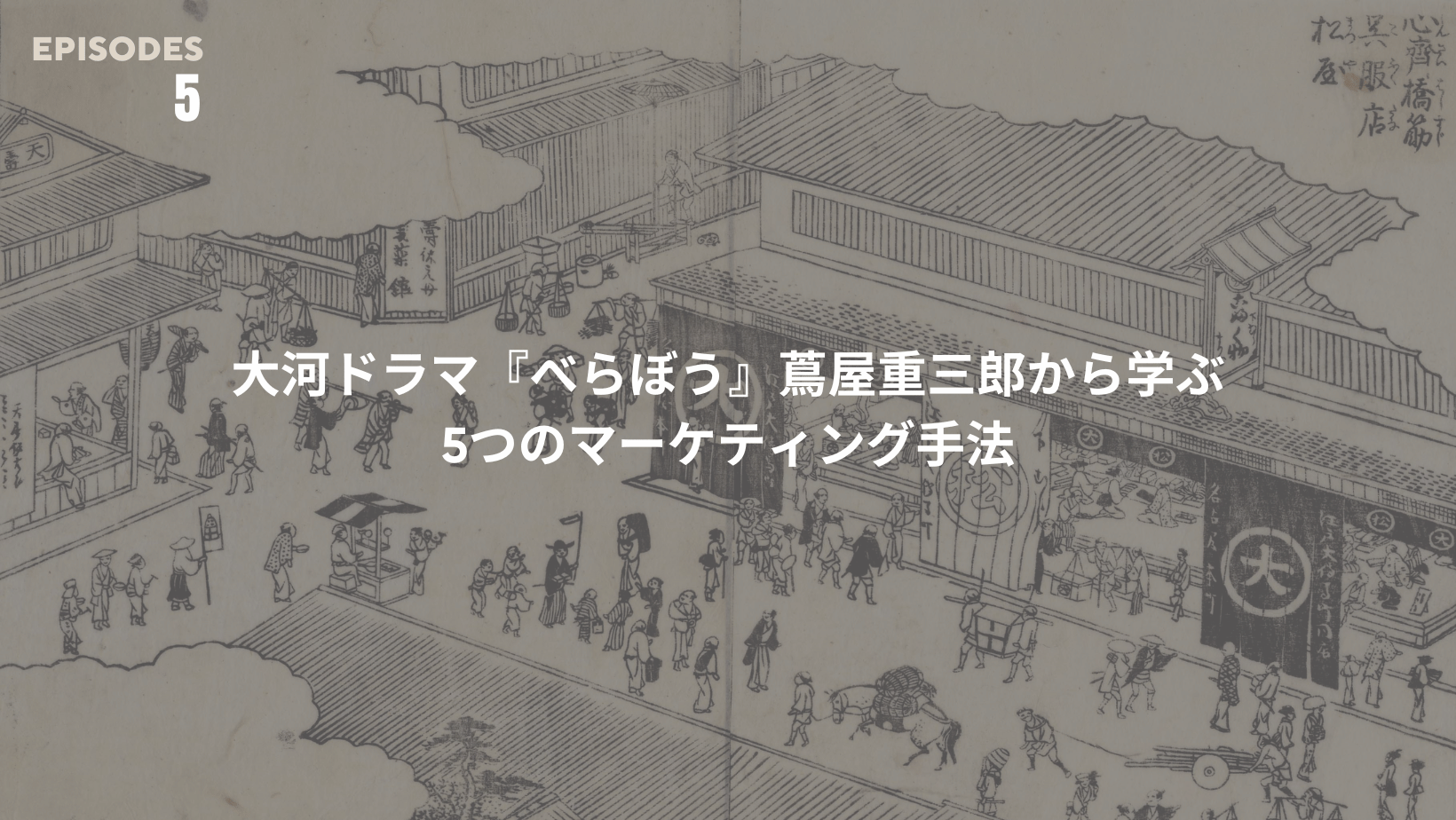大河ドラマ『べらぼう』蔦屋重三郎に学ぶ、信頼と理念で組織を再構築する経営戦略
2025年放送の大河ドラマ『べらぼう 〜蔦重栄華乃夢噺〜』では、江戸時代の出版文化を牽引した蔦屋重三郎の人生を通じて、商業や広告、そして経営における本質的な知恵が描かれています。回を重ねるごとに、蔦重の行動には単なる集客や販売戦略だけではなく、理念・信頼・組織といった「経営そのもの」に関わる深いテーマが現れてきました。
今回の第13話「お江戸揺るがす座頭金」と第14話「蔦重瀬川夫婦道中」では、蔦重が直面する信頼喪失とその再構築、組織やパートナーとの関係性を通じた理念の共有が中心に描かれます。ビジネスで言えば、レピュテーションリスク、ガバナンス、パーパス経営、エンゲージメントといった現代経営に直結する重要な要素が内包されています。
本記事では、これら2話から読み解ける現代ビジネスのヒントを、「江戸時代の課題と対応策」と「現代の課題と対応策」という対比の形で深掘りしていきます。
ep.1 大河ドラマで注目が集まる蔦屋重三郎とは?引札で江戸時代の広告革命を牽引
ep.2 大河ドラマ『べらぼう』に見る蔦屋重三郎のマーケティング戦略と現代的教訓
ep.3 大河ドラマ『べらぼう』蔦屋重三郎から学ぶ江戸から令和の広告戦略とマーケティングの本質
ep.4 大河ドラマ『べらぼう』蔦屋重三郎から学ぶコンテンツとデータ活用のマーケティング術
ep.5 大河ドラマ『べらぼう』蔦屋重三郎から学ぶ5つのマーケティング手法
ep.6 大河ドラマ『べらぼう』に見る蔦屋重三郎のプロモーション戦略と江戸の集客方法
ep.7 大河ドラマ『べらぼう』蔦屋重三郎に学ぶ、競争と共創が生んだ江戸のブランド再構築戦略
ep.8 大河ドラマ『べらぼう』蔦屋重三郎に学ぶ、信頼と理念で組織を再構築する経営戦略
.png?width=869&height=490&name=tsutaya08%20(1).png)
- 第13話「お江戸揺るがす座頭金」:構造問題への対峙とガバナンス再構築戦略
- 第14話「蔦重瀬川夫婦道中」:理念と価値観の共有による組織再生戦略
- 第13話・14話から読み解く:信頼・理念・関係性の再構築戦略
- おわりに
1.第13話「お江戸揺るがす座頭金」:構造問題への対峙とガバナンス再構築戦略

あらすじ
鱗形屋による偽板の販売が発覚し、座頭金をめぐる問題が江戸の経済構造全体を揺るがす事態に発展します。盲人の金貸し集団・当道座を率いる鳥山検校の強引な貸付が市井の人々を苦しめており、幕府もようやく本格的な調査と対策に乗り出すこととなります。
一方、鳥山と瀬川の関係にも緊張が走り、瀬川が蔦重への想いを口にしたことで鳥山は激怒。脇差を手に詰め寄りますが、瀬川はあくまで忠義を貫く姿勢を見せました。組織、個人、社会の信頼が交差する中、蔦重はなおも自らの信念を手放すことなく、周囲と向き合っていきます。
江戸時代の課題と対応策
座頭金という高利貸しの仕組みが市民生活を圧迫し、社会の信頼が揺らいでいた。蔦重は個人としてその被害を受ける形となりながらも、巻き込まれた瀬川を守るために前に出る誠実さを示し、信頼を再び築こうとした。
現代の課題と対応策
現代の企業も、不透明な取引や下請け搾取などが明るみに出た際、信頼の再構築が急務となる。その際、トップや関係者が誠実にリスクを引き受け、説明責任を果たすことがブランド再生の第一歩になる。
2.利益優先の仕組みがもたらす組織的腐敗と倫理の回復
江戸時代の課題と対応策
座頭金によって、民衆の家督が乗っ取られるという深刻な事態が発生。鳥山の影響力に陰りが見え始めたことを機に、田沼意次や徳川家治は「庶民を守る政治」として、倫理的視点から座頭金問題への取り締まりを断行しました。
現代の課題と対応策
企業の成長過程で、収益至上主義が倫理や持続可能性を犠牲にする場面は少なくありません。ESG経営やサステナビリティの観点が欠かせない今、経営者には社会的責任と判断力が問われています。
3. 関係性の歪みと心理的ロイヤルティの再構築
江戸時代の課題と対応策
鳥山の支配的な振る舞いに対し、瀬川は毅然と「忠義と愛情」を自らの選択で示しました。力ではなく信念に基づく姿勢が、人間関係を結び直す礎になっていました。
現代の課題と対応策
企業でも上下関係による支配構造が組織文化を歪めることがある。従業員が「どこに忠誠を置くのか」を問われる場面では、経営者側が価値観を明確に示し、心理的安全性を担保することが、健全な組織運営に直結する。組織において、信頼は命令や待遇だけで成立するものではなく、共通の価値観に基づく“感情的ロイヤルティ”によって築かれます。従業員の心を動かすのは、理念に共感できるかどうかにかかっています。
江戸時代と現代の比較
第13話では、偽板事件と座頭金をめぐる社会構造の歪みが露呈し、蔦屋重三郎を取り巻く信用と秩序が揺らいでいく様子が描かれました。座頭金によって市井の人々が生活を脅かされ、組織や家族が崩壊していく姿は、まさに経済と統治が密接に結びついた構造的課題への警鐘とも言える内容でした。
このような状況の中、蔦重は自身も巻き込まれながらも、理念を手放すことなく誠実に行動し、瀬川を守ろうとする姿勢を貫きます。これにより信頼の一部を回復し、再び前に進む糸口をつかみました。この展開は、現代において企業や経営者が不祥事や信頼失墜を経験した際に、いかに理念と真摯な姿勢を軸に立て直しを図るか、という経営判断と重なります。
また、鳥山検校や田沼意次、家治といった登場人物たちの対応からは、組織の倫理とガバナンスが問われたとき、どのように社会的責任を果たすかという現代の経営リーダーに通じる視点も浮かび上がってきます。
江戸も令和も、組織が信用を失い、制度が揺らいだときに求められるのは、「責任ある行動」と「本質に立ち返る姿勢」です。蔦屋重三郎の行動は、表層的な対応ではなく、“誠実さ・理念・共感”を再構築の軸に据えることの大切さを示しており、現代の経営におけるレピュテーションマネジメントの基本といえます。これは今日のリーダーシップやブランド再構築のあり方においても変わらぬ本質であり、信頼を失った組織や社会が再生するには、「誠実さ」と「本質への回帰」が何よりも重要であることを、本話は改めて教えてくれます。

あらすじ
幕府が座頭金を巡る不正蓄財の摘発に乗り出し、鳥山検校と瀬川が拘束されます。蔦屋重三郎もその場にいたことで誤解され拘束されますが、瀬川を庇ったことで釈放されます。鳥山は入牢、瀬川は松葉屋に預けられることとなります。蔦重は瀬川に「本屋を一緒にやらないか」と新たな未来を提案します。瀬川も次第に心を開いていきますが、過去の恨みによる襲撃を受けたことで、「自分の存在が重三郎の夢を壊す」と思い詰めます。年が明けて間もなく、瀬川は姿を消し、手紙だけを残して去っていきました。
1. 組織再生における価値観の共有と理念の再定義
江戸時代の課題と対応策
蔦重は「江戸を面白くする本を作る」という信念に立ち返り、それを瀬川と共有しようとしました。再出発には価値観のすり合わせが重要でした。
現代の課題と対応策
経営においても、変革期や再起動時に必要なのは「なぜ我々はこれをやるのか」を再定義し、共有すること。MVV(ミッション・ビジョン・バリュー)浸透による組織の一体化は、あらゆる変化対応の原動力となる。
2.過去の影と感情的負債への組織的配慮
江戸時代の課題と対応策
瀬川が襲撃された背景には、座頭金によって人生を狂わされた者の恨みがありました。鳥山の妻という立場は、知らず知らずのうちに他者の痛みに関わっていたのです。瀬川はその重みを受け止め、自ら身を引く選択をします。
現代の課題と対応策
企業が過去に与えた社会的・心理的影響が、従業員や顧客に“感情的負債”として残ることは少なくありません。そうした背景に配慮し、ヒューマンリスクを前提にしたコンプライアンス設計や心理的サポートが重要となります。
3.組織における「別れの設計」と継承
江戸時代の課題と対応策
瀬川は「夢の邪魔になりたくない」と姿を消し、重三郎に「夢を見続けてほしい」と託します。蔦重は喪失の痛みを抱えつつも、それを受け止めて前へ進む決意を固めました。
現代の課題と対応策
事業承継・チーム再編・離職などにおいても、関係性の終わりを“物語の一部”として捉えることが、次の価値創造へのきっかけとなります。退職や離脱を組織のストーリーの一部と捉え、アルムナイネットワークや卒業制度などで関係性を継続させる文化は、組織の柔軟性と持続性を支える基盤になります。
江戸時代と現代の比較
第14話では、座頭金事件の余波が瀬川にも及び、蔦屋重三郎も共犯と疑われる中で、二人の関係性と未来に焦点が当てられました。瀬川が松葉屋に預けられ、蔦重が再び「一緒に本屋をやろう」と誘いをかける場面には、信頼の再構築と理念の共有が描かれています。しかし、過去の痛みと他者からの憎しみを背負う瀬川は、自らの存在が蔦重の夢を妨げると感じ、静かに彼のもとを去ります。
このような別れは、単なる離脱ではなく、「相手の未来を思っての選択」として描かれており、組織における関係性の再定義や、感情的負債をどう処理するかという視点に通じます。組織再建において、理念を共有しようとする蔦重の姿勢は、現代で言うところのパーパス経営そのものであり、「共に歩む未来をどう描くか」が信頼の起点となることを示しています。
また、瀬川の決断は、組織にとっての“離脱”や“別れ”をどう設計するかという点にもつながります。現代の組織では、退職・異動・解散といった“終わり”を物語として捉え、いかに意味のある体験として整理できるかが、次の成長の糧となります。
江戸も令和も、組織における関係性や価値観の共有が揺らいだとき、求められるのは「誰と、何を信じて前に進むか」という本質的な問いです。蔦屋重三郎と瀬川の選択は、現代においても“人と組織が信念でつながることの難しさと尊さ”をあらためて私たちに問いかけてくれます。
3.第13話・第14話から読み解く:信頼・理念・関係性の再構築戦略
1.信頼を失ったとき、誠実さと理念で再起を図ることができるか
→ 江戸時代の蔦重も、現代の企業も「誠実な対話」と「理念の再確認」が信頼回復の基礎になる。
2.競争や対立を価値観の共創へと昇華できるか
→ 鳥山や親たちとの関係を乗り越えた蔦重のように、現代でも利害を超えて目的を共有する姿勢が求められる。
3.理念を再定義し、仲間と共有できる言葉を持てるか
→ パーパスを言語化し、組織のあらゆる判断基準に落とし込むことが、今後の経営には不可欠。
4.別れ・退場を“物語”として組織に組み込めるか
→ 瀬川の離脱のように、別れを否定せず、関係の再設計として活かす発想が、組織の成熟に繋がる。
1. 信頼を失ったとき、誠実さと理念で再起を図ることができるか
江戸時代の戦略:
偽板事件や座頭金問題の余波で、蔦屋重三郎は出版業界や吉原の親たちとの関係性、そして社会的な信用を大きく損なうことになりました。そんななかでも蔦重は逃げず、瀬川や関係者と真正面から向き合い、自らの出版理念を語り続けることで信頼を少しずつ取り戻していきました。誠実に責任を引き受ける姿勢と、変わらぬ信念こそが、再起の原動力となったのです。
現代の応用:
現代においても、ブランドが炎上や不祥事で信頼を失ったときに問われるのは、情報開示の早さや謝罪の巧みさではなく、「理念に基づいた行動があるかどうか」です。企業やリーダーが短期的損得よりも長期的信頼を重視し、誠実なコミュニケーションを通じて立て直す姿勢は、レピュテーションマネジメントの中核を成します。
2. 競争や対立を「価値観の共創」へと昇華できるか
江戸時代の戦略:
鱗形屋や鳥山検校といった、これまで敵対関係にあった存在と蔦重は、真正面から対立するのではなく、時に理念を共有しながら共存の道を探ろうとしました。特に吉原の親たちや午之助との関係性では、過去のわだかまりを乗り越え、再び協働する姿勢が見られました。
現代の応用:
ビジネスの現場でも、競合他社や利害の異なるパートナーとの“対立”は避けがたいものです。しかし現代では「コーペティション(競争と協調の両立)」という考え方が広がっており、価値観や社会的目的を共有することで、競争相手とも共創できる環境が整いつつあります。蔦重のように、対話と共感をベースにした価値創出が鍵となります。
3. 理念を再定義し、仲間と共有できる言葉を持てるか
江戸時代の戦略:
蔦屋重三郎は、苦境の中でも「江戸を面白くする本をつくる」という出版理念を手放すことはありませんでした。そして、松葉屋に預けられた瀬川に「一緒に本屋をやらないか」と語りかけたように、その理念を“言葉”として再確認し、共有することで仲間を再び惹きつけていきました。
現代の応用:
現在では、MVV(Mission・Vision・Value)という形で、企業理念を言語化し、組織内で共有することが不可欠とされています。とくに変革期には「なぜこの事業をやっているのか」という問いに答える必要があり、理念が従業員の行動基準や意思決定の軸となります。蔦重の姿勢は、現代のパーパス経営の源流とも言えるでしょう。
4. 別れ・退場を“物語”として組織に組み込めるか
江戸時代の戦略:
最終的に瀬川は、蔦重の夢の邪魔になりたくないという想いから、手紙を残して彼のもとを離れました。この別れは決して絶縁ではなく、「想いを引き継いで前に進んでほしい」という情緒的で意味のある離脱として描かれています。蔦重もその想いを受け止め、新たな決意を胸に前へ進みます。
現代の応用:
現代のビジネスにおいても、離職・退任・解散といった“終わりのシーン”をどう設計するかが、次の創造の起点になります。企業が卒業生ネットワークを重視したり、退職者と良好な関係を保つ“アルムナイ施策”を展開するのはその一例です。関係性の終わりを“物語の一部”として捉える文化は、組織のしなやかさと信頼性を高める要素になります。
おわりに
これまで『べらぼう』を通じて読み解いてきたのは、蔦屋重三郎のマーケティング的視点――すなわち、ブランドの価値を高める工夫や、人を惹きつける仕掛けづくりでした。しかし、第13話・14話で描かれたのは、それらの“手法”を支える根幹――経営における「信頼」「理念」「関係性」の本質でした。
蔦重は、座頭金問題によって社会全体の信頼が揺らぐなか、外的要因ではなく、自らの行動と言葉によって信頼を取り戻そうとします。仲間や顧客と再びつながるために、理念を再定義し、価値観を共有する。そして、別れや痛みも“物語”の一部として受け入れ、新たな一歩へと踏み出します。
これは、現代の経営においてもまったく同じです。マーケティング戦略やプロモーション施策が効果を生むのは、企業の根本に「何を信じ、どうありたいか」という軸があるからこそです。
組織が信頼を失ったとき、理念を語れなくなったとき、人とのつながりが形骸化したとき――ブランドの力も、事業の成長も、すべてが脆くなります。
だからこそ、経営の本質は“数値”ではなく、“関係性と共感”にある。江戸時代の蔦重の姿勢は、それを私たちに静かに教えてくれます。
マーケティングを支える土台としての「経営のあり方」。
その重要性に気づかせてくれた13話・14話は、まさにこれまでの連載のターニングポイントとも言える回でした。
次回もまた、蔦屋重三郎の足跡をたどりながら、ビジネスの本質に迫る視点でお届けしてまいります。引き続き、ご期待ください。
また、江戸時代の広告文化に興味を持った方は、ぜひ、引札についても興味を深めて頂ければと思います。
Tokyo Tokyo(東京おみやげプロジェクト)について
https://tokyotokyo.jp/ja/action/omiyage/
江戸時代から明治時代に使われていた「引札(宣伝用チラシ)」には、当時の日本の文化や暮らしが色濃く反映されています。私たちは、この歴史的に貴重な引札のデザインを現代に活かすため、東京都が進める「東京おみやげプロジェクト」に参画し、伝統的な日本の魅力が詰まった商品の開発と販売を行っています。
東京都と民間企業が共同で開発した伝統的な工芸品から文房具、食料品など、東京旅行の思い出をもっと楽しくするアイテム「東京おみやげ」のPR・販売拠点「# Tokyo Tokyo BASE」(羽田空港)で販売しています。
引札の魅力や現代の広告や商品開発に引札のエッセンスを取り入れたい方は、お気軽にご相談下さいませ。