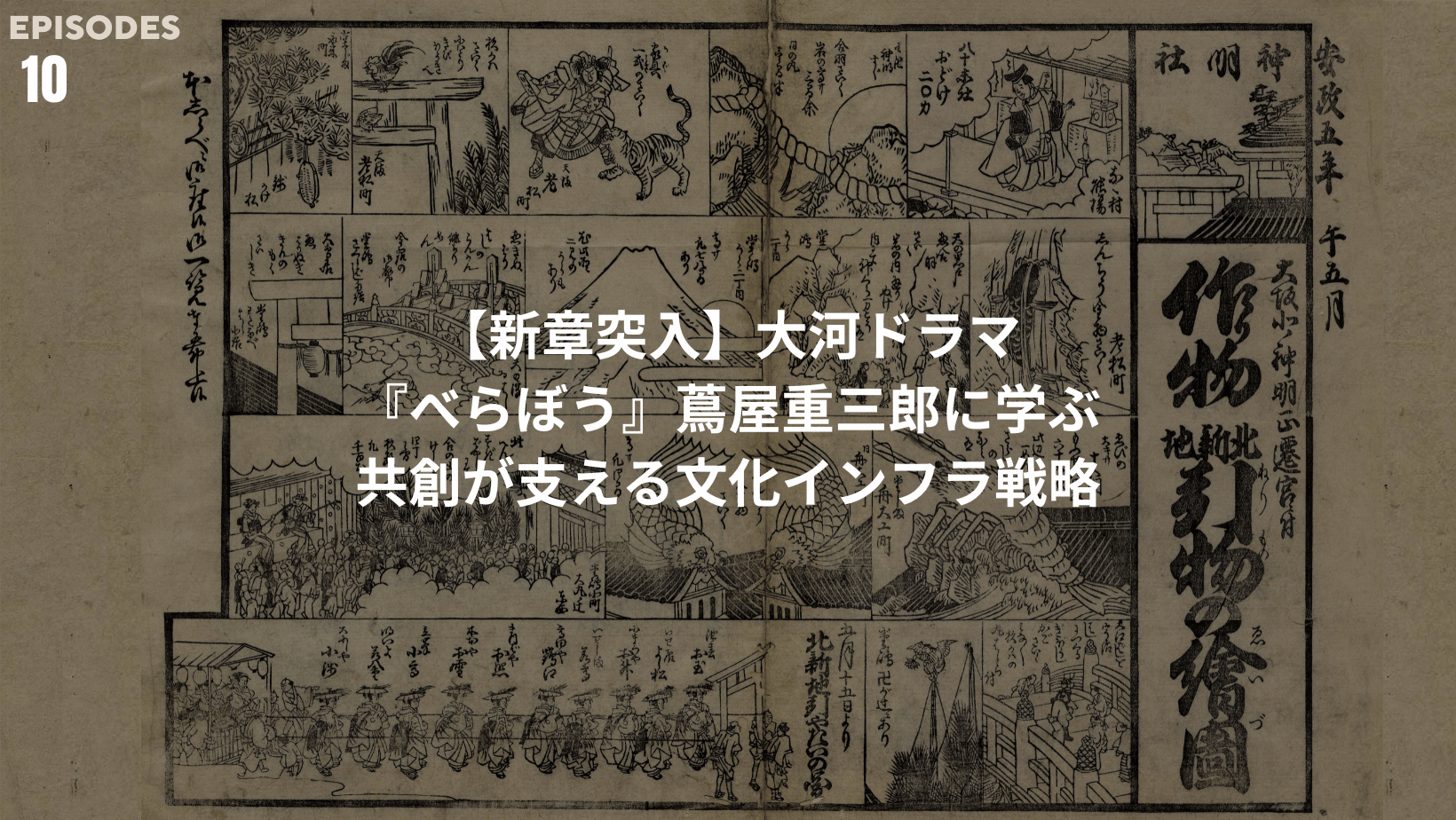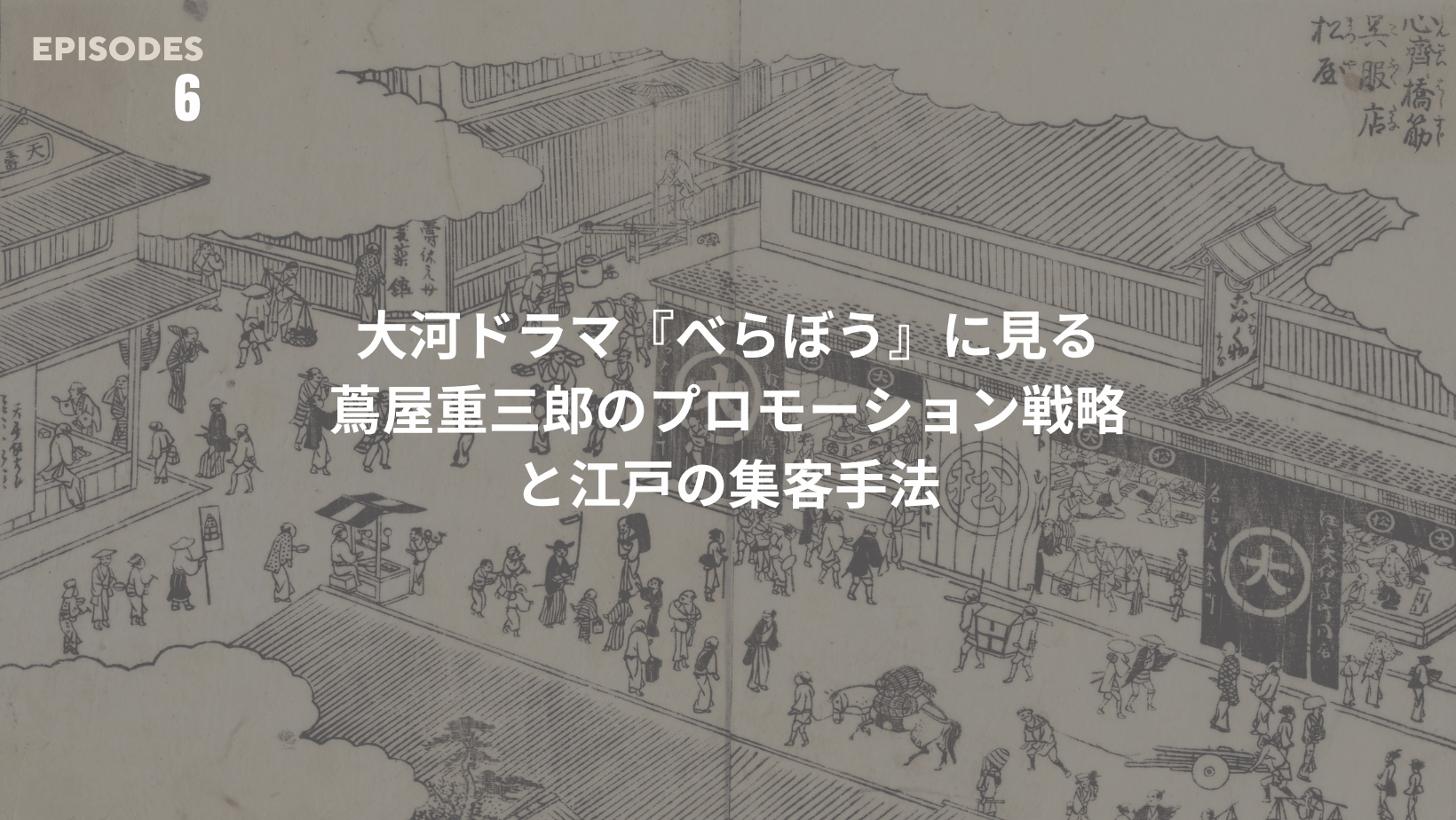大河ドラマ『べらぼう』蔦屋重三郎に学ぶ、競争と共創が生んだ江戸のブランド再構築戦略
2025年放送の大河ドラマ『べらぼう 〜蔦重栄華乃夢噺〜』は、江戸時代の出版文化を牽引した蔦屋重三郎の人生を描きながら、商業や広告の変遷、そして時代の変わり目に求められるビジネスセンスを見事に映し出しています。回を重ねるごとに、その知恵と行動力には現代のマーケティングにも通じる本質的な学びがあります。
今回の第11話・第12話では、吉原再興を掲げる蔦重が「競争」と「共創」のバランスを取りながら、祭りという文化イベントを通じてブランドを再構築していく姿が描かれました。ライバルの存在を否定せず、地域の人々や文化資源と手を取り合う姿勢は、まさに現代の企業が直面する「共感を軸にしたブランド戦略」に重なります。
この記事では、吉原の祭りを舞台に繰り広げられる蔦屋重三郎の取り組みを、現代のビジネス視点から読み解きながら、「競争が生む価値」「共創の力」「文化資源の活用」「記録による価値継承」などのテーマで整理していきます。
ep.1 大河ドラマで注目が集まる蔦屋重三郎とは?引札で江戸時代の広告革命を牽引
ep.2 大河ドラマ『べらぼう』に見る蔦屋重三郎のマーケティング戦略と現代的教訓
ep.3 大河ドラマ『べらぼう』蔦屋重三郎から学ぶ江戸から令和の広告戦略とマーケティングの本質
ep.4 大河ドラマ『べらぼう』蔦屋重三郎から学ぶコンテンツとデータ活用のマーケティング術
ep.5 大河ドラマ『べらぼう』蔦屋重三郎から学ぶ5つのマーケティング手法
ep.6 大河ドラマ『べらぼう』に見る蔦屋重三郎のプロモーション戦略と江戸の集客方法
ep.7 大河ドラマ『べらぼう』蔦屋重三郎に学ぶ、競争と共創が生んだ江戸のブランド再構築戦略
ep.8 大河ドラマ『べらぼう』蔦屋重三郎に学ぶ、信頼と理念で組織を再構築する経営戦略

1.第11話「富本、仁義の馬面」:文化と共創によるブランド再起戦略

あらすじ
蔦重が新たに制作した『吉原細見』は、親たちから拒絶されてしまい、さらに高価な錦絵本『青楼美人合姿鏡』も売れ残るという窮地に陥ります。信頼を失いかけた蔦重に対し、吉原の親たちは「祭りを開け」と命じます。そこで蔦重は、人気の浄瑠璃太夫・富本午之助を招き、祭りを盛り上げようと奔走。かつて吉原で受けた屈辱から出演を拒んだ午之助でしたが、蔦重や女郎たちの真心に動かされ出演を決意。最終的には鳥山検校の後押しで、「富本豊前太夫」の襲名と、蔦重の正本出版が実現します。この一連の流れは、文化資源を活用した共創型のプロモーションとして、現代のマーケティングに通じるエッセンスが随所に見られます。
江戸時代の課題と対応策
吉原の再興を図るため、蔦重は「富本節」という当時の大衆芸能を祭りに組み込むことを決断します。人気太夫・富本午之助の起用により、文化的価値と話題性の両方を兼ね備えた祭りを企画し、吉原の格式回復を図ったのです。さらに、彼の語りを記録した正本を出版することで、一過性のイベントを長期的なブランディング資産に転換しました。
現代の課題と対応策
現在でも、地域や企業が文化的コンテンツやIP(知的財産)を活用してブランドを再構築する例は多く見られます。たとえば、伝統芸能やご当地キャラを観光資源として活かす地方自治体、またはアーティストとコラボする高級ブランドなどがそれに当たります。蔦重のように、「物語性のある文化資産」を通じて独自の魅力を発信することは、今なお有効な戦略といえるでしょう。
2.共創型プロモーションと感情訴求の戦略
江戸時代の課題と対応策
午之助の出演を実現するために、蔦重は女将のりつや義兄の次郎兵衛、さらには花魁や振袖新造たちと協力し、もてなしの場を演出しました。とりわけ、女郎たちの涙ながらの懇願は、彼の心を動かす最大の要因となりました。このように、祭りの実現は蔦重一人ではなく、関係者との“共創”によって成し遂げられたものでした。
現代の課題と対応策
企業と顧客、あるいは社内外のステークホルダーが共に価値を創り出す「共創型マーケティング」は、近年注目を集める手法です。たとえば、ユーザー投稿型のキャンペーン(UGC)や、社員・ファンを巻き込んだブランディングプロジェクトは、まさにこの精神に則った取り組みです。蔦重の施策もまた、関係者の感情を動かしながらプロジェクトを成功へと導いた共創の好例です。
3. イベント起点のブランド再起と信頼回復
江戸時代の課題と対応策
出版物の失敗や親たちの不信により、蔦重の事業は一時的に信用を失います。しかし彼は、吉原祭りという大規模イベントを成功させることで、再び人々の関心と信頼を取り戻します。イベントは、吉原の華やかさを再び示し、集客とともにブランドの再評価をもたらしました。
現代の課題と対応策
現代でも、ブランドイメージの回復や再注目を狙ってイベントを活用する例は少なくありません。たとえば、企業不祥事のあとに行われるCSRイベント、あるいはリブランディング発表会などは、社会との関係を再構築する場として機能します。蔦重のように、「人が集まる場」を通じてブランドの信頼性を取り戻す戦略は、今も有効です。
4. ネーミング戦略と象徴性の設計
江戸時代の課題と対応策
祭りにおいて蔦重が実現した「富本豊前太夫」という名跡襲名は、ブランドに象徴的価値を与えるものでした。午之助の名前が変わることで、吉原祭り自体に「文化の頂点」というイメージが付与され、イベントが一層格式高いものとなりました。
現代の課題と対応策
ブランドの命名やロゴ変更は、企業イメージを刷新・強化するための有効な手段です。たとえば、Facebookが「Meta」に改称したように、ネーミングは企業や商品に「未来」や「革新」の象徴性を持たせる装置となります。蔦重の名跡襲名の演出も、こうしたネーミングによる象徴戦略と同様の意図があったと考えられます。
江戸時代と現代の比較
吉原の再起を目指す蔦屋重三郎の戦略には、現代のブランディングやコンテンツマーケティングにも通じる本質的な考え方が見て取れます。たとえば、文化資源である「富本節」の活用や、名跡「豊前太夫」の襲名によってイベントに格式と話題性を加える施策は、今日の企業が伝統芸能やアートとのコラボレーションでブランド価値を高める手法に重なります。また、女郎や義兄といったステークホルダーとの“共創”による祭りの実現は、現代でいえばファンや社員と共に作り上げるブランディング施策の先駆的事例といえるでしょう。
江戸の時代であっても、人の感情を動かし、文化的な意味付けを行うことでブランド価値を再構築するという考え方は変わらず、蔦重の戦略は「感動体験×物語性」という現代マーケティングの原則と深く共鳴しています。

あらすじ
安永六年(1777年)の正月、富本午之助が「富本豊前太夫」の名跡を正式に襲名し、蔦屋重三郎はその正本を出版。吉原への集客も増え、文化的な盛り上がりを見せ始める。そんな中、前年の祭りの失敗を挽回すべく、親たちは再び重三郎に相談を持ちかけるが、若木屋が先手を打って廻状を出し、「俄(にわか)」祭りを仕掛けてくる。これに対抗する形で、大文字屋と手を組んだ重三郎は、競争を逆手に取り、活気ある祭りを創出する。源内の助言を受け、吉原の記録冊子『明月余情』を制作。祭りの成功により、吉原は再び笑顔と熱気に包まれる。
1. 競争環境を活用した活性化戦略
江戸時代の課題と対応策
若木屋の先制的なプロモーション(廻状・錦絵販売)に対し、蔦重は競争そのものを否定せず、「張り合いこそが祭りを面白くする」と発想を転換。ライバルの存在を脅威ではなく活性化の契機と捉え、大文字屋に「競争に勝つ=来年の主導権を握る」構図を提示し、競争をモチベーションに変えて祭りの品質を高めた。
現代の課題と対応策
現代でも競合企業との健全な競争が、イノベーションやサービス向上を生み出す原動力になります。たとえば、コカ・コーラとペプシのような「ブランド戦争」は市場活性化の好例であり、両者の競争が業界全体のマーケティング力を底上げしています。蔦重の競争活用は、ビジネス戦略における「コーペティション(競争と協調)」的発想と重なります。
2.外部人材の創造性を活かしたコンテンツ戦略
江戸時代の課題と対応策
蔦重は、祭りの熱狂を記録に残すため、平賀源内に依頼するが断られる。代案として提示されたのが戯作者「朋誠堂喜三二」、すなわち平沢常富である。立場上耕書堂では書けない事情を抱えつつも、重三郎の熱意と提案に応じ、祭りの記念冊子『明月余情』の序文を執筆。この冊子が記念品として飛ぶように売れた。
現代の課題と対応策
近年、外部クリエイターとのコラボレーションによって魅力的なコンテンツを生み出す戦略が浸透しています。たとえば、無印良品が建築家と組んで家をデザインしたり、企業が人気YouTuberやライターとタイアップして独自コンテンツを発信するなど、ブランドに創造性を加える取り組みは多数存在します。蔦重の喜三二起用も、社外リソースの創造性を活用した好例です。
3.地域を巻き込んだイベントマーケティング
江戸時代の課題と対応策
吉原全体が参加する夏祭りを企画し、各店の出し物で観客を楽しませた。町中から人を呼び込み、吉原を“開かれた場所”と見せることで、観光地的なイメージの醸成とブランディングに成功。女子どもの入場解禁や通行切手不要といった開放性の演出も注目された。
現代の課題と対応策
地域イベントやフェスをマーケティング戦略として活用する企業や自治体は多くあります。例えば、北海道の「雪まつり」や沖縄の「那覇まつり」など、地域資源を活用した観光誘致と経済活性化を実現する手法と共通しています。蔦重の“地域巻き込み型プロモーション”は、地域ブランディングの先駆けといえるでしょう。
4.ストーリーテリングと記録の資産化
江戸時代の課題と対応策
熱気に満ちた祭りの体験を一過性にせず、冊子『明月余情』として記録に残し、ストーリーを伝える資産として販売。内容には芝居絵の名手・勝川春章の絵も取り入れ、視覚的な訴求力を備えた媒体に仕上げた。
現代の課題と対応策
ブランドのストーリーテリングは、消費者との感情的なつながりを生み、信頼や共感を醸成する力を持ちます。スターバックスが各店舗に背景ストーリーを設けたり、Appleが創業エピソードをマーケティングに活用するように、物語はブランドの文脈を深めるツールとなります。蔦重の冊子制作もまた、祭りを単なるイベントで終わらせず、価値のあるコンテンツとして定着させた例です。
江戸時代と現代の比較
第12話では、競争と創造性を通じて吉原の魅力を高めるという蔦屋重三郎の戦略が描かれました。これは、現代における「競争が市場全体を活性化させる」というビジネス観と一致しています。ライバル店の仕掛けたイベントに対し、対抗ではなく“相乗効果”として受け入れ、そこに記録冊子『明月余情』というコンテンツで物語を加える発想は、まさにブランドストーリーテリングの源流です。
さらに、外部クリエイター(朋誠堂喜三二/平沢常富)との連携や、祭りという体験を通じて地域全体を巻き込む手法は、現代のコラボレーション型コンテンツマーケティングや地域振興型プロモーションに通じるものでした。
江戸も令和も、“体験の価値”を物語で拡張し、それを可視化して資産化するという構造は変わらないのだということが、本話を通じて強く感じられます。
3.第11話・第12話から読み解く現代のマーケティング戦略
第11話・第12話で描かれた蔦屋重三郎の動きには、文化・共創・競争・O2Oプロモーションという現代でも非常に重要な4つの要素が含まれていました。彼の行動は、いわばマーケティングの先駆者としての実践例とも言えるでしょう。
-
文化を活かすことでブランドを差別化
-
他者との協働でブランド共感を高め
-
競争をチャンスとして捉え
-
顧客体験を記録・波及させることで価値を拡張
現代のマーケティング担当者にとっても、蔦屋の施策は非常に示唆に富んでいます。
1. 文化資源を活用したブランド再構築戦略
(第11話「富本節による格式再構築」から学ぶ)
江戸時代の戦略:
蔦屋は吉原の祭りに「富本節」という文化コンテンツを活用しました。浄瑠璃の人気語り手・富本午之助(のちの豊前太夫)を呼び、吉原の文化的格を高めようとしたのです。文化をプロモーションに取り込むことで、「娯楽」から「芸術性のある遊郭」へとブランドイメージを刷新しました。
現代の応用:
現代でも、「文化資源の再編集」によってブランド価値を高める取り組みは増えています。
-
地域の伝統工芸や祭りを活かした観光プロモーション(例:佐賀のバルーンフェスタ×焼き物文化)
-
ブランドミュージアムの設置や文化イベントへの協賛(例:LOUIS VUITTON財団の美術館活動)
-
コンテンツIPとブランドの融合(例:浮世絵×アパレルのコラボ、漫画×自治体PR)
“文化の力”をブランド構築に取り込む点で、蔦屋の動きは極めて現代的です。
2. 共創によるブランド共感戦略
(第11話「午之助との和解と祭り出演」から学ぶ)
江戸時代の戦略:
蔦屋は、過去に吉原で傷ついた経験を持つ富本午之助に対し、花魁たちとの直接対話の場を設け、共感を通じて出演を承諾させました。このように「参加者自らがブランドの一部になる」仕組みは、単なる交渉ではなく、共創によるブランディングの先駆けと言えます。
現代の応用:
現在のマーケティングでも、「共創(コ・クリエーション)」は重要なキーワードです。
-
ブランドファンとの共創プロジェクト(例:無印良品のアイデア募集施策)
-
インフルエンサーとのコラボ商品開発(例:YouTuber監修のコスメやフード)
-
クラウドファンディングによる開発参加型商品(例:MakuakeやKickstarter活用)
顧客・出演者・関係者が「自分ごと化」することで、より強いブランド共感を得ることが可能です。
3. 競争環境を逆手に取ったプロモーション戦略
(第12話「若木屋との祭り競争と“俄”戦略」から学ぶ)
江戸時代の戦略:
12話では、ライバルの若木屋が先んじて「俄(にわか)芝居」を展開し、吉原での注目を集めます。しかし、蔦屋はこの競争を否定せず、むしろ「競争があるからこそ盛り上がる」として、大文字屋に差別化された出し物を提案。競争をコンテンツとして利用した戦略でした。
現代の応用:
現代でも、競争を“戦う”のではなく“演出”するマーケティングが注目されています。
-
ブランド間の“掛け合い”による話題づくり(例:マクドナルドvsバーガーキングの広告合戦)
-
比較広告による差別化戦略(例:Google Pixel vs iPhoneキャンペーン)
-
ライバル企業との同時キャンペーンで話題性を演出(例:ECモール間のセール戦争)
競争そのものをストーリーとして利用することで、注目度・認知度を高める手法は、蔦屋の機転と一致します。
4. O2O型プロモーションによる来場促進と情報拡散
(第12話「錦絵と青本による“記録型プロモーション”」から学ぶ)
江戸時代の戦略:
蔦屋は、吉原の祭りを盛り上げるだけでなく、その熱狂を「勝川春章の絵+記念冊子『明月余情』」という形で記録・商品化しました。これはまさに、来場者の記憶を形にし、情報が他者へ波及していくプロモーションと言えます。
現代の応用:
現代では、O2O(Online to Offline)戦略が主流です。
-
イベント来場者にSNS投稿を促すプロモーション
-
来場者限定のデジタルコンテンツ配布
-
オフラインイベントの記念グッズをECで再販(例:フェスや展示会のグッズEC展開)
来場体験を記録化し、そこから波及効果を狙う点は、蔦屋の錦絵&冊子戦略とまったく同様です。
おわりに
大河ドラマ『べらぼう』第11話・第12話では、蔦屋重三郎が文化・競争・共創といった要素を巧みに取り入れ、吉原という地域ブランドを再び輝かせる姿が描かれました。それは単なる歴史の一場面ではなく、現代のマーケティングにも通じる普遍的な戦略の連続でもあります。
ブランドの差別化に文化資源を活かし、競合との対立を共創の機会に変え、イベントを通じて感情を動かし、その体験をストーリーとして資産化する。蔦屋の一手一手は、今日のビジネス現場においても有効であり、むしろ今だからこそ再評価されるべき知恵に満ちています。
市場が成熟し、顧客の価値観が多様化する今、求められるのは、商品やサービスの“スペック”だけでなく、感情・文化・物語といった“共感資産”の設計です。蔦屋重三郎が行ったように、人の心を動かし、記憶に残り、語り継がれる価値を創造することこそが、ブランドの持続的な力となります。
江戸から令和へ――時代は違えど、人を惹きつける本質は変わりません。蔦屋の歩みを通じて、私たちが今できるマーケティングのかたちを、引き続き探っていきましょう。次回もまた、『べらぼう』を通じてそのヒントを紐解いていきたいと思います。
次回以降も、ぜひご期待ください。
Tokyo Tokyo(東京おみやげプロジェクト)について
https://tokyotokyo.jp/ja/action/omiyage/
江戸時代から明治時代に使われていた「引札(宣伝用チラシ)」には、当時の日本の文化や暮らしが色濃く反映されています。私たちは、この歴史的に貴重な引札のデザインを現代に活かすため、東京都が進める「東京おみやげプロジェクト」に参画し、伝統的な日本の魅力が詰まった商品の開発と販売を行っています。
東京都と民間企業が共同で開発した伝統的な工芸品から文房具、食料品など、東京旅行の思い出をもっと楽しくするアイテム「東京おみやげ」のPR・販売拠点「# Tokyo Tokyo BASE」(羽田空港)で販売しています。
引札の魅力や現代の広告や商品開発に引札のエッセンスを取り入れたい方は、お気軽にご相談下さいませ。