大河ドラマ『べらぼう』蔦屋重三郎に学ぶ、政治的混乱と悲劇を乗り越える危機管理戦略
2025年に放送されたNHK大河ドラマ『べらぼう ~蔦重栄華乃夢噺~』の第27話と第28話では、江戸時代の出版業界の革新者・蔦屋重三郎が、政治的混乱と社会不安という激動の時代に直面する姿が描かれます。
第27話では、天明の大飢饉が深刻化する中で米騒動が勃発し、田沼政権への批判が高まる政治的危機に蔦重が巻き込まれます。そして第28話では、田沼意知暗殺事件という歴史的悲劇を通じて、蔦重は出版の力で社会に問いかけを投げかける使命を見出していきます。
政治的混乱と社会不安という現代にも通じる困難を前に、蔦重がどのように事業を継続し、社会的責任を果たしたのか。その物語は、現代の企業が直面する政治リスク管理、社会課題への対応、そして危機時のコミュニケーション戦略について、深い示唆を与えてくれます。
本記事では、これら二話で描かれた物語をもとに、現代のビジネス戦略に照らし合わせながら、政治的不安定期における企業の立ち位置、危機時のコンテンツ戦略、そして社会的影響力の活用について紐解いていきます。
.png?width=800&height=451&name=%E3%80%90%E5%9B%BA%E5%AE%9A%E3%80%91%E3%82%B5%E3%83%A0%E3%83%8D%E3%82%A4%E3%83%AB%E7%94%A8%E3%81%AE%E3%82%B3%E3%83%94%E3%83%BC%20(4).png)
1.第27話「願わくば花の下にて春死なん」:米騒動と政治的混乱への対応
天明の大飢饉がさらに深刻化し、江戸の米価は異常な高騰を続けています。田沼意知とその父・意次は、米価対策として「米穀売買御勝手次第(米の売買自由化)」という思い切った政策を導入します。しかし、この規制緩和政策は期待とは裏腹の結果を招きました。裕福な商人たちが米を買い占め、米価は下がるどころかさらに高騰し、庶民の生活はますます困窮していきます。
このような状況の中で、田沼親子への非難の声が高まり、江戸の町には飢えた流民が溢れるようになります。「田沼親子=悪の組織」という声も起こり、政治的な混乱が社会全体を覆っていきます。
蔦屋重三郎は、このような混乱の中でも大店の主として事業を継続していかなければなりません。安い米を仕入れる新たなルートを模索しつつ、町に溢れる流民への対処も課題となります。蔦重にとって、これは単なる経営上の問題ではなく、地域社会の一員としての責任を問われる試練でもありました。
一方、人間関係の面では、田沼意知と誰袖花魁の身請け話が一時頓挫しかかりますが、意知は「春にはともに花を見たい」と約束し、二人の関係は深まっていきます。しかし、この束の間の幸福も、迫り来る悲劇の影を感じさせるものでした。
政治の世界では、幕府内で蝦夷地(北海道)の扱いを巡る対立が激化していきます。一橋治済が田沼意次の政策に反発し、松前家や島津家も巻き込んだ政争が繰り広げられます。この政治的な対立は、後の事件への伏線となっていきます。
物語の終盤では、佐野政言の父・政豊が田沼邸で「系図を返せ」と騒ぎを起こし、政言が止めに入るなど騒然とした空気が満ちていきます。この混乱が、次話で起こる悲劇的事件への不穏な前兆として描かれています。
1. 危機期における供給チェーン管理と社会的責任
天明の大飢饉により米価が高騰する中、蔦重は「安く米を仕入れる新たなルートを模索」する一方で、大店の主として地域社会への責任も果たそうとしました。これは単なる利益追求ではなく、困窮する流民や町の人々に対する社会的責任を意識した行動でした。
蔦重のこの取り組みは、現代で言えば「サプライチェーンの最適化」と「CSR(企業の社会的責任)活動」を同時に実現しようとする試みといえます。危機的状況の中でも、自社の経営安定と社会貢献を両立させることで、長期的なブランド価値の維持を図ったのです。
現代の課題と対応策
現代企業も、パンデミックや自然災害、地政学的リスクなどにより供給チェーンが混乱した際、同様の課題に直面します。原材料の価格高騰や供給不足に対応しながら、同時に顧客や地域社会への責任も果たさなければなりません。
成功する企業は、複数の供給ルートの確保、在庫の戦略的管理、そして危機時の社会貢献活動を組み合わせることで、短期的な困難を乗り越えながら長期的な信頼を築いています。
江戸時代と現代の比較
蔦重の米の仕入れルート開拓は、現代のリスク分散型サプライチェーン構築と本質的に同じです。どちらも、単一の供給源に依存することの危険性を認識し、複数のオプションを確保することで事業の継続性を保とうとしています。また、利益追求と社会的責任のバランスを取る姿勢も共通しています。
2.政治リスクへの対応と中立的立場の維持
江戸時代の課題と対応策
田沼政権への批判が高まる中、蔦重は政治的な混乱に巻き込まれることなく、事業を継続していかなければなりませんでした。田沼意知との関係を維持しながらも、民衆の怒りの矛先が自分の事業に向かわないよう、慎重な立ち回りが求められました。
この状況では、特定の政治勢力に過度に肩入れすることなく、商人としての中立的な立場を保ちながら、社会の混乱を鎮めるような役割を果たすことが重要でした。蔦重は出版業者として、情報の発信者という立場を活かし、社会の安定に貢献しようとしたのです。
現代の課題と対応策
現代のグローバル企業も、政治的な不安定や政権交代、国際関係の悪化などの政治リスクに常に直面しています。特定の政治勢力や政策に依存しすぎることなく、どのような政治情勢の変化にも対応できる柔軟性を保つことが重要です。
企業は政治的中立性を保ちながら、ESG(環境・社会・ガバナンス)の観点から社会的な価値創造に取り組むことで、政治的な変化に左右されない持続可能な経営基盤を築くことができます。
江戸時代と現代の比較
蔦重の政治的中立性の維持は、現代企業の政治リスク管理と同じ発想です。どちらも、短期的な政治的利益よりも、長期的な事業の安定性と社会的信頼を重視しています。政治的な混乱期において、企業が果たすべき社会的役割を意識している点も共通しています。
3. 有能な事業パートナーとの出会いと信頼関係の構築
江戸時代の課題と対応策
米騒動と政治的混乱の中で、蔦重は流民への対処という新たな課題に直面しました。これは単なる治安問題ではなく、有能な人材を見極め、組織に取り込むための機会でもありました。困窮した人々の中から、将来性のある人材を発掘し、適切に教育・配置することで、組織の強化を図ったのです。
また、既存の従業員の士気維持も重要な課題でした。社会全体が不安定な中で、従業員が安心して働ける環境を整備し、組織の結束力を保つことが事業継続の鍵となりました。
現代の課題と対応策
現代においても、経済危機や社会不安の時期には、優秀な人材の流動性が高まります。他社からの転職希望者が増える一方で、自社の人材流出のリスクも高まります。この状況を人材獲得の機会として活用しながら、既存従業員の定着率向上も図る必要があります。
成功する企業は、危機時でも従業員の雇用を維持し、教育投資を継続することで、回復期における競争優位性を確保しています。また、社会貢献活動を通じて従業員のエンゲージメントを高めることも重要な戦略です。
江戸時代と現代の比較
蔦重の人材マネジメントは、現代の危機時人材戦略と本質的に同じです。どちらも、困難な状況を人材強化の機会として捉え、長期的な組織力向上を図っています。また、従業員の安心・安全を確保することで、組織の結束力を維持しようとする姿勢も共通しています。
2.第28話「佐野世直大明神」:悲劇的事件と社会変革への使命

あらすじ
江戸城内で衝撃的な事件が発生します。佐野政言が突如、田沼意知に斬りつけ、重傷を負わせるという前代未聞の事件が起こったのです。意知は父・田沼意次のもとに運ばれますが、傷は深く、回復の見込みはありませんでした。意知は最期に父に対し、「志を継いでほしい」「身請けした遊女を頼む」と遺言を残し、静かに息を引き取ります。
息子を亡くした意次は深い悲しみに沈みます。一方、意知を斬った佐野政言も切腹して自害し、この事件は江戸中に大きな衝撃を与えました。しかし、民衆の反応は意外なものでした。事件は「天罰」として受け止められ、田沼家の葬列には石が投げられるなど、民衆の怒りが爆発したのです。
この混乱の中で、意知の棺を守ろうとした誰袖は、群衆の投石で怪我を負います。愛する人を失った悲しみと、民衆の怒りに晒される恐怖の中で、誰袖の慟哭は見る者の心を打ちました。
蔦重はこの一連の事件を目の当たりにし、人々の苦しみや政争の激しさを痛感します。同時に、出版業者として自分が果たすべき役割について深く考えるようになります。黄表紙などの出版を通じて、希望や問いかけを世の中に投げかけることこそが、自分の使命であると決意を固めるのです。
民衆の間では、佐野政言を「世直し大明神」として祀る声が湧き上がります。政治への不満と変革への願いが、一人の男を神格化するという形で現れたのです。江戸の空気は混迷と悲しみに包まれながらも、新たな時代への期待も感じられる複雑なものとなっていきます。
この回では、歴史的な事件を通じて、蔦重が単なる商人から社会的使命感を持つ文化人へと変貌していく過程が描かれています。
1. 危機時のコミュニケーション戦略とメッセージ発信
江戸時代の課題と対応策
田沼意知の暗殺事件という衝撃的な出来事を受け、蔦重は「出版(黄表紙など)の力で希望や問いかけを世の中に投げよう」と決意します。これは、社会的混乱の中で企業が果たすべきコミュニケーションの役割を示す重要な例です。
蔦重は、単に事件を報道するのではなく、社会全体が抱える問題や課題について人々に考えてもらうきっかけを提供しようとしました。出版という手段を通じて、建設的な社会対話を促進し、混乱した世情に一筋の光明を見出そうとしたのです。
現代の課題と対応策
現代企業も、社会的危機や重大事件が発生した際、適切なコミュニケーション戦略が求められます。SNSやオウンドメディアを通じて、企業の価値観や社会に対する姿勢を明確に発信することで、ステークホルダーとの信頼関係を維持・強化することができます。
重要なのは、単なる情報発信ではなく、社会課題の解決に向けた建設的なメッセージを発信することです。企業の専門性を活かした視点から、社会に価値ある問いかけを投げかけることが、真の社会的影響力の発揮につながります。
江戸時代と現代の比較
蔦重の出版を通じた社会への問いかけは、現代の企業によるソート・リーダーシップの発揮と本質的に同じです。どちらも、自社の専門性と影響力を活用して、社会的課題について人々に考えてもらうきっかけを提供しています。危機時だからこそ、企業の真価が問われるという認識も共通しています。
2.社会的感情とブランド戦略の関係性
江戸時代の課題と対応策
佐野政言の「神格化」という現象は、民衆の感情や社会の空気を読み取り、それを商機として捉える重要性を示しています。蔦重は、この社会的な騒動や大衆の感情が持つ強力な拡散力(バイラル効果)を敏感に察知し、風刺本や黄表紙の出版に素早く着手したのです。
これは現代で言えば、SNSでのトレンドや世論の動向を把握し、タイムリーなコンテンツマーケティングを展開することに相当します。社会の関心事に敏感に反応し、適切なタイミングで価値あるコンテンツを提供することで、大きな影響力を獲得することができました。
現代の課題と対応策
現代企業も、社会的な出来事や大衆の感情の変化を的確に捉え、それに対応したマーケティング戦略を展開する必要があります。ただし、センシティブな問題については、十分な配慮と責任感を持って取り組むことが重要です。
企業は社会の動向を常にモニタリングし、自社の価値観と整合性の取れた形で、タイムリーなメッセージやコンテンツを発信することで、ブランドの存在感を高めることができます。
江戸時代と現代の比較
蔦重の時事的な出版戦略は、現代のリアルタイムマーケティングやニュースジャッキングと同じ発想です。どちらも、社会の関心事に敏感に反応し、適切なタイミングでコンテンツを提供することで、大きな影響力を獲得しています。ただし、社会的責任を伴う重要なテーマについては、慎重なアプローチが求められる点も共通しています。
3.社会変革期における企業の役割と使命感
江戸時代の課題と対応策
田沼意知の死と佐野政言の神格化は、江戸社会の大きな転換点となりました。蔦重は、このような社会変革期において、出版業者として何ができるかを深く考え、「言葉の力」で社会に貢献することを決意しました。
単に商品を売るだけでなく、社会の課題や矛盾について人々に考えてもらうきっかけを提供し、より良い社会の実現に向けた議論を促進することが、文化産業に携わる者の使命であると認識したのです。
現代の課題と対応策
現代においても、社会的な変革期には企業の役割が特に重要になります。技術革新、環境問題、社会格差など、様々な課題に対して、企業は自社の事業活動を通じて解決策を提示することが求められています。
パーパス経営(目的経営)の考え方が注目されるのも、企業が単なる利益追求組織ではなく、社会的価値創造の担い手としての役割を果たすことが期待されているからです。
江戸時代と現代の比較
蔦重の社会的使命感は、現代のパーパス経営やESG経営の先駆けといえます。どちらも、企業が社会の一員として、より良い世界の実現に向けて積極的な役割を果たそうとする姿勢を示しています。利益追求と社会貢献を両立させることで、持続可能な成長を実現しようとする発想も共通しています。
3.第27話・28話から読み解く:政治的危機を乗り越える企業戦略

現代の企業経営においても、政治的不安定や社会的混乱は避けられないリスクです。以下では、蔦重の危機対応から学べる3つの重要な戦略について詳しく分析します。
1. 政治的中立性を保ちながらの社会的責任の履行
米騒動と田沼政権への批判が高まる中、蔦重は特定の政治勢力に偏ることなく、商人としての中立的な立場を維持しました。同時に、流民への対応や地域社会への貢献を通じて、社会的責任を果たそうとしたのです。
この姿勢は、現代で言えば「政治的中立性を保ちながらのESG経営」に相当します。特定の政治的立場に偏ることなく、社会全体の利益を考慮した事業運営を行うことで、政治的変化に左右されない持続可能な経営基盤を築くことができます。
実践的な行動指針
蔦重の政治的危機対応から学べる現代的な教訓は以下の通りです:
- 多様なステークホルダーとの関係維持:特定の政治勢力だけでなく、幅広い関係者との良好な関係を保つ
- 社会課題への積極的取り組み:政治的立場を超えて、社会全体の課題解決に貢献する
- 長期的視点での意思決定:短期的な政治的利益よりも、長期的な社会的価值を重視する
2. 危機時のコンテンツ戦略とソート・リーダーシップ
情報発信による社会的影響力の発揮
田沼意知暗殺事件という衝撃的な出来事を受け、蔦重は出版を通じて社会に建設的なメッセージを発信することを決意しました。単なる事件報道ではなく、社会全体が抱える課題について人々に考えてもらうきっかけを提供しようとしたのです。
この取り組みは、現代の「ソート・リーダーシップ」や「コンテンツマーケティング」と本質的に同じです。企業の専門性と影響力を活用して、社会的課題について価値ある視点を提供することで、ブランドの存在意義を高めることができます。
現代への応用
現代企業が危機時に展開すべきコンテンツ戦略:
- 専門性を活かした独自の視点:自社の専門分野から社会課題にアプローチする
- 建設的な対話の促進:批判だけでなく、解決策や改善案を提示する
- 継続的な情報発信:一時的なリアクションではなく、長期的な取り組みとして位置づける
3. 社会変革期における企業の使命感とパーパス経営
時代の転換点での役割自認
佐野政言の神格化という現象を通じて、蔦重は社会が大きな変革期にあることを実感しました。この状況で、出版業者として何ができるかを深く考え、「言葉の力」で社会に貢献することが自分の使命であると認識したのです。
この使命感は、現代の「パーパス経営」の考え方と完全に一致します。企業が単なる利益追求組織ではなく、社会的価値創造の担い手として、より良い世界の実現に向けて積極的な役割を果たそうとする姿勢です。
パーパス実現のための戦略要素
蔦重の使命感から学ぶパーパス経営の実践方法:
- 社会課題の深い理解:表面的な問題ではなく、根本的な社会の矛盾や課題を把握する
- 自社の強みの社会的活用:企業の持つ専門性やリソースを社会課題解決に活用する
- 長期的なコミットメント:一時的な取り組みではなく、継続的な社会貢献を約束する
これらの戦略を通じて、蔦屋重三郎は政治的混乱と社会不安という困難な状況を乗り越え、企業の社会的影響力を最大化することに成功しました。現代の企業経営においても、これらの教訓は非常に価値ある指針となるでしょう。
おわりに:混乱期を乗り越える企業リーダーの資質
第27話・28話では、蔦屋重三郎が米騒動から田沼意知暗殺事件まで、江戸時代でも稀に見る政治的混乱と社会不安を経験し、その中で出版業者としての真の使命を見出していく姿が描かれました。これらの激動を通じて、蔦重は単なる商売人から、社会的責任を深く自覚する文化的リーダーへと成長していきます。
この物語が現代の私たちに伝える教訓は、以下の3つの柱に集約されます。
■ 政治的中立性と社会的責任の両立 米騒動と政治的混乱の中で、蔦重は特定の政治勢力に偏ることなく、商人としての中立的な立場を保ちながら、流民への対応や地域社会への貢献を通じて社会的責任を果たしました。この姿勢は、現代のESG経営における政治的中立性と社会課題への積極的取り組みの重要性を先取りしたものです。企業が持続可能な成長を実現するためには、政治的変化に左右されない普遍的な価値創造が不可欠です。
■ 危機時のコミュニケーション力 田沼意知暗殺事件という衝撃的な出来事を受け、蔦重は出版を通じて社会に建設的なメッセージを発信することを決意しました。これは、現代の企業が実践すべきソート・リーダーシップやコンテンツマーケティングの本質を示しています。危機時だからこそ、企業の価値観と専門性を活かした価値ある情報発信が、社会からの信頼獲得につながります。
■ 社会変革期における使命感 佐野政言の神格化という現象を通じて、蔦重は社会が大きな転換点にあることを実感し、「言葉の力」で社会に貢献することが自分の使命であると認識しました。この使命感は、現代のパーパス経営の考え方と完全に一致します。企業が単なる利益追求組織ではなく、社会的価値創造の担い手として積極的な役割を果たすことで、持続可能な成長と社会の発展を同時に実現することができます。
加えて、田沼意知と誰袖の悲恋や、民衆の怒りに晒される誰袖の姿を通じて、企業活動が多くの人々の人生に深く関わっていることも描かれました。企業の意思決定は、従業員、顧客、地域社会など、様々なステークホルダーの生活に大きな影響を与えるため、高い倫理観と責任感が求められます。
そして、蔦重が最終的に辿り着いた「書を以て世を耕す」という理念は、現代の企業が目指すべき「社会的インパクトの創出」と同じ志向です。単に商品やサービスを提供するだけでなく、社会全体の知識レベル向上や課題解決に貢献することで、企業の存在意義を高めることができます。
次回以降、蔦重がこれらの混乱期の経験をどのように活かし、さらなる文化的貢献を果たしていくのか。彼の歩みから、現代の私たちが学ぶべき「社会的リーダーシップ」と「危機管理能力」の本質を引き続き探っていきましょう。
Tokyo Tokyo(東京おみやげプロジェクト)について
https://tokyotokyo.jp/ja/action/omiyage/
江戸時代から明治時代に使われていた「引札(宣伝用チラシ)」には、当時の日本の文化や暮らしが色濃く反映されています。私たちは、この歴史的に貴重な引札のデザインを現代に活かすため、東京都が進める「東京おみやげプロジェクト」に参画し、伝統的な日本の魅力が詰まった商品の開発と販売を行っています。
東京都と民間企業が共同で開発した伝統的な工芸品から文房具、食料品など、東京旅行の思い出をもっと楽しくするアイテム「東京おみやげ」のPR・販売拠点「# Tokyo Tokyo BASE」(羽田空港)で販売しています。
引札の魅力や現代の広告や商品開発に引札のエッセンスを取り入れたい方は、お気軽にご相談下さいませ。




.png)
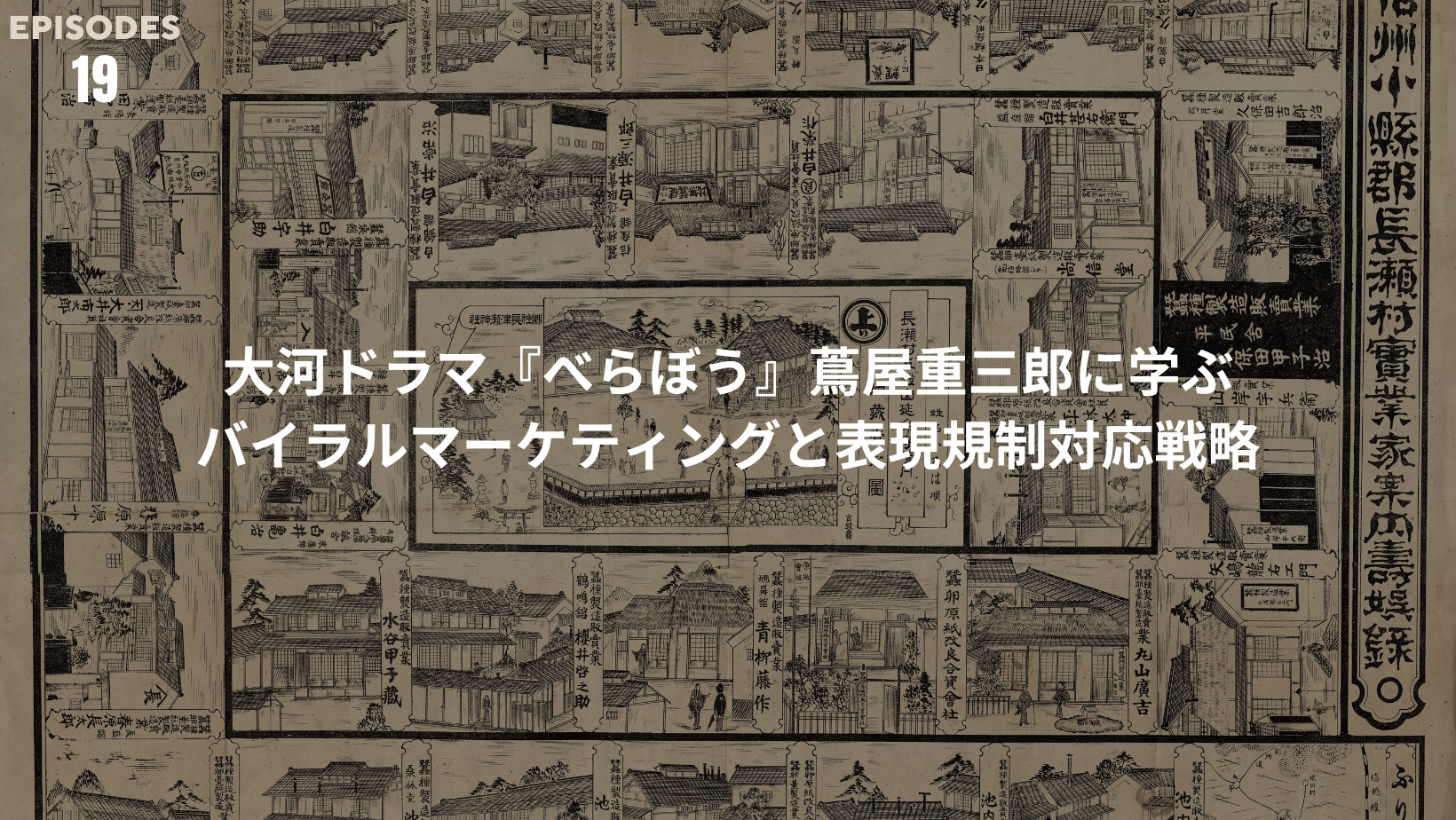
.png)