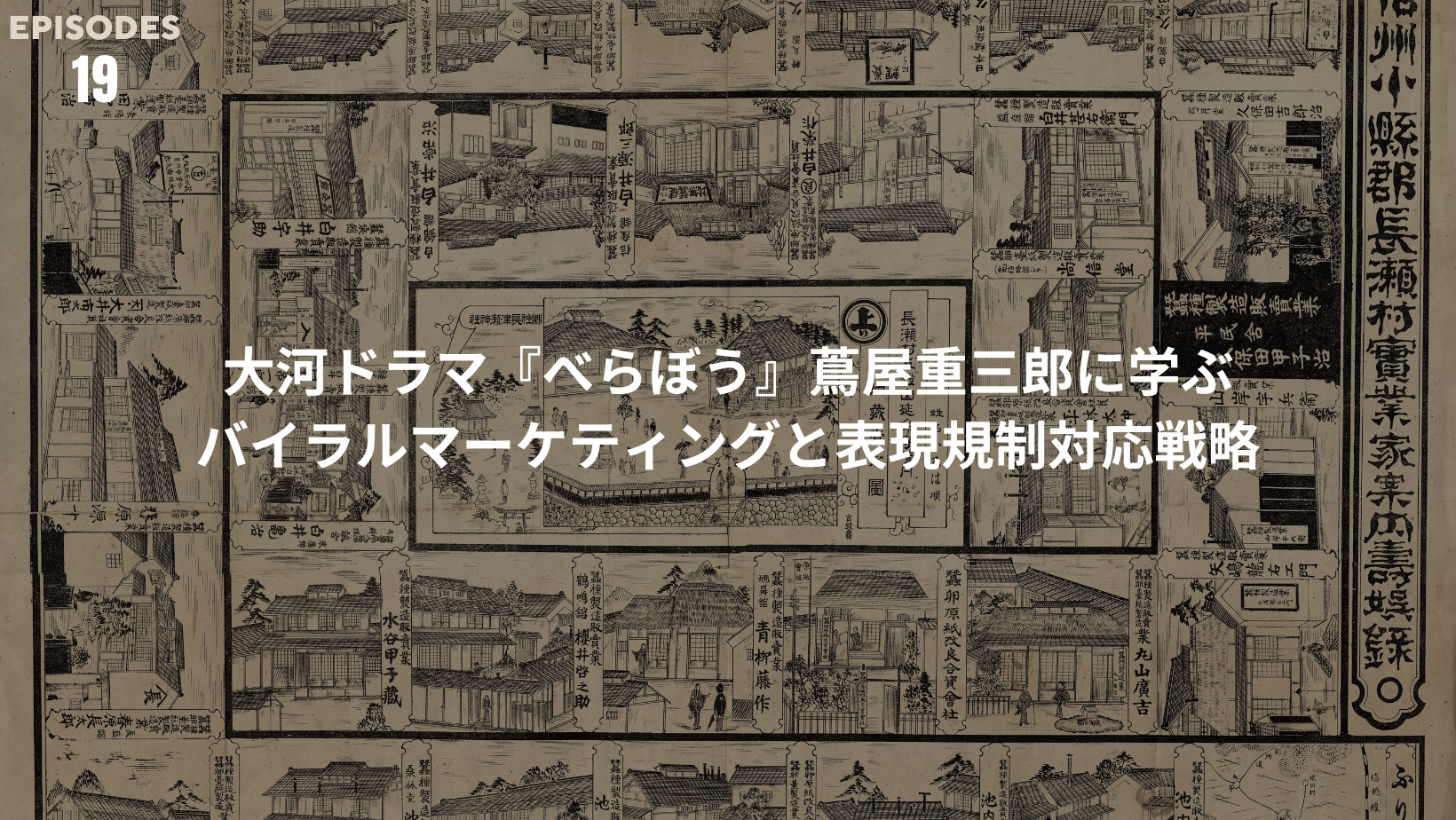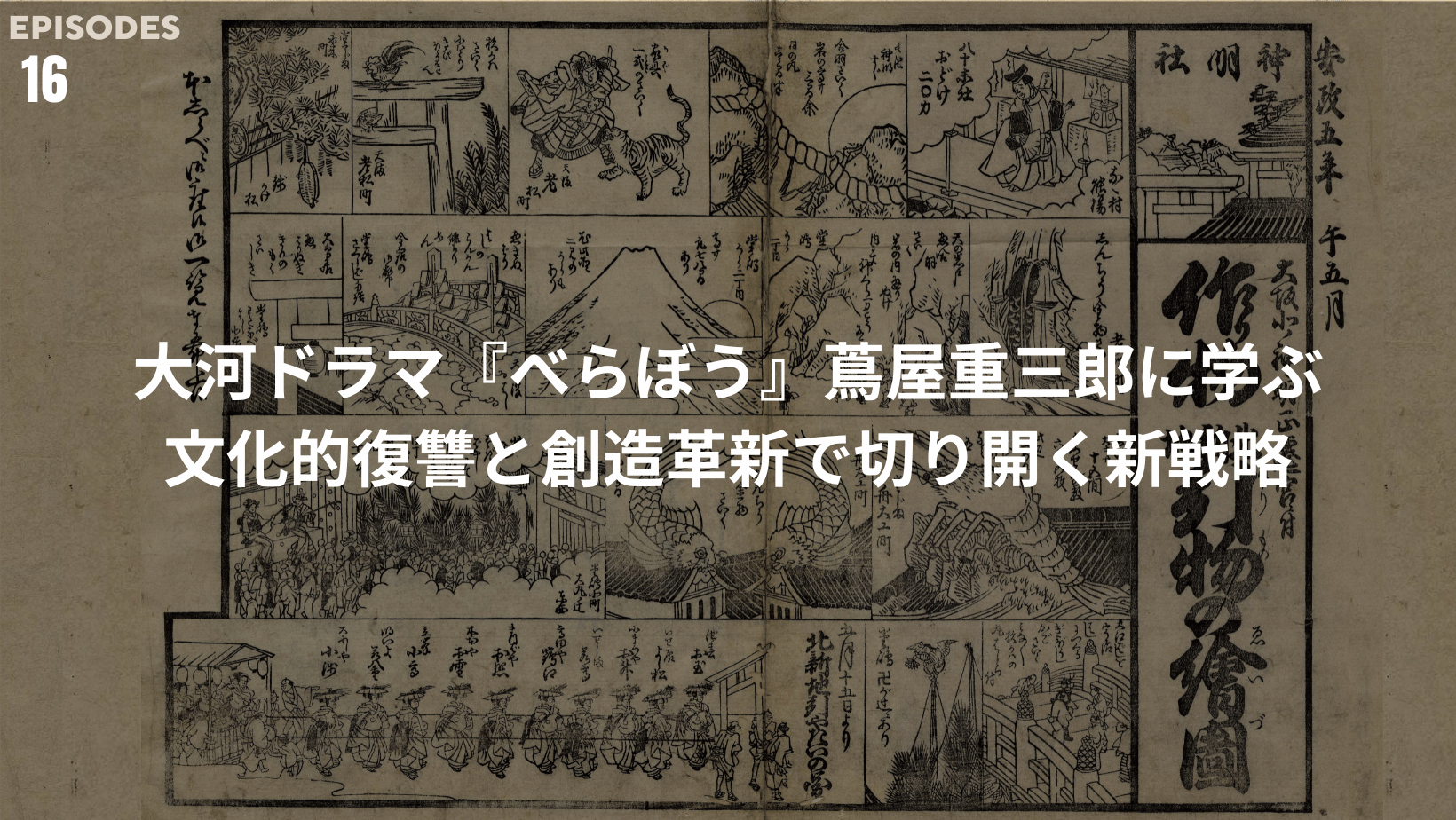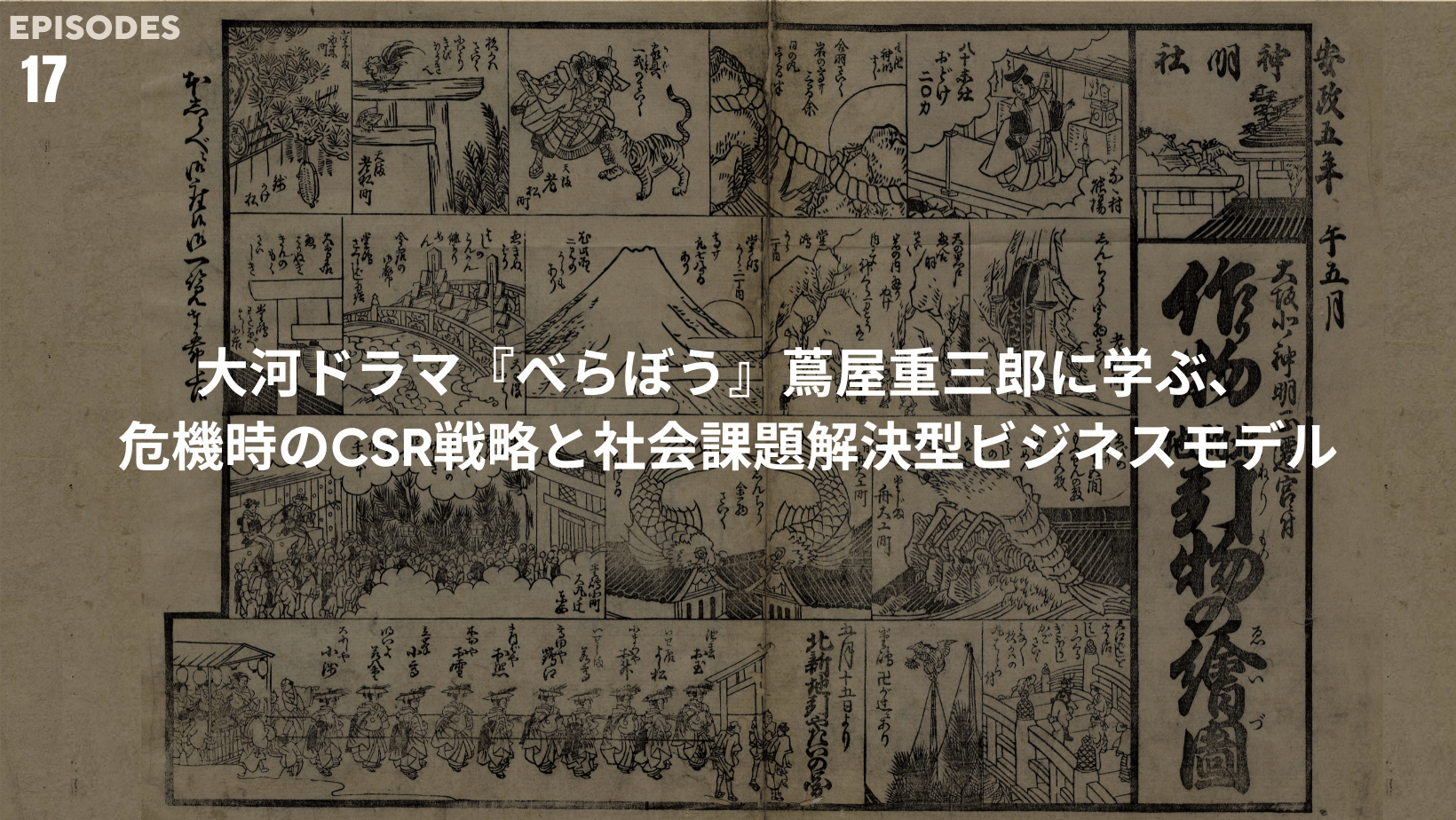大河ドラマ『べらぼう』蔦屋重三郎に学ぶ、クリエイターエコノミー時代の人材戦略とビジネス転換
2025年に放送されたNHK大河ドラマ『べらぼう ~蔦重栄華乃夢噺~』の第37話と第38話では、江戸時代の出版文化が存亡の危機を迎える中で、蔦屋重三郎がクリエイターの離散という深刻な課題に直面し、新たなビジネスモデルへの転換を迫られる様子が描かれます。
第37話「地獄に京伝」では、恋川春町の切腹という悲劇を受けて戯作者たちが一斉に筆を折る中、蔦重が歌麿という唯一の希望に活路を見出そうとする姿が描かれます。そして第38話では、主力クリエイターである山東京伝の完全離脱により、蔦重の経営が重大な転機を迎えます。
これらの物語は、現代のクリエイターエコノミーにおける人材流出対策、パトロンシップモデルの活用、そして逆境時のビジネスモデル転換について、深い示唆を与えてくれます。規制強化という外的圧力の中で、いかにして創造的事業を継続し、新たな価値創造の仕組みを構築するかという現代的課題を、江戸時代の蔦重の経営判断を通じて学ぶことができます。
.png?width=674&height=380&name=%E3%81%B9%E3%82%89%E3%81%BC%E3%81%8620%20(1).png)
1.第37話「地獄に京伝」:クリエイター離散危機とサバイバル戦略

あらすじ
江戸の出版界に衝撃が走ります。人気戯作者・恋川春町が政治批判の責任を取って切腹するという悲劇的な事件が発生し、これを受けて江戸の戯作者たちが一斉に筆を折る事態となりました。出版規制の厳しさと、創作活動に伴うリスクの高さを目の当たりにした創作者たちが、自らの身を守るために創作活動から離脱したのです。
蔦屋重三郎は、この危機的状況を打開するため、町人戯作者である北尾政演に協力を求めます。しかし政演もまた、友人である春町の死に深く心を痛め、蔦重の申し出を断ってしまいます。出版事業の中核を担っていた戯作者たちを次々と失った蔦重にとって、もはや頼れるのは絵師・歌麿だけという絶望的な状況に陥ります。
そんな中、歌麿のもとに栃木の豪商から肉筆画の直接依頼が舞い込みます。これまで出版物を通じて間接的に評価されていた歌麿にとって、顧客から直接その技量を評価され、高額な対価を得られるこの機会は、新たな自己肯定感と創作への意欲をもたらしました。
一方、幕府では松平定信による改革が一層激化します。中新(中洲)の取り壊しや大奥での厳格な倹約令の実施など、社会全体に質素倹約を強制する政策が推進されます。吉原を含む商人や遊興業への締め付けも強化され、蔦重の事業環境はますます厳しくなっていきます。周囲からは「これ以上幕府を刺激するな」と諫められ、蔦重は四面楚歌の状況に置かれることになります。
現代に通じるポイント
江戸時代の課題と対応策
春町の切腹事件は、創作活動に伴うリスクが顕在化した象徴的な出来事でした。戯作者たちの一斉離脱は、現代で言うところの「人材流出」「タレントドレイン」に相当する深刻な経営危機です。蔦重は残された人材(歌麿)の価値を最大化する戦略に転換し、量から質への方向転換を図りました
現代の課題と対応策
現代のクリエイターエコノミーにおいても、優秀なクリエイターの確保と維持は企業の競争力に直結する重要課題です。特にゲーム業界、広告業界、エンターテインメント業界では、スタークリエイターの流出が企業価値に大きな影響を与えます。
効果的なタレントリテンション戦略には、創作環境の整備、適切な報酬体系、キャリアパスの明確化、そして何より創作者の安全と尊厳の保護が不可欠です。また、特定のクリエイターへの過度な依存を避け、人材の多様化と育成システムの構築も重要です。
蔦重の時代と現代では、クリエイターが直面するリスクの性質は異なりますが、創作活動の自由と安全を確保することの重要性は変わりません。現代では政治的弾圧の代わりに、炎上リスクやSNSでの批判、著作権侵害などが新たなリスク要因となっています。
重要な教訓は、クリエイターとの信頼関係を築き、彼らが安心して創作に集中できる環境を提供することです。また、危機的状況においても、残された人材の価値を最大化し、新たな可能性を見出す柔軟性が求められます。
2. パトロンシップモデルと直接顧客関係の構築
江戸時代の課題と対応策
歌麿への栃木豪商からの直接依頼は、従来の出版流通に依存しない新たな収益モデルの可能性を示しています。中間業者を通さない直接的な顧客関係により、より高い収益性と顧客満足度を実現できる可能性が生まれました。
現代の課題と対応策
現代のデジタル時代においても、パトロンシップモデルは重要な収益源となっています。PatreonやFanbox、YouTube のメンバーシップなど、ファンが直接クリエイターを支援するプラットフォームが拡大しています。
このモデルの利点は、安定した収益源の確保、ファンとの深い関係構築、創作の自由度向上です。企業にとっても、個人クリエイターとの直接契約により、より柔軟で効率的なコンテンツ制作が可能になります。
江戸時代と現代の比較
歌麿の豪商との直接取引と現代のパトロンシップモデルは、中間流通を排除して付加価値を最大化するという点で共通しています。技術の進歩により、現代ではより多くの潜在的パトロンにアクセスできますが、個人的な信頼関係の重要性は変わりません。
江戸時代の課題と対応策
松平定信による厳格な出版規制は、蔦重にとって事業存続の危機でした。従来の戯作者依存モデルが機能しなくなった状況で、歌麿という唯一の資産を活用した新たな事業モデルの構築が急務となりました。
現代の課題と対応策
現代企業も、規制強化、市場環境の変化、技術革新などにより、既存ビジネスモデルの見直しを迫られることがあります。このような状況では、保有する核となる資産や能力を再評価し、新たな市場機会を見出すピボット戦略が重要です。
成功するピボットには、市場ニーズの正確な把握、既存資産の活用可能性の検証、そして迅速な意思決定と実行が必要です。また、変化に対応できる組織文化と、リスクを取れる経営判断力も不可欠です。
江戸時代と現代の比較
蔦重が直面した出版規制と現代企業が直面する規制強化(個人情報保護、環境規制、金融規制など)は、既存ビジネスモデルを根本から見直す必要がある点で共通しています。どちらの時代においても、規制を単なる制約として捉えるのではなく、新たな価値創造の機会として活用する視点が重要です。
現代の優位性は、デジタル技術とグローバル市場により、より多様なピボット選択肢が存在することです。しかし、蔦重の時代から変わらない成功要因は、保有する核となる資産(人材、技術、ブランド)を正確に評価し、それを新たな市場ニーズに適合させる経営判断力です。規制という逆風を、競合他社との差別化機会として捉える戦略的思考が、時代を超えた成功の鍵となっています。
2.第38話:主力クリエイターの離脱と経営転換の実践
.png?width=720&height=480&name=ChatGPT%20Image%202025%E5%B9%B410%E6%9C%888%E6%97%A5%2014_29_58%20(1).png)
あらすじ
蔦屋重三郎の経営危機は更に深刻化します。前話で協力を断った山東京伝が、筆禍事件への恐怖から「俺、もう書かねえっす」と完全に創作活動からの引退を宣言し、蔦屋出版から離脱してしまいます。これにより、蔦重は最後の主力戯作者まで失うことになりました。
一方で、歌麿の才能とビジネス展開への期待が、蔦重にとって唯一の希望の光となります。豪商からの直接依頼で成功を収めた歌麿は、従来の出版業界の枠組みを超えた新たな芸術ビジネスの可能性を示しています。蔦重は歌麿との協働により、「江戸で生き残る出版戦略」の新たな一手を模索し始めます。
しかし、歌麿の身近な女性であるおきよの体調悪化が続き、歌麿自身にも不安材料が増えてきます。頼みの綱である歌麿にも問題が生じる中、蔦重の経営と人間関係の両面で大きな転機を迎えることになります。このような状況で、蔦重は従来の出版業依存から脱却し、新たなビジネスモデルの構築を迫られています。
1. 主力人材流出による事業リスクと対応策
江戸時代の課題と対応策
京伝の完全離脱は、蔦重にとって最大の経営資産であるクリエイターの喪失を意味しました。これは現代で言うキーパーソンリスクの典型例です。蔦重は残された限られた人材(歌麿)の価値を最大化し、新たな事業領域への展開を図る戦略に転換せざるを得ませんでした。
現代の課題と対応策
現代企業においても、主力人材の離脱は深刻な経営リスクです。特にクリエイティブ業界、IT業界、コンサルティング業界など、個人の能力に依存する度合いが高い事業では、キーパーソンの流出が企業価値に直結します。
効果的なリスク対応策には、人材の多様化、ナレッジマネジメントシステムの構築、後継者育成プログラム、そして属人的な業務の標準化が含まれます。また、離職リスクの早期発見と予防的な対話も重要です。
| リスク要因 | 江戸時代(蔦重の事例) | 現代企業の対応 |
|---|---|---|
| 主力人材の離脱 | 京伝の完全引退により戯作部門が機能停止 | 複数人材の育成、業務の標準化 |
| 外的圧力 | 政治的弾圧による創作活動のリスク増大 | 規制対応、コンプライアンス強化 |
| 市場環境変化 | 出版規制による従来モデルの機能不全 | ビジネスモデルの多角化、新市場開拓 |
江戸時代と現代の比較
京伝の離脱が蔦重に与えた打撃と現代企業のキーパーソンリスクは、個人の能力に依存するビジネスモデルの脆弱性という点で共通しています。どちらの時代においても、特定の人材への過度な依存は経営リスクとなり得ます。
現代の優位性は、デジタル技術によるナレッジの蓄積・共有システムや、リモートワークによるグローバルな人材確保が可能なことです。しかし、蔦重の時代から変わらない重要な教訓は、人材の多様化と後継者育成の重要性です。一人の天才に依存するのではなく、組織全体の創造力を高める仕組みづくりが、持続可能な競争優位の源泉となります。
2.個人ブランド戦略とダイレクト顧客関係
江戸時代の課題と対応策
歌麿の成功は、個人の才能とブランド価値を直接顧客に届けるモデルの有効性を証明しています。従来の出版流通を介さない直接的な関係により、より高い付加価値と顧客満足を実現できることが示されました。
現代の課題と対応策
現代のデジタル時代において、個人ブランドの重要性はますます高まっています。SNS、YouTube、個人サイトなどを通じて、クリエイターが直接ファンとつながり、収益化を図ることが可能になっています。
成功する個人ブランド戦略には、独自性の確立、一貫したメッセージ発信、ファンとの継続的な関係構築が必要です。企業としては、所属クリエイターの個人ブランド化を支援し、Win-Winの関係を構築することが重要です。
江戸時代と現代の比較
歌麿の個人ブランド化と現代のインフルエンサーマーケティングは、個人の才能と魅力を直接顧客に届けるという点で本質的に同じ戦略です。技術的な違いはあっても、「人」に焦点を当てたマーケティングの有効性は時代を超えて変わりません。
現代の優位性は、SNSやデジタルプラットフォームにより、より広範囲で効率的な個人ブランディングが可能なことです。しかし、歌麿の時代から変わらない成功要因は、本物の才能と継続的な価値提供です。テクニカルな手法に頼るのではなく、真の価値を持つクリエイターの魅力を最大化することが、持続可能な個人ブランド戦略の核心となります。
3.逆風時の経営転換とイノベーション創出
江戸時代の課題と対応策
蔦重は従来の戯作者依存モデルが機能しなくなった状況で、歌麿という唯一の資産を活用した新たな芸術ビジネスモデルの構築を迫られました。これは典型的なピボット戦略の実例です。
現代の課題と対応策
現代企業も、市場環境の激変により既存ビジネスモデルの見直しを迫られることがあります。COVID-19パンデミック、デジタル化の加速、ESG経営の要請など、様々な要因により戦略転換が必要になります。
成功する経営転換には、既存資産の再評価、新市場機会の発見、迅速な意思決定、そして組織全体の変革マインドが必要です。逆風をイノベーションの機会として捉える経営者のマインドセットが成功の鍵となります。
江戸時代と現代の比較
蔦重の出版業から芸術ビジネスへの転換と、現代企業のデジタルトランスフォーメーションは、既存ビジネスモデルの限界を認識し、新たな価値創造手法を模索するという点で共通しています。どちらも、変化を脅威ではなく機会として捉える経営マインドが成功の分かれ目となります。
現代の優位性は、豊富なデータ分析ツールと多様な技術的選択肢により、より精密で効果的な戦略転換が可能なことです。しかし、蔦重の時代から変わらない成功要因は、保有する核となる資産(人材、技術、ブランド、顧客関係)を正確に評価し、それを新たな市場価値に転換する経営判断力です。技術が変わっても、変革を実行する経営者の洞察力と決断力こそが、企業の生存と成長を決定する最も重要な要素となります。
3.第37話・38話から読み解く:現代企業のクリエイター戦略
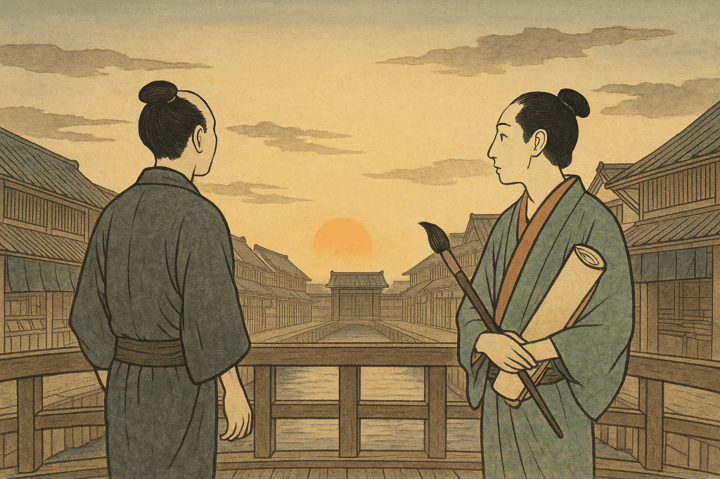
1. クリエイターエコノミー時代の人材マネジメント
第37話・38話を通じて描かれるのは、創造的人材の確保と活用が事業成功の決定的要因となる時代の経営課題です。現代のクリエイターエコノミーにおいても、同様の課題が存在します。
多層的な人材ポートフォリオ戦略
蔦重の失敗から学ぶべきは、特定のクリエイターへの過度な依存のリスクです。現代企業には、以下のような多層的な人材戦略が求められます。
・スター人材の確保と育成:歌麿のような突出した才能の発見と支援
・中堅層の厚みづくり:安定的な創作活動を支える中核人材群の形成
・新人発掘システム:継続的な才能発掘と育成のメカニズム構築
・外部ネットワーク:フリーランスや協力会社との柔軟な関係構築
リスク分散と事業継続性
京伝の離脱が示すように、キーパーソンリスクは常に存在します。現代企業には以下の対策が有効です。
・ナレッジマネジメントシステムの構築
・クロストレーニングによるスキル分散
・メンタリングプログラムによる知識継承
・危機時のコンティンジェンシープラン策定
2. パトロンシップモデルとダイレクト・エンゲージメント
歌麿の豪商との直接取引は、現代のクリエイターエコノミーにおけるパトロンシップモデルの先駆けといえます。
現代的パトロンシップの形態
・サブスクリプション型支援:Patreon、Fanboxなどのプラットフォーム活用
・企業スポンサーシップ:ブランドとクリエイターの長期的パートナーシップ
・クラウドファンディング:プロジェクトベースの資金調達
・NFTやデジタル資産:新たな価値創造と収益化手段
ダイレクト・カスタマー・リレーション
中間業者を排除した直接的な顧客関係は、より高い収益性と顧客満足度をもたらします。
・顧客ニーズの直接把握
・カスタマイゼーションの実現
・付加価値の最大化
・長期的な関係構築
3. 逆風時のイノベーション戦略
松平定信の規制強化という逆風の中で、蔦重が示した対応は現代企業にも応用可能な戦略的示唆に富んでいます。
ピボット戦略の実践
既存事業モデルが機能しなくなった際の方向転換
・資産の再評価:保有する人材・技術・ネットワークの新たな活用方法の発見
・市場ニーズの再分析:規制下でも存在する潜在需要の発掘
・ビジネスモデルの革新:従来の枠組みを超えた新たな価値提供方法
・リスク管理の高度化:コンプライアンスと創造性のバランス
おわりに:江戸時代の知恵から学ぶ現代ビジネス戦略
第37話・38話で描かれる蔦屋重三郎の経営危機は、現代のクリエイターエコノミーにおける企業が直面する課題と本質的に共通しています。優秀な人材の確保と維持、外的圧力への対応、新たなビジネスモデルの構築という課題は、時代を超えて経営者が取り組むべき普遍的なテーマです。
蔦重の事例から学ぶべき最も重要な教訓は、危機を変革の機会として捉える経営マインドです。京伝の離脱や規制強化という逆風の中で、歌麿という唯一の資産を最大化し、新たな可能性を見出そうとする姿勢は、現代企業経営者にとっても重要な指針となります。
また、パトロンシップモデルや直接顧客関係の構築といった戦略は、デジタル技術により実現可能性が大幅に向上した現代において、より大きな価値を発揮する可能性があります。中間業者に依存しない直接的な価値提供は、クリエイターと顧客の双方にとってWin-Winの関係を生み出すことができます。
現代企業にとって、クリエイティブ人材は競争優位の源泉であり、その確保と活用は経営戦略の中核を成します。蔦重の江戸時代から現代まで一貫しているのは、人材の価値を最大化し、変化する環境に柔軟に適応する経営力の重要性です。技術が進歩し、ビジネス環境が複雑化する現代においても、この本質的な経営能力こそが持続的成長の鍵となることを、蔦重の物語は教えてくれています。
【展示会情報】
船橋東武開店48周年「全館大誕生祭」特別企画『江戸から昭和のチラシ展』を企画制作
【特別企画】江戸から昭和のチラシ展
~よみがえる「江戸の愛嬌と艶」、懐かしい「昭和の活気」~
10月2日(木)~15日(水)午前10時から午後6時(15日は午後5時)まで東武百貨店 船橋店 7階3番地レストラン街特設会場にて開催。江戸から昭和にかけて実際に使用された「引札」を中心に、レトロでアートな世界観を体感できる展示を実施いたします。
.png?width=234&height=334&name=%E4%BC%81%E7%94%BB%E8%A1%A8%E7%B4%99%20(1).png)
Tokyo Tokyo(東京おみやげプロジェクト)について
https://tokyotokyo.jp/ja/action/omiyage/
江戸時代から明治時代に使われていた「引札(宣伝用チラシ)」には、当時の日本の文化や暮らしが色濃く反映されています。私たちは、この歴史的に貴重な引札のデザインを現代に活かすため、東京都が進める「東京おみやげプロジェクト」に参画し、伝統的な日本の魅力が詰まった商品の開発と販売を行っています。
東京都と民間企業が共同で開発した伝統的な工芸品から文房具、食料品など、東京旅行の思い出をもっと楽しくするアイテム「東京おみやげ」のPR・販売拠点「# Tokyo Tokyo BASE」(羽田空港)で販売しています。
引札の魅力や現代の広告や商品開発に引札のエッセンスを取り入れたい方は、お気軽にご相談下さいませ。