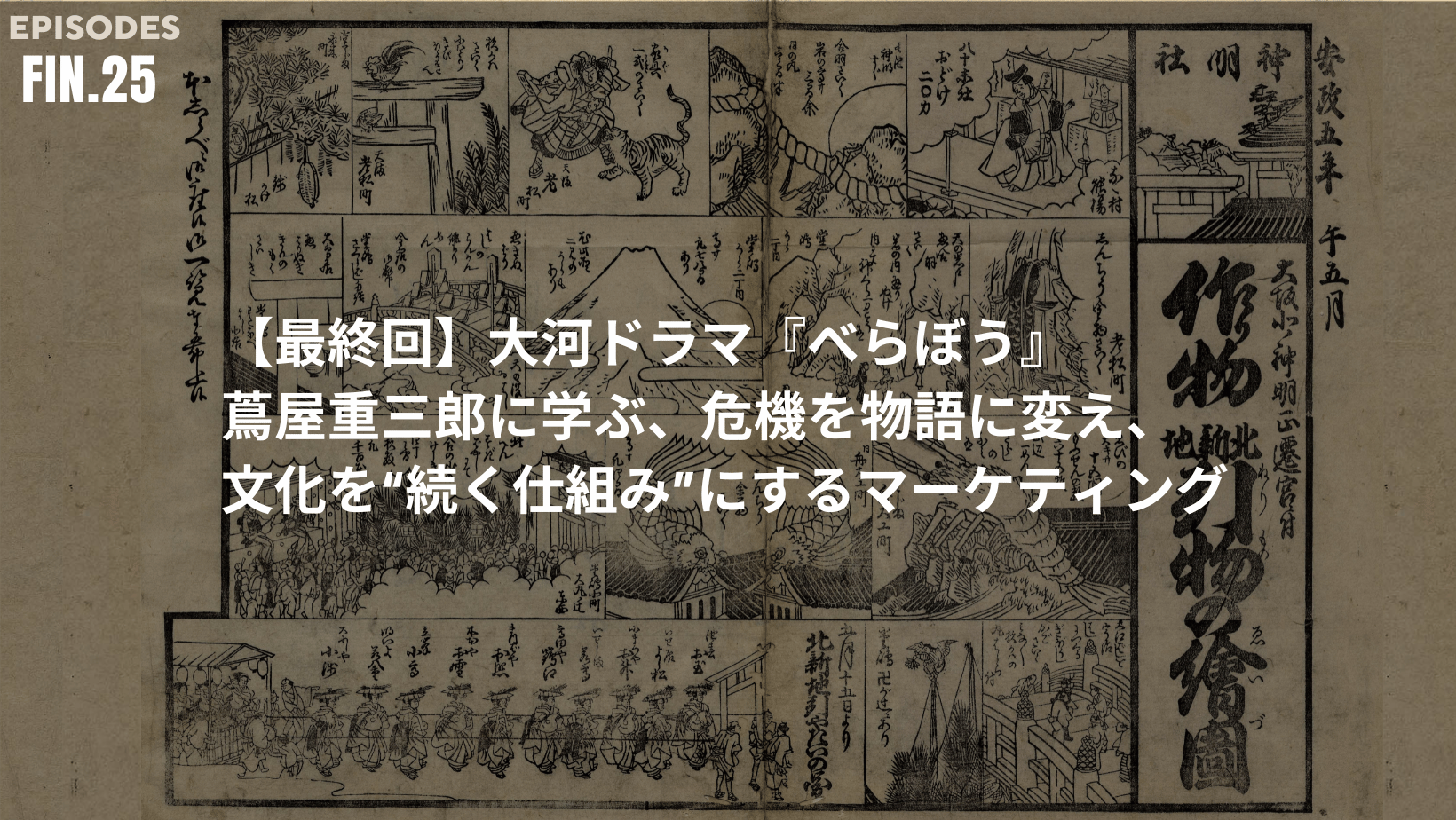大河ドラマ『べらぼう』蔦屋重三郎に学ぶ、バイラルマーケティングと表現規制対応戦略
2025年に放送されたNHK大河ドラマ『べらぼう ~蔦重栄華乃夢噺~』の第35話と第36話では、天明8年(1788年)の黄表紙ブームから寛政の改革による出版規制強化までの激動期が描かれます。この時期は、蔦屋重三郎が偶発的なバイラルヒットを経験し、その後の政治的弾圧に直面した重要な転換点でもありました。
第35話「間違凧文武二道」では、風刺作品『文武二道万石通』の意図しない誤読によって生まれた偶発的バズマーケティング現象が展開されます。一方、第36話「鸚鵡のけりは鴨」では、人気作品の絶版命令と出版規制の強化により、蔦重が直面した表現の自由と事業継続のジレンマが描かれます。
これらの物語は、現代企業が直面するSNSマーケティング、バイラルコンテンツ戦略、炎上リスク管理、そして規制環境下での事業運営について、深い示唆を与えてくれます。江戸時代の出版業から学ぶ実践的なビジネス戦略への応用可能性を探っていきます。

- 第35話「間違凧文武二道」:誤読が生んだバズと風刺の逆説
- 第36話「鸚鵡のけりは鴨」:弾圧下のリスクマネジメントと文化的抵抗
- 第35話・36話から読み解く現代の炎上対策とブランドマネジメント
- おわりに
1.第35話「間違凧文武二道」:偶発的バズマーケティングの威力

あらすじ
年が明けた江戸で、蔦屋重三郎が出版した黄表紙『文武二道万石通』(朋誠堂喜三二作)が大評判となります。この作品は鎌倉時代の忠臣・畠山重忠が武士を「文に秀でた者」「武に秀でた者」「役に立たぬ者」に分けて評価するという風刺の効いた物語で、重忠の着物には松平家の家紋(梅鉢紋)が描かれていました。
ところが松平定信は、この風刺に全く気づかず、自身が名将・重忠に例えられていると大感激します。定信は自分の政策が民衆に認められていると勘違いし、むしろやる気を高めて弓術指南所や湯島聖堂の改修など新たな改革に乗り出します。一方で、蔦屋のもとには定信の腹心が様子を伺いに現れ、監視の目が強まっていることも明らかになります。
また、歌麿とおきよとの静かな交流も描かれ、後の"笑い絵"(春画)誕生への布石が打たれます。町では田沼を揶揄する洒落や狂歌も広がり、文化・出版・政治が複雑に絡み合う状況が展開されます。
現代に通じるポイント
江戸時代の課題と対応策
『文武二道万石通』の成功は、意図した風刺が松平定信に誤読されたことで生まれた偶発的な現象でした。蔦重は権力者への批判を込めた作品を制作しましたが、定信自身がそれを自分への賛美として受け取り、むしろ改革への意欲を高めたのです。蔦重はこの誤解を訂正せず、むしろ流れに乗って更なる話題性を獲得する戦略を選択しました。
現代の課題と対応策
『文武二道万石通』の成功は、意図した風刺が松平定信に誤読されたことで生まれた偶発的な現象でした。蔦重は権力者への批判を込めた作品を制作しましたが、定信自身がそれを自分への賛美として受け取り、むしろ改革への意欲を高めたのです。蔦重はこの誤解を訂正せず、むしろ流れに乗って更なる話題性を獲得する戦略を選択しました。
蔦重の対応と現代のリアルタイムマーケティングは、「偶発性を戦略的に活用する」という点で本質的に同じです。どちらも完全にコントロールされたメッセージよりも、受け手の解釈や参加を促すオープンなコンテンツ設計が大きな影響力を生む可能性を示しています。現代の優位性は、デジタルツールによるリアルタイム監視と迅速な対応が可能な点ですが、人間の解釈の多様性と予測不可能性という本質的な課題は変わっていません。
江戸時代の課題と対応策
蔦重は検閲リスクを回避しながらも幅広い読者層にアピールするため、一つの作品に複数の解釈レイヤーを持たせる手法を開発しました。『文武二道万石通』では、表面的には歴史物語として政治的に無害な内容を装いながら、深層では現在の政治への風刺を込めるという二重構造を構築。これにより権力者には賛美として、庶民には批判として受け取られる巧妙な設計を実現しました。
現代の課題と対応策
現代のコンテンツマーケティングでも、多様なターゲット層に対して異なる価値を同時に提供する戦略が重要視されています。一般消費者には娱楽性を、コアファンには深い洞察を、専門家には技術的価値を提供するマルチレイヤー設計。特にSNSでは、シェアする文脈によって異なる意味が生まれるコンテンツが高いバイラル性を示します。
江戸時代と現代の比較
蔦重の多層的戦略と現代のコンテクスチュアルマーケティングは、「一つのコンテンツで複数の価値を創造する」効率性において共通しています。現代ではデータ分析により各セグメントの反応を詳細に測定できる優位性がありますが、異なる解釈を許容する「余白の設計」という本質的な創作技法は、江戸時代から変わらない重要な原則として継承されています。
江戸時代の課題と対応策
蔦重は既存の浮世絵市場の成熟化に対応するため、歌麿という確立されたクリエイターとおきよという新しい視点を持つ人物を組み合わせ、"笑い絵"(春画)という新ジャンルの開拓を企図しました。これは単なる商品開発ではなく、クリエイターの才能を新しい市場機会に結びつける戦略的パートナーシップでした。蔦重は歌麿に商業的成功を、歌麿は蔦重に芸術的価値を相互に提供する共創関係を構築していました。
現代の課題と対応策
現代のクリエイターエコノミーでも、企業と個人クリエイターが協働して新しい価値を創造する手法が主流となっています。重要なのは、単なる宣伝委託ではなく、クリエイターの創造性と企業のリソースを組み合わせた共創パートナーシップの構築です。インフルエンサーマーケティング、UGC活用、コラボレーション商品開発など、様々な形態で実践されています。
江戸時代と現代の比較
蔦重とクリエイターの関係と現代のクリエイターエコノミーは、「相互価値創造」という点で本質的に同じモデルです。現代では、デジタルプラットフォームにより個人クリエイターの発見と協働が容易になり、グローバルな規模でのコラボレーションが可能となっています。しかし、創造性と商業性を両立させる Win-Win関係の構築という根本的な成功要因は、蔦重の時代から変わらない普遍的な原則として継承されています。
2.第36話「鸚鵡のけりは鴨」:表現規制下での危機管理戦略

あらすじ
『文武二道万石通』をはじめとする蔦屋重三郎の黄表紙がますます人気となる中、松平定信の政策や人格を揶揄した内容が幕府の逆鱗に触れます。奉行所による蔦屋への強制捜査が実施され、『鸚鵡返文武二道』『天下一面鏡梅鉢』『文武二道万石通』の三作品に絶版命令が下されます。
一方、定信は業務改革で役人の賄賂を禁止したため、現場では多忙と不満が広がりますが、改革の理想が実際の業務に行き届かない状況が露呈します。江戸では出版規制の空気が強まり、喜三二は筆を折り、春町も身を隠す決断をします。他の戯作者たちも苦悩しながら、裏で江戸の文化を支え続ける姿が描かれます。
また、アイヌ蜂起と松前藩の失政、蝦夷地問題も並行して描写され、政治・出版・社会の三者が激しくぶつかる転機となります。
1. 炎上リスクとレピュテーション管理の重要性
江戸時代の課題と対応策
蔦重の黄表紙の大ヒットは、注目度の向上と政治的弾圧という表裏一体のリスクをもたらしました。『文武二道万石通』などの作品が松平定信の逆鱗に触れ、強制捜査と絶版命令という深刻な事態に発展。蔦重は全面的な抵抗ではなく、一部作品の犠牲を受け入れながら事業全体と人材を守る戦略的判断を行いました。表現の自由と事業継続のバランスを取る苦渋の選択でした。
現代の課題と対応策
現代企業もSNSでの話題性を狙ったコンテンツが、短期的な注目を集める一方で長期的なブランド価値を毀損するリスクに直面しています。重要なのは事前のリスク評価システムの構築と、炎上発生時の迅速な危機対応戦略です。AI活用による感情分析、ステークホルダーとの継続的対話、透明性のある説明責任の履行などが求められます。
江戸時代と現代の比較
蔦重の危機対応と現代のレピュテーション管理は、「短期的損失を受け入れて長期的価値を守る」戦略的判断において共通しています。現代では情報拡散の速度が格段に速く、24時間以内の初期対応が重要ですが、ステークホルダーの感情と利害を慎重に調整しながら事業の本質的価値を維持するという根本的なアプローチは、蔦重の時代から変わらない危機管理の本質といえます。
2.規制環境下での事業継続とコンプライアンス戦略
江戸時代の課題と対応策
寛政の改革による出版規制強化に直面した蔦重は、直接的な政治批判から間接的で創造的な表現手法への戦略転換を図りました。絶版となった三作品の教訓を活かし、検閲をクリアしながらも文化的価値と商業的成功を両立する新しい出版モデルの構築に取り組みました。規制を制約ではなく、より洗練された表現技法を開発する機会として捉える発想の転換が鍵でした。
現代の課題と対応策
現代企業も様々な規制(個人情報保護法、広告規制、プラットフォームガイドラインなど)に対応しながら事業価値を維持する課題に直面しています。重要なのは、コンプライアンスを厳格に遵守しながらも創造性と競争力を維持する「制約の中のイノベーション」です。規制対応を単なるコストではなく、新しいビジネスモデルや技術開発の機会として活用する戦略的思考が求められます。
江戸時代と現代の比較
蔦重の規制対応戦略と現代のコンプライアンス経営は、「制約をイノベーションの源泉に転換する」発想において本質的に同じです。現代では法令遵守がより複雑化し、グローバル対応も必要ですが、規制環境の変化を事業発展の機会として捉え、競合他社との差別化要因にする戦略的アプローチは、蔦重が示した普遍的な企業戦略の原則として現代にも応用可能です。
3.危機時の人材マネジメントとタレント保護
江戸時代の課題と対応策
政治的弾圧により喜三二が筆を折り、春町が身を隠すという人材流出に直面した蔦重は、残された戯作者たちのモチベーション維持と心理的サポートに注力しました。単に失われた人材を嘆くのではなく、「裏で江戸の文化を支え続ける」という使命感の共有により組織結束を図りました。同時に新しい才能の発掘と既存メンバーの能力開発により、組織力の再構築を進めました。
現代の課題と対応策
現代のクリエイティブ産業やスタートアップ企業も、市場変化や競争激化により優秀な人材が離脱するリスクに常に直面しています。重要なのは、「リテンション」「エンゲージメント」「アクイジション」を同時に展開する包括的人材戦略です。残存メンバーの心理的安全性確保、明確なビジョン共有、成長機会の提供、適切な評価・報酬システムなどが求められます。
江戸時代と現代の比較
蔦重の人材マネジメントと現代のタレントマネジメントは、「危機時の組織結束と価値観共有」において本質的に同じアプローチです。現代では、リモートワークやギグエコノミーにより人材の流動性が高まっていますが、共通の使命感と長期的ビジョンによる組織の求心力創出という根本的な人事戦略は、時代を超えて有効な普遍的原則として継承されています。
3.第35話・36話から読み解く現代企業のコンテンツ戦略とリスク管理
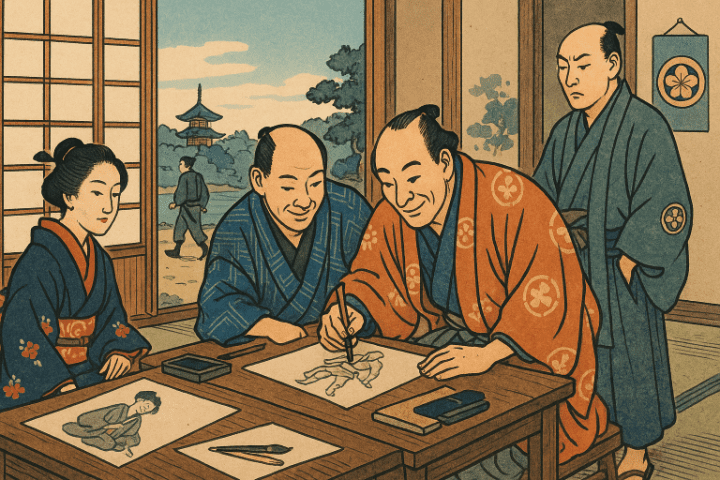
第35話・36話を通じて描かれるのは、コンテンツが持つ爆発的な拡散力と、それに伴うリスクの表裏一体の関係です。蔦屋重三郎の経験は、現代のデジタルマーケティングが直面する根本的なジレンマを260年も前に先取りしています。
1. 予測不可能性を前提とした戦略設計
| 江戸時代(蔦重の手法) | 現代企業の対応策 |
|---|---|
| 多層的解釈が可能な作品設計 | マルチプラットフォーム対応コンテンツ |
| 読者の創造的誤読を活用 | UGC(User Generated Content)の促進 |
| 政治的リスクの事前評価 | AI活用による炎上リスク分析 |
| 段階的な表現強化戦略 | A/Bテストによる段階的最適化 |
| クリエイターネットワークの構築 | インフルエンサーエコシステムの活用 |
蔦重は意図的に「読み手に委ねる余白」を作ることで、予測不可能な反応を戦略的に活用していました。現代企業も、完全にコントロールされたメッセージよりも、ユーザーの解釈や参加を促すオープンなコンテンツ設計が、より大きな影響力を生む可能性があります。
2. リアルタイム危機管理システムの構築
第36話で描かれる強制捜査への対応は、現代のデジタル危機管理と多くの共通点があります:
・早期警戒システム:蔦重は政治的な動向を常に監視し、リスクの兆候を早期に察知していました
・段階的対応戦略:全面的な抵抗ではなく、核心的価値を守りながら妥協点を見つける柔軟性
・ステークホルダーコミュニケーション:戯作者、読者、取次業者との継続的な関係維持
・事業継続計画:一部の商品やサービスを犠牲にしても、事業全体を存続させる戦略的判断
・代替戦略の準備:規制強化に備えた新しい表現手法や流通経路の開拓
3. 表現規制下でのイノベーション創出
規制強化という制約は、しばしば新しい創造性の源泉となります。蔦重が直接的な政治風刺から間接的で洗練された表現手法に転換したように、現代企業も規制をイノベーションの触媒として活用できます。
例えば、個人情報保護規制の強化は、プライバシーファーストの新しいビジネスモデルを生み出しています。広告規制は、よりクリエイティブで価値のあるコンテンツマーケティングを促進しています。プラットフォームのアルゴリズム変更は、新しい形態のコンテンツフォーマットを創出しています。
重要なのは、規制を「障害」ではなく「新しいルールの中での競争」として捉え、その制約の中で独自の競争優位を築くことです。
4. エコシステム全体の持続可能性
蔦重の取り組みで特筆すべきは、個社の利益だけでなく、出版文化全体のエコシステムを維持することを重視していた点です。戯作者の保護と育成、読者文化の継続的発展、政治的プレッシャーとの適切な距離感など、短期的な利益を超えた長期的視点での事業運営を行っていました。
現代のプラットフォーム企業やコンテンツ産業においても、この「エコシステム思考」は極めて重要です。クリエイター、ユーザー、プラットフォーム、広告主、規制当局など、多様なステークホルダーとのバランスを取りながら、業界全体の健全で持続可能な発展を目指す必要があります。
おわりに:江戸時代の知恵から学ぶ現代ビジネス戦略
大河ドラマ「べらぼう」の第35話・36話は、江戸時代の出版業を通じて、現代のデジタルコンテンツビジネスが直面する本質的な課題を鮮明に描き出しています。偶発的なバズマーケティングの威力と危険性、表現規制下でのイノベーション創出、そして危機時の戦略的判断など、時代を超えて通用する重要な示唆に満ちています。蔦屋重三郎の経験から学べる最も重要な教訓は、「不確実性を前提とした経営」と「多様なステークホルダーとの共生」の重要性です。完全な予測や制御は不可能であることを受け入れた上で、どのような状況変化にも対応できる柔軟性と、核心的価値を守り抜く一貫性を同時に持つことが求められます。
現代企業にとって、蔦重の物語は単なる歴史的事例ではなく、デジタル変革期を生き抜くための実践的な戦略指針として活用できるものです。技術は急速に進歩しても、人間の本質的な行動パターンや社会の基本的な構造には普遍的な要素が多く、江戸時代の知恵が現代ビジネスにも十分に応用可能であることを、これらの二話は明確に示しています。
特に注目すべきは、蔦重が示した「文化的価値と経済的価値の統合」という視点です。短期的な収益追求だけでなく、社会全体の文化的豊かさを維持・発展させることで、長期的な事業の持続可能性を確保するという考え方は、現代のESG経営やサステナブルビジネスの先駆けといえるでしょう。
【展示会情報】
船橋東武開店48周年「全館大誕生祭」特別企画『江戸から昭和のチラシ展』を企画制作
【特別企画】江戸から昭和のチラシ展
~よみがえる「江戸の愛嬌と艶」、懐かしい「昭和の活気」~
10月2日(木)~15日(水)午前10時から午後6時(15日は午後5時)まで東武百貨店 船橋店 7階3番地レストラン街特設会場にて開催。江戸から昭和にかけて実際に使用された「引札」を中心に、レトロでアートな世界観を体感できる展示を実施いたします。
.png?width=234&height=334&name=%E4%BC%81%E7%94%BB%E8%A1%A8%E7%B4%99%20(1).png)
Tokyo Tokyo(東京おみやげプロジェクト)について
https://tokyotokyo.jp/ja/action/omiyage/
江戸時代から明治時代に使われていた「引札(宣伝用チラシ)」には、当時の日本の文化や暮らしが色濃く反映されています。私たちは、この歴史的に貴重な引札のデザインを現代に活かすため、東京都が進める「東京おみやげプロジェクト」に参画し、伝統的な日本の魅力が詰まった商品の開発と販売を行っています。
東京都と民間企業が共同で開発した伝統的な工芸品から文房具、食料品など、東京旅行の思い出をもっと楽しくするアイテム「東京おみやげ」のPR・販売拠点「# Tokyo Tokyo BASE」(羽田空港)で販売しています。
引札の魅力や現代の広告や商品開発に引札のエッセンスを取り入れたい方は、お気軽にご相談下さいませ。


.png)