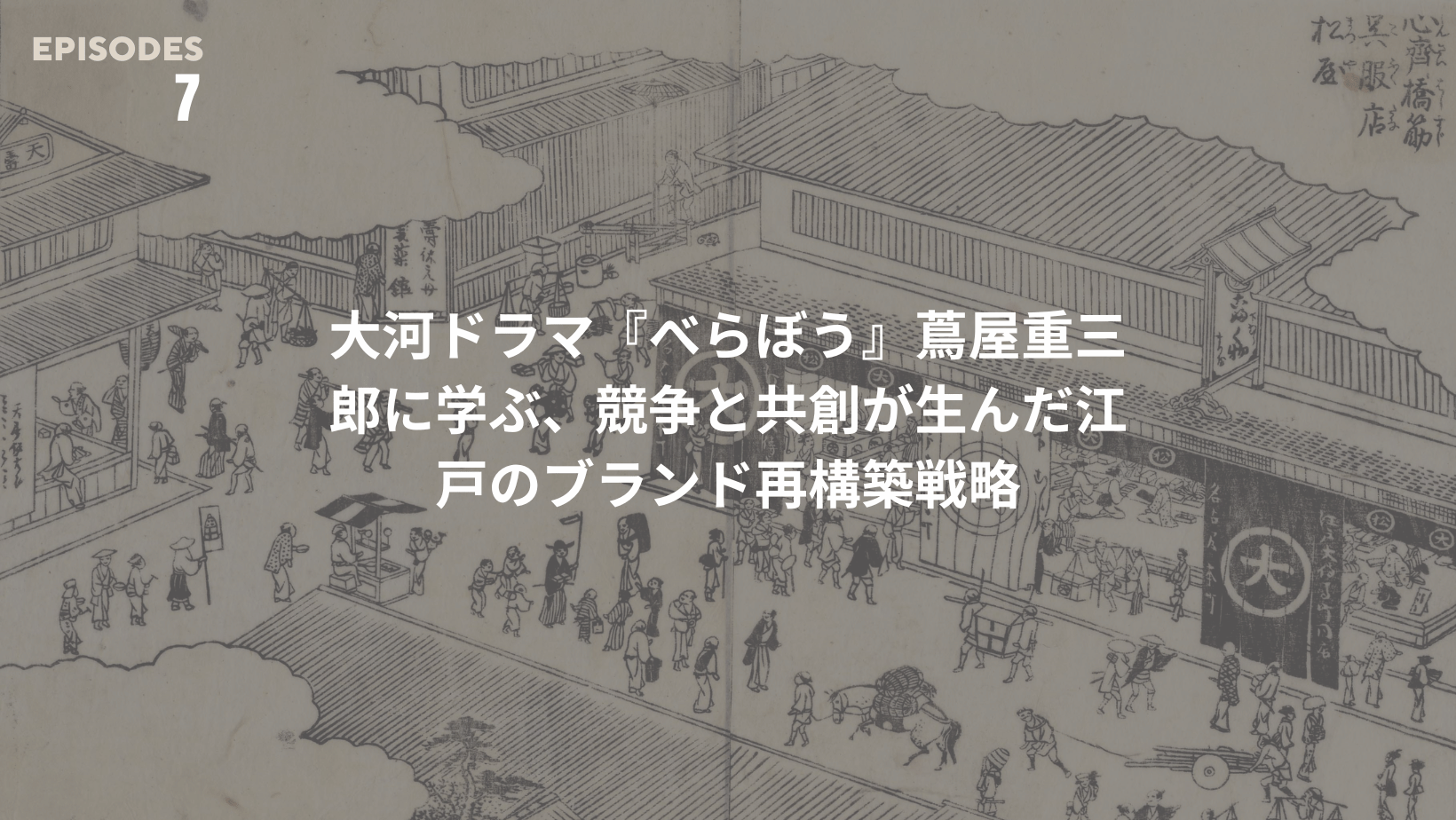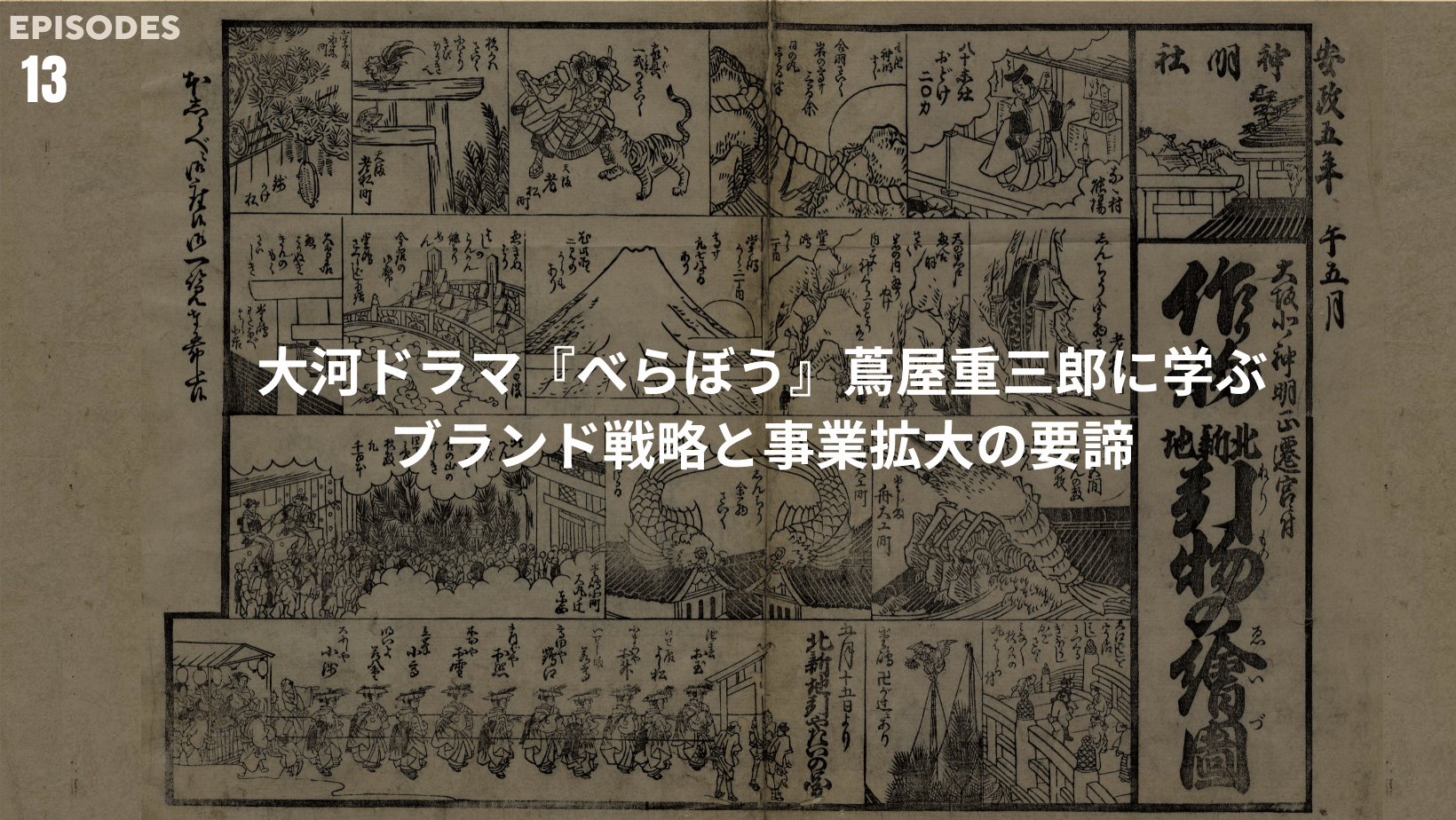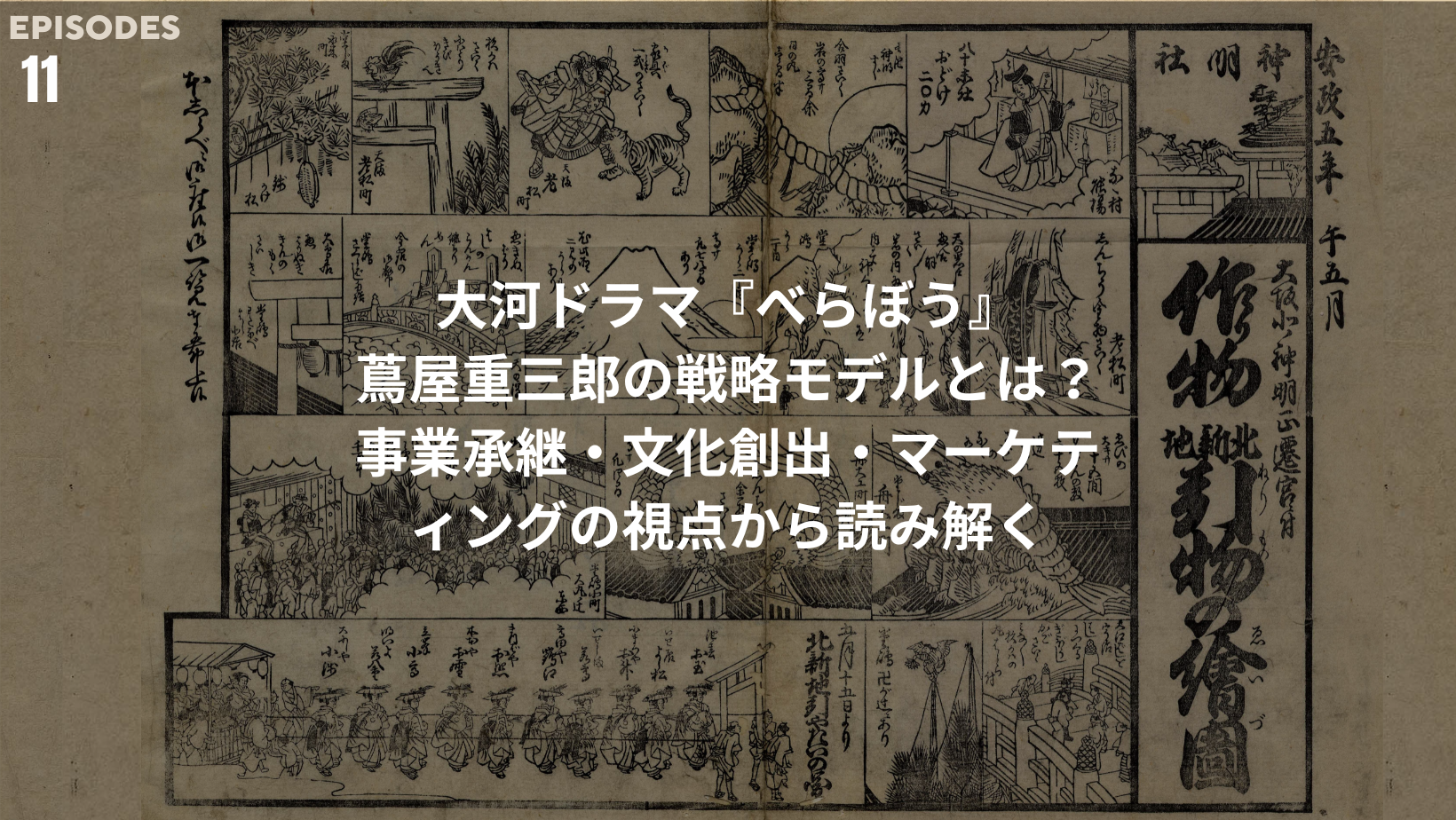大河ドラマ『べらぼう』蔦屋重三郎に学ぶ、江戸時代のプロモーション戦略・集客手法
大河ドラマ『べらぼう』では、江戸時代に活躍した蔦屋重三郎の商才とマーケティング手法が描かれています。これまでの記事では、第1話から第8話までの流れを振り返り、蔦重が吉原や出版業界で試みたマーケティング戦略を紐解いてきました。彼の手法には、市場環境の変化に対応する戦略、ブランド価値の向上、プロモーションの工夫 など、現代のビジネスにも通じる要素が数多く含まれています。
今回取り上げる第9話と第10話では、吉原の活性化を目指す蔦屋重三郎のさらなる挑戦が描かれています。市場環境分析やブランディング、PR戦略や体験型マーケティングなど、現代にも応用できる手法 を読み解きながら、江戸時代の広告革命を現代のマーケティングと比較していきます。
ep.1 大河ドラマで注目が集まる蔦屋重三郎とは?引札で江戸時代の広告革命を牽引
ep.2 大河ドラマ『べらぼう』に見る蔦屋重三郎のマーケティング戦略と現代的教訓
ep.3 大河ドラマ『べらぼう』蔦屋重三郎から学ぶ江戸から令和の広告戦略とマーケティングの本質
ep.4 大河ドラマ『べらぼう』蔦屋重三郎から学ぶコンテンツとデータ活用のマーケティング術
ep.5 大河ドラマ『べらぼう』蔦屋重三郎から学ぶ5つのマーケティング手法
ep.6 大河ドラマ『べらぼう』に見る蔦屋重三郎のプロモーション戦略と江戸の集客方法
ep.7 大河ドラマ『べらぼう』蔦屋重三郎に学ぶ、競争と共創が生んだ江戸のブランド再構築戦略
ep.8 大河ドラマ『べらぼう』蔦屋重三郎に学ぶ、信頼と理念で組織を再構築する経営戦略

第9話「玉菊燈籠恋の地獄」:市場環境分析とブランド価値向上

あらすじ
吉原遊郭と地本問屋の関係が悪化し、蔦屋重三郎が制作した『吉原細見』が江戸市中で販売できなくなる危機に直面します。この状況が続けば、吉原全体の客足が減少し、遊郭の経営が困難になる可能性がありました。さらに、蔦重は花魁・瀬川の身請け話に関与し、吉原を象徴する花魁の一人である瀬川の存在が遊郭のブランド価値を左右すると考えました。しかし、松葉屋のいねの厳しい管理のもと、蔦重と瀬川の関係は制限され、密かに貸本に手紙を忍ばせる形で想いを伝え合うことになります。その後、瀬川の身請け話が進行し、蔦重の願いは届かぬまま二人の道は分かれることとなりました。この一連の出来事は、市場環境の変化を的確に捉え、ブランド価値を守る重要性を示しています。
江戸時代の課題と対応策
かつては江戸随一の遊郭として繁栄していた吉原だったが、岡場所や宿場町といった新興の娯楽施設が台頭するにつれ、次第に客足が遠のいていった。特に岡場所は、格式ばらず気軽に楽しめる場所として庶民の間で人気を博し、これが吉原の衰退に拍車をかけた。さらに、吉原の案内書である『吉原細見』が地本問屋との対立によって販売できなくなったことで、吉原の魅力を伝える手段が制限され、集客の機会を失っていった。
この状況に対し、蔦屋重三郎は吉原のブランド価値を守るための戦略を模索した。まず、吉原の花魁たちを単なる遊女ではなく「高嶺の花」として位置づけ、特別感を強調することで高級遊郭としての格式を保つよう努めた。また、従来の情報流通に依存せず、貸本屋を活用して吉原の魅力を広める方法を考案するなど、新たなチャネルを開拓する動きも見られた。さらに、富裕層向けにサービスの質を高め、吉原が単なる遊び場ではなく「憧れの場所」として認識されるようなブランディングを強化した。
現代の課題と対応策
現代のビジネス環境でも、市場の競争激化や情報発信の制約は大きな課題となっている。特に、オンラインマーケティングの分野では、Googleのアルゴリズム変更やSNSの広告規制強化により、従来の広告手法が通用しなくなるケースが増えている。さらに、ターゲットとなる消費者の嗜好が多様化し、一つの戦略では効果が得られにくくなっている。
こうした状況に対し、多くの企業はブランディングの見直しを進め、独自の価値を打ち出すことで競争力を維持しようとしている。例えば、高級ブランドはプレミアムな価値を強調し、特定のターゲット層に焦点を当てたマーケティングを行うことで、ブランドの独自性を確立している。また、オウンドメディアやインフルエンサーマーケティングを活用し、従来の広告手法に依存しない情報発信を試みる企業も増えている。蔦重が吉原の新たな情報流通を模索したように、現代の企業も市場環境の変化に応じて柔軟な対応を求められている。
2.ブランド価値の向上
江戸時代の課題と対応策
吉原の魅力の象徴でもあった花魁たちが、高額な身請けによって次々と引き抜かれることで、吉原全体のブランド価値が低下する懸念があった。特に、瀬川のような人気花魁が身請けされてしまえば、吉原にとっての「顔」となる存在を失うことになり、その影響は計り知れないものとなる。
この問題に対し、蔦重は花魁を単なる遊女ではなく、吉原のブランドアイコンとして位置づけることで、ブランド価値を維持する戦略をとった。花魁を「憧れの存在」とし、その格式を守るために身請けの条件を厳しく設定することで、ブランドの流出を防ぐ工夫も行われた。
現代の課題と対応策
現代においても、ブランドの維持と差別化は重要な課題である。市場には数多くの競合が存在し、どの企業も類似のブランディング手法を採用することで、個々のブランドが埋もれてしまうリスクがある。さらに、Z世代を中心に「ブランドよりも体験を重視する」傾向が強まり、従来の「高級=価値がある」という図式が通用しにくくなってきている。
このような状況のなか、多くの企業は、単なる高級ブランドではなく「ストーリーを持ったブランド」としての価値を訴求する方向にシフトしている。たとえば、企業はインフルエンサーを活用し、そのブランドに共感する人々を増やすことで、消費者の心をつかむ戦略をとっている。また、ブランドの歴史や価値観を伝えるストーリーテリングを重視し、単なる「高級品」ではなく「そのブランドを選ぶ理由」を明確に伝えることで、顧客のブランドロイヤルティを高めている。蔦重が吉原のブランド価値を守るために花魁の存在を強調したように、現代でもブランドの独自性を打ち出し、消費者に特別な価値を提供することが求められている。
江戸時代と現代の比較
吉原が直面した競争環境の変化と、それに対抗するための戦略が描かれていた。市場環境の変化に適応しながらブランド価値を維持するためには、新たな情報流通の開拓や、ブランドの象徴となる存在を守る施策が必要だった。これは、現代の企業が競争の激化や情報発信の制限に対応するために、柔軟なマーケティング戦略をとることと共通している。
江戸時代の吉原も、現代のビジネス環境も、本質的には「競争の中でどうブランド価値を維持し、高めていくか」という共通の課題を抱えている。蔦屋重三郎の戦略を紐解くことで、現代のマーケティングにも応用できる重要なヒントを得ることができるのではないだろうか。

あらすじ
年の暮れ、花魁・瀬川の最後の花魁道中が決定する。吉原の親たちは、この道中に合わせて花魁たちの姿を描いた錦絵を制作するよう蔦屋重三郎に依頼。蔦重はこれを単なる記念ではなく、吉原全体のブランド価値を向上させる好機と捉え、新たな戦略を模索する。彼の狙いは、吉原の格式を再び高めることにあった。そこで、錦絵を将軍家に献上するという計画を立案し、田沼意次の協力を得てこの戦略を実現する。将軍が吉原の錦絵を受け取ったという事実が広まることで、吉原は「将軍も認める格式高い遊郭」としてのイメージを確立し、競争市場の中での優位性を築こうとしたのだった。
1. PR戦略:影響力のある人物への働きかけ
江戸時代の課題と対応策
吉原の格式が低下し始めるなか、蔦重はそのブランド価値を維持し、さらには向上させるために、将軍家への献上という「権威付け」の戦略を採用した。当時、将軍家に関わるものは、すべて特別な価値を持つとされていた。そこで、影響力のある田沼意次を巻き込み、吉原の錦絵を将軍に献上することで、「将軍も認める吉原」というイメージを確立しようとしたのだ。この戦略は、単に吉原の遊女たちの美を記録するだけでなく、江戸全体に向けて「吉原は格式高い場所である」というメッセージを発信する効果を狙ったものである。
この戦略が成功すれば、他の遊郭や岡場所との差別化が図れ、吉原のブランド価値が維持されるだけでなく、より富裕層や特権階級の客を引き寄せることが可能になると考えられていた。つまり、吉原は単なる遊興の場ではなく、文化的価値を持つ高級な空間であるというブランディングが施されていたのだ。
現代の課題と対応策
現代のマーケティングにおいても、影響力のある人物や機関を活用するPR戦略は広く用いられている。例えば、Appleは新製品を発表する際に、ハリウッド俳優や著名なインフルエンサーに製品を提供し、彼らを通じてブランドの信頼性を高めている。また、高級ブランドは、著名なデザイナーとのコラボレーションや、アカデミー賞やファッションウィークなどの格式あるイベントでの着用を通じて、ブランドのステータスを確立する戦略をとっている。
これは、蔦重が田沼意次を介して将軍家に錦絵を献上した戦略と本質的に同じである。影響力のある存在と結びつくことで、ブランドの価値を社会的に認知させ、他の競合との差別化を図ることができるのだ。吉原が「将軍も認める遊郭」としてブランド価値を高めたように、現代の企業も「有名人や権威のある機関が認めたブランド」としての地位を確立することで、市場における優位性を築いているのである。
2.プロモーション戦略:花魁道中と体験型マーケティング
江戸時代の課題と対応策
瀬川の最後の花魁道中は、吉原にとって単なる見世物ではなく、ブランド価値を再認識させるための重要なプロモーション施策であった。花魁道中は、多くの見物客を集めるだけでなく、「この華やかな空間に身を置くことが特別な体験である」という意識を植え付ける効果があった。
この戦略の本質は、視覚的なインパクトとストーリー性を活かした体験型マーケティングにある。道中の派手な衣装や美しい花魁たちの振る舞いは、見る者に「自分もこの世界に関わりたい」という憧れを抱かせ、結果的に吉原の集客につながる仕組みだった。瀬川という象徴的な花魁の最後の道中というストーリーが加わることで、その希少性と特別感が強調され、さらなる話題性を生むことができたのだ。
現代の課題と対応策
現代においても、企業は単なる広告ではなく、消費者が実際に「体験」できるプロモーション戦略を取り入れている。例えば、高級ブランドは、期間限定のポップアップストアを設置し、店舗では得られない特別なショッピング体験を提供することで、ブランドの魅力を強調している。また、テーマパークやエンターテインメント業界では、没入型のブランド体験を通じて、消費者の記憶に残るプロモーションを展開している。
これは、吉原の花魁道中が単なるイベントではなく、「吉原というブランドを体験させる」ための施策であったことと類似している。現代の企業も、消費者がブランドの世界観を体験できる場を作り上げることで、商品やサービスに対する興味を喚起し、ブランド価値を向上させているのだ。
江戸時代と現代の比較
蔦屋重三郎が吉原のブランド価値を向上させるために、「権威付け」と「体験型マーケティング」という二つの手法を駆使したことが描かれていた。将軍への錦絵の献上は、影響力のある人物と結びつくことでブランド価値を向上させる戦略であり、これは現代の企業が有名人や権威ある機関とコラボするPR戦略と通じる部分が多い。また、花魁道中という視覚的で華やかなプロモーションは、現代の企業が取り入れる体験型マーケティングと類似したアプローチであった。
このように、江戸時代の商業戦略は、現代のマーケティングの原型とも言える要素を多く含んでいる。蔦屋重三郎の手法を紐解くことで、ブランド価値の向上や消費者の興味を引くプロモーションの本質を理解し、現代のマーケティングに応用するヒントを得ることができるのではないだろうか。
9話・10話の江戸のマーケティングに学ぶ現代ビジネス戦略
1. 権威性を活用したブランド価値向上戦略
(第10話「将軍献上戦略」から学ぶ)
江戸時代の戦略:
蔦屋重三郎は、吉原の錦絵を将軍に献上することで「将軍も認める遊郭」というブランドイメージを作り上げた。これは、吉原の格式を向上させ、他の遊郭との差別化を図るための戦略だった。
現代の応用:
企業がブランド価値を高めるために、「権威ある存在との提携」を積極的に活用する。例えば、以下のような方法が考えられる。
・有名な機関や団体とのコラボレーション: 企業やブランドがISO認証を取得する、政府機関や国際的な認証機関からの承認を得ることで、信頼性を高める。
・著名なインフルエンサーやセレブリティとの提携: Appleが有名なハリウッド俳優を広告に起用する、ハイブランドがトップアスリートやデザイナーとコラボするなど、ブランドの「特別感」を演出する。
2. 体験型マーケティングによるブランド浸透
(第10話「花魁道中のイベントマーケティング」から学ぶ)
花魁道中は、単なる遊女の行列ではなく、吉原のブランド価値を高める「体験型プロモーション」だった。見物客が華やかな花魁道中を見ることで、吉原に対する憧れや格式の高さを感じさせる仕組みになっていた。
現代の応用:
消費者がブランドを「体験」することで、その価値を理解し、ファン化する戦略が有効。
具体的には、以下のような手法がある。
・ポップアップストアの活用: 期間限定のブランド体験型店舗を開設し、消費者が商品やサービスに直接触れられる機会を提供する。(例:ルイ・ヴィトンのポップアップイベント、スターバックスのコンセプトストア)
・メタバース・VR体験: 最新テクノロジーを活用した仮想体験型プロモーションを導入し、ブランドの世界観を消費者に提供する。(例:ナイキのバーチャル試着体験、ディズニーの仮想パーク)
3. ブランドストーリーを活かしたマーケティング
(第9話「瀬川のブランド化」から学ぶ)
吉原は、単なる遊郭ではなく「憧れの場所」であることを強調するために、花魁をブランドの象徴として活用した。特に瀬川のような人気花魁は、「ただの遊女ではなく特別な存在」として演出されていた。
現代の応用:
企業やブランドが単に商品を売るのではなく、「ブランドストーリー」を発信し、消費者の共感を得ることが重要。
・創業ストーリーを語る: 企業の理念や創業者の想いを発信し、ブランドに対する共感を生む。
(例:Appleがスティーブ・ジョブズのビジョンを前面に出す、パタゴニアが環境保護の理念を強調する)
(例:エルメスのバッグが職人の手作業で作られていることを伝える、スイスの高級時計ブランドが伝統の製造技術を強調する)
4. 競争市場におけるプレミアム戦略
(第9話「吉原の高級化と競争戦略」から学ぶ)
岡場所や宿場町といった低価格の競合が増えるなかで、吉原は「高級遊郭」としての地位を確立することで、競争に対抗しようとした。そのため、富裕層をターゲットにし、格式を守ることでプレミアムなブランドイメージを維持した。
現代の応用:
企業が競争市場において差別化を図るために、「価格競争に巻き込まれないプレミアム戦略」を採用する。
・ハイエンド市場の開拓: 低価格帯で競争するのではなく、高価格帯でブランド価値を高める。
・会員制・限定性: 誰でも買える商品ではなく、限定性を持たせることでブランド価値を高める。
まとめ
蔦屋重三郎のマーケティング戦略は、江戸時代の吉原を維持・発展させるためのものであったが、その手法は現代のビジネスにおいても非常に有効 である。権威付けの活用、体験型マーケティング、ブランドストーリー戦略、プレミアム市場の開拓 など、どの戦略も企業の成長に欠かせない要素となっている。蔦重の知恵を現代ビジネスに応用することで、競争が激化する市場の中でもブランド価値を高め、成功へと導くことができるのではないだろうか。
おわりに
今回の記事では、第9話・第10話を通じて、市場環境分析とブランド価値向上、PR戦略とプロモーションの工夫 という視点から、蔦屋重三郎のマーケティング手法を掘り下げました。江戸時代の商人が、厳しい競争環境の中でブランドを守り、新たな市場の創出を図っていたことは、現代の企業が競争優位性を確立するために取り組んでいる戦略と多くの共通点を持っています。
吉原の衰退を防ぐために、蔦重はブランド価値を高める施策 を講じました。花魁を「高嶺の花」として位置づける戦略、吉原の情報流通の制限に対抗するための新たなプロモーション手法の開発 は、まさに現代の企業が市場シェアを守り、ターゲット層の関心を引き続けるための施策と共通します。また、将軍献上というPR戦略 によって吉原の格式を再び高めた手法は、現在の企業が権威ある機関や著名人と提携し、ブランドイメージを向上させる手法 に通じるものでした。
蔦屋重三郎が築いた成功の方程式は、時代が変わっても普遍的なビジネスの原則 として生き続けています。私たちは、江戸時代のマーケティング手法から、現代のビジネスに応用できる知見を学び続けることが可能 です。
江戸時代のマーケティング手法を現代のビジネスに応用することで、競争の激しい市場の中でも強固なブランド構築と持続可能な事業展開が実現できます。今後も大河ドラマ『べらぼう』を追いながら、江戸時代の商業戦略が現代のマーケティングにどのように活かせるのかを探求していきます。
Tokyo Tokyo(東京おみやげプロジェクト)について
https://tokyotokyo.jp/ja/action/omiyage/
江戸時代から明治時代に使われていた「引札(宣伝用チラシ)」には、当時の日本の文化や暮らしが色濃く反映されています。私たちは、この歴史的に貴重な引札のデザインを現代に活かすため、東京都が進める「東京おみやげプロジェクト」に参画し、伝統的な日本の魅力が詰まった商品の開発と販売を行っています。
東京都と民間企業が共同で開発した伝統的な工芸品から文房具、食料品など、東京旅行の思い出をもっと楽しくするアイテム「東京おみやげ」のPR・販売拠点「# Tokyo Tokyo BASE」(羽田空港)で販売しています。
引札の魅力や現代の広告や商品開発に引札のエッセンスを取り入れたい方は、お気軽にご相談下さいませ。